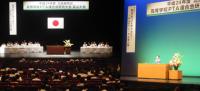刑務所の中の中学校日々雑記
20120717
一昨年、オダギリジョー、渡辺謙、大滝秀治らの出演したドラマをご覧になった方もいらっしゃるかと思います。PTAの研修会で、そのモデルとなった角谷敏夫さんの講演を聞きました。
日本でたった一つ、刑務所の中に中学校があります。さまざまな事情で義務教育を修了していない受刑者を対象にした、3年生1クラスだけの学校。松本市立旭町中学校の「桐分校」です。角谷さんは33年間、桐分校でクラス担任を務めました。
生徒は10代から70代まで、全国から集まってきます。中学校卒業を、自分の人生の軌道修正にしたいという思いを持ってきた人たちです。オリエンテーションで彼らに作文を書かせます。しかし漢字が思うように書けません。「先生、この漢字を教えてください」…この場で手の挙がる教えて欲しい漢字のベスト3は、べんきょう、どりょく、いっしょうけんめい、だそうです。
60分の授業を一日に7コマ。休息時間は昼40分、午前と午後にそれぞれ15分だけ。夜は自習3時間。夏休み冬休みなし。普通の中学生なら間違いなく音を上げるであろう学習量です。それにくらいついてゆく生徒たちの「知」への熱い欲求がうかがえます。
ひとつ押えておかなければなりません。彼らは「中学生」でありながら、受刑者です。自ら犯した罪への反省、被害者の苦しみや怒りをゆめ忘れることは許されません。桐分校で行われているのは、義務教育であるだけでなく「矯正」でもあるのです。
「遠足」として、本校である旭町中学校を訪問するプログラムがあります。家庭科室で「おやき」を作り、音楽室で本校の中学生たちと歌で交流します。このときの受刑者たちの感動は、毎年同行する角谷さんももらい泣きするほどだそうです。彼らは初めて自分の「母校」を深く胸に刻み込みます。それは心のふるさとです。
義務教育を受けていないというコンプレックスが、彼らの人生のつまづきの原因ともなっていました。勉強が彼らの心を、世界を広げてゆき、卒業と共にコンプレックスから開放されるのがまざまざと目に見えるといいます。
角谷さんの語り口は物静かで訥々としていて、見るからに謙虚な方で、自慢話めいたニュアンスはまったくありません。
角谷さんは教員になろうとしていたとき、「今いちばん教育を必要としている、学びたがっている人は誰か」という考えにとりつかれました。自問自答するうち、非行少年、犯罪者たちのためにと答えを出し、ただちに法務省の門をたたいてこの道を歩み始めたそうです。そうして、人生を刑務所の中の中学校に捧げることになりました。
この日角谷さんの口から聞いたわけではありませんが、一般刑法犯の再犯率はおよそ4割、しかし、桐分校卒業者の再犯率はほぼゼロに近いとのことです。
心に染みる話をお聞きしました。富山で先週聞いた「21世紀の日本が求めるグローバルな人材」の話と、この日の受刑者たちの話。これほどまでにと思われる極端な世界の違い、教育の幅の広さに、たじろいでしまいました。
8強!日々雑記
20120716
32年ぶりに球場に足を運び、柄にもなく母校の応援をしましたぞ。。
高校野球地区予選、今日は4回戦8試合が行われました。わが母校、今夏はノーシードから久々に3回戦を勝ち上がり、この試合に勝てば16年ぶりの8強となります。
球場は相手S高の地元とあって、完全アウェイかと覚悟して行きましたが、意外にも母校の応援団もかなり集まっていました!写真は試合前に応援団(保護者会)の方からいただいた「必勝パン」。中身はピーナツサンドでした。
序盤。いい当たりをいくつも飛ばしますが、野手の正面をついたり塁を埋めてもあと1本が出なかったりと、無得点が続きます。こちらのエースピッチャーはややコントロールに苦しんでいるように見えますが、要所を締め何とか得点を許しません。
それでも打線はいい当たりを連発し確実に相手投手を捕らえていますから、遠からず点が入るだろうと思っていた4回、ついに待望の先取点!2-0、応援席の沸くこと、沸くこと。
このまま行けばいいのですがそうは問屋が卸さず、母校も5回に捕まり、連打を浴びて同点に。さすがに古豪M商に完封勝ちしたシード高のS高、簡単には勝たせてくれません。2-2。
しかし追いつかれた次の回には、再びの連打で5-2!ここまでくると否応無く勝利を意識します。あとは3点のリードをいかに守りきってくれるのか?ここで投手が交代し、息子の同級生T君がマウンドに上ります。彼は小柄な体を一層丸めて投げるような変則っぽいフォームで、球威はともかく打たせて取るタイプでしょうか。緩急で勝負する感じ。
それが、ストライクが入らない。6回裏に早速1点を返され、本当にヒヤヒヤしましたが、T君は尻上りに調子を上げ、コントロールも良くなり、相手の打ち気をうまく散らして結局5-3で母校の勝利。ベスト8進出です!応援席はもう大盛り上がり、いやこんないい試合を見せてくれるとは…感激。結局12安打を放ちました。
考えてみれば私の高校時代は、ブラスバンドの常として夏の大会は必ず応援に行っていたわけです。残念ながら3年間のスタンド応援で、目の前で勝利を見た経験がほとんどなく(一度なんて延長戦の末「サヨナラホームスチール」で負けたことも…ワンサイドゲームならともかく、ホームスチールを目の前で見た人って、滅多にいないと思いますよ)勝利の嬉しさとはご縁が少なかった。そんなに弱いチームではなかったのですが、巡りあわせが悪かったのでしょうか。大学野球でも、勝利に居合わせたことはあまりなかったですねえ。
やっぱり、勝負事は勝ってナンボですよねえ。
準々決勝の相手は甲子園にも何度も出ている強豪で、客観的に見て力の差はかなりあるでしょう。おいそれと勝たせてはもらえないでしょうが、相手に冷や汗かかせる場面をいくつか作れるようなら、チャンスもゼロではないかもしれません。同じ高校生なんだもの。
試合は3日後です。
餃子のたれに…食べもの
20120711
突然ですが皆様、焼餃子には何をつけて召し上がりますか?
あまり真面目に考えたことがありませんでした。餃子を買うとついてくる小袋入りをそのまま使うか、そうでなければ普通の醤油にラー油を少々ってところでしょうか。子供の頃は「ウスターソース」をつけていました。変ですか。
こういうことを真剣に考えている人がいるのですね。先日ミツカンさんに試食会で試させていただいたのは、「酢と胡椒」で食べるやり方。東京赤坂の餃子の名店「珉珉」で勧めているんだそうです。酢にたっぷりの黒胡椒をかけて食します。
ホントかな、と思いましたが、これがなかなかの好相性です。私、ストレートな酢の味はやや苦手なのですが、不思議と酸っぱさは前に出て来ず、刺激よりも爽やかさを感じます。胡椒と肉とが合うのは当たり前、それに酢がうま~く割り込んできて、油っこさを中和しているような感じですね。
この場合、醤油は無しです。餃子には多かれ少なかれ下味がついていますから、醤油の味はわざわざ無くてもいいのかも知れません。(もともと薄味の餃子だったら、また別かも)
検索してみますと、珉珉でも最初からこうしていたのではなく、お客さんに言われて試してみたのが始まり、みたいな記述もありました。こうした食べ方の発祥はどこなのか、本場中国ではこうして食べているのかな?
ミツカンさんの試食ですから、使う酢を「末広」か「米酢」か「特醸優選」にするのか、ここがこだわりどころというわけです。比べるとそれぞれの酢で明らかに味が違います。どっちがいいかは、お店のセンス次第!
当社一押しのベストセラー、「ケンちゃん餃子」(冷凍)と合わせて、ぜひお試しを。
魚処やつはしお店紹介
20120709
富山に行けば必ず訪れる居酒屋がありまして、今回も同行した皆さんをお連れしました。「魚処やつはし」というお店です。富山湾の幸と地酒を堪能しました。
桜木町という、怪しげな夜のお店が立ち並ぶ一角に、ほんとにさりげなく構えている小さなお店です。気をつけていないと通り過ぎてしまいます。
この日は、大きな「のどぐろ」の塩焼き、生の岩牡蠣、絢爛たるお刺身盛り(甘海老、バイ貝とその肝、トビウオ、アイナメ、ワラサ、平目、マグロなど)、ゲンゲの唐揚げなどを戴きました。お酒は「立山」を常温で。みんなうまいうまいと杯を重ね、いや何杯飲んだろう…まったくよく飲んだもんだ!
のどぐろって魚は、本当においしいですね。白身ながら脂がしっかり乗り、なおかつ気品を忘れていないというか。大きくなるほど値は張りますが、比例しておいしさも増していきます。お刺身でも食べたことはありますが、やっぱり塩焼きがうまいです。あらゆる焼き魚の中で、最強の王者と讃えたい。骨までしゃぶったあと、頭を割って中のぷるぷるしたところまで、しっかり戴きました。
今の時期は何と言っても岩牡蠣。この濃厚で凝縮された旨さの塊を、日本酒に合わせる口福は、たまりません。(こればかりはワインってわけにはいきませんな)メンバーに、生牡蠣はちょっと苦手…という人がいましたが、大変喜んで食べてもらえました。産地ならでは、新鮮ならではの味です。
過去、家族でも二度ほど訪れていますが(奥に個室あり)当時まだ小学生の子供たちの喜んだこと。愛読書が魚類図鑑だった息子が目を輝かせて魚の話をしたことから、ご主人に船釣りに誘っていただきました。初めての釣り、少々船が揺れ、船酔いを我慢しながらもキスやらキュウセンやらを釣った体験は、忘れられないものとなっています。
今では息子さんに代を譲られたそうですが、そのご主人、まだまだお元気でお店に出ていらっしゃいました。たまたま夏しか行ったことがないのですが、冬のブリもそれは旨いと聞いています。太田和彦氏の著書でも紹介されているこの店、富山がもうちょっと近ければ、もっと頻繁に行けるのですがね…でもまたきっと訪れたいお店です。
関連リンク: 食べログ「魚処やつはし」
富山へ日々雑記
20120708
高校PTAの大会に参加するため、富山市に行ってきました。。
信州とは隣県ではありますが、長野市からならともかく、伊那からはとっても遠い土地です。北アルプス安房峠を越えてゆくか、はるばる上越市を回っていくか。安房峠でも3時間半、上越なら4時間はかかります。「北信越」というくくりで富山、石川、福井の大会などに参加することがありますが、いつも「俺たちゃ日本海の人間じゃないよ」と思うものです。
私はずっと訪れる機会のない街でしたが、12年前JCの大会で初めて行きました。富山市はコンパクトで都会的な魅力もあり、食べ物もおいしく、なかなか好印象でした。路面電車が走っているのもいいですね。
ガイドブックには殆ど載っていないようですが、市庁舎に無料で上れる展望台があるのを偶然見つけました。市内ではかなり高い位置にある展望台でしょう。残念ながら天気は良くなかったですが、ボランティアの方が眺望や歴史を解説していただいたり。夜9時まで入場できるそうで、観光やデートの穴場だと思います。
この市庁舎にしても、大会が行われた富山市芸術文化センター「オーバードホール」にしても、富山城を復元した「富山市郷土博物館」の展示にしても、実にゴージャス、バブリーなにおいがプンプンして、いやいや内緒の話。
大会は1400人の参加者を迎えて盛大に行われました。小中学校のPTAではこうした大会には地区(郡市)の代表たちが参加していましたが、高校のPTAは学校数そのものが少ないですから、原則として全ての学校からの参加となります。
基調講演は、ベストセラー「女性の品格」で有名な昭和女子大学学長の坂東眞理子さんにより「日本が必要とする21世紀人材」と題して行われました。
グローバル化の中、世界で生きていける人材に求められる資質は何か。健康、体力から始まって、努力を面倒がらないこと、行動力、持続力、知的好奇心、論理的思考、協力、親切、明るいこと、語学、基礎学力、コミュニケーション能力、高い志や人間愛まで、尽きることなく次々と語られました。それだけ兼ね備えていれば、世界どころか宇宙ででも生きていけるだろう…というのは、凡人の僻み。
それはともかく、今の子はとても恵まれているが、与えられすぎ、豊かすぎの環境は子供の向上心を摩滅させる、不自由から学ぶことこそが大切だ、という大変耳の痛い指摘をいただき、深く反省しました。やたらと車で子供の送り迎えをしてはいけませんね。妻にも言っておきましょう。
パクチー食べもの
20120704
香菜、シャンツァイ、コリアンダー。アジア料理には欠かせないハーブですが、日本人にとっては人によって極端に好き嫌いの分かれる食材でもあります。よく、カメムシのにおいがするなんて言いますね。少しでも入っていれば嫌いな人はすぐに気がついてしまうでしょう。
でも私も家族も大好き!文字通り香り高く、青臭さと芳香が入り混じって独特の風味を醸しています。
この辺のスーパーの店頭ではまだまだ市民権を得るに至らず、ほとんど見かけることがありません。一度か二度、直売コーナーに並んでいるのを見たことはありますが。
売ってないなら自前でと、我が家ではプランターで栽培しています。育て始めたばかりの頃、もうそろそろいいかなと思った翌日、鳥に全部食べられてしまった悔しい経験がありました。鳥もちゃんと、食べどきを分っています。
最近は食べられることもなく(何でだろう?)ちょうど今、花が咲いています。焼そばやチャーハンや冷奴のたびに、むしってきてはワサワサとかけて食べています。花も食べられますよ。
家族でたまに行くタイ料理屋さんでは、わざわざ「パクチー入れて!」と言わなくては入れてきません。やはり嫌がる客が多いのか。タイやベトナムでの私の経験では、これらが入っていない料理の方が少ないような印象があります。
東京銀座の「マルディ・グラ」というレストラン(とっても美味しく楽しい店!)には、その名も「香菜の爆弾」というパクチーだけを使ったサラダがあり、名物になっていました。もう何年も行っていませんが、今でもメニューにあるのかな。経堂に「パクチーハウス」というパクチー専門の料理店があるそうですが、まだ行ったことがありません。
以前書きましたが、2年前タイへ行ったとき、同行者の全員がパクチーOKだったのには少しびっくりしました。それだけ食べ慣れた人も増えているのですから、スーパーさん、店頭に少しばかり並べてみてもいいのでは?
見かけがちょっと似たものに「イタリアンパセリ」がありますが、私はこれが苦手です。こちらの方がパクチーよりよっぽど癖があると思います。イタリアンパセリを食べられる人は、パクチーだってきっと食べられるんじゃないでしょうか…
しばしのお別れ食べもの
20120630
ちょっと忙しくて、更新間隔が空きがちになっております、すみません。
皆様ご承知の通り、牛のレバ刺しが、今日6月30日を最後に提供できなくなりました。O-157への感染を完全に排除できないというのが理由です。レバーの表面は除菌できても、内部にあるものは取り除けない、といいます。
以前ユッケをめぐる騒動の記事を書いたときに、私が予想した通りになってしまいました。たった1企業の馬鹿者がしでかしたとんでもない中毒事件のために、日本中の誠実な焼肉店さんと生肉ファンたちが被った迷惑たるや、計り知れません。
繰り返しますが、人は本来、自分の欲するものを食べたいように食べる権利があります。よほどの理由がなくては、それを規制することは望ましくない。ユッケやレバ刺しには相応のリスクがありますが、過去の食中毒の統計などを見てもその他の食品と比べてこれらのリスクが飛びぬけて高いとは思いません。
とりあえず禁止してさえおけば問題は起きない(行政が文句を言われることもない)くらいの考えで敷かれた規制が、世の中を一歩一歩、確実に窮屈にしていきます。
しかしこういうのは、ゼロリスク信奉がはびこる世の中での、一つの帰結なのかもしれませんね。自分が食べるものには、0.000001%のリスクも認めたくないという身勝手な考え方。我々の口に入るものは何であろうと、すべて自然の恵みを分けていただいているのであって、人間のために地球上にわざわざ用意されたものではない、ということに気づいてほしいと思います。
素人によく分らないのは、肝臓内部のO-157って、どの位の頻度で出現するのでしょう。どんな牛のレバーでも同じように生食しているわけではないと思うんですが…飼育される牛の生育条件とか、そういうのは関係ないんですかね。放射線の照射によってレバー内部の細菌を殺すことも研究されているようです。
私がレバ刺し好きなので恨み言を言っているわけではありません。むしろ苦手としている食べ物で、過去たまたま口にして美味しかった経験は何度かありますが、その後も自らオーダーすることはなく今日まで来ています。
TVで「街の声」を聞くと、自分は食べないしどうでもいいんじゃないですか、という人が必ずいます。だけどそうじゃない。自分には関係ないからいいや、と思う方、次の俎上に上るのは生牡蠣、鶏刺し、生卵、野生の茸、お餅(?!)かもしれませんよ。そのときになって慌てても、あなたの味方をしてくれる人はいるでしょうか。
今回の規制には業界団体の反対はもちろん、各紙の社説などでも多くの反対意見が出されています。消費者のご機嫌取り的スタンスに立つことの多いマスコミには珍しいことです。今後そう遠くないうちに生レバーの提供が復活することを心から願いながら、しばしのお別れを迎えたいと思います。
関連リンク: レバ刺し禁止 食の文化も忘れずに (東京新聞社説)
火事日々雑記
20120625
午後、市内で大きな火事が。防災放送で、私共のお得意様の名前が伝えられたには驚きました。慌てて車で飛んで行くと…
もう建物は完全に炎に包まれており、消防も手の施しようがないような事態です。結局、お店を全焼してしまいました。営業中の火事でしたが、怪我人のなかったことが不幸中の幸いでした。
原因はまだ私はお聞きしていませんが、近所の人たちが爆発音を聞いているそうで、ひょっとしてガス?どうなのでしょうか。
これから書き入れ時を迎える筈だったご主人。まだ若い方です。ご無事な様子を遠目で見ましたが、言葉のかけようがありませんでした。まったくお気の毒です。
火事は本当に怖い。一切合財が灰燼となってしまう恐ろしさ。肝に銘じなければなりません。
会社のほうは消火器や火災報知機の設置など、法令に従ってちゃんとやっている筈です。そもそも暖房や賄い以外では、火気を扱う事業所ではありません。でも、正直私だって消火器を使ったことがない…1000年に一度の大地震の備えよりも、こっちの方が先ですね。
50年祭日々雑記
20120624
このブログではときどき同窓会の話題を書いています。昨日は中学の同期卒業生が、50歳を記念して集まりました。
駒ヶ根市では、中学の卒業生たちが数え年42歳の厄年に再会し、まとまった形での同年同窓会を組織することになっています。通称、厄年会。私たちの同窓生は300人を少し超えるくらいの人数がおりますが、これだけの規模の同窓会が全ての年代にわたって組織的に動いている地域は少ないと聞いています。
厄年、その翌年に一年間の無事を感謝して「おふだ返し」、それからちょっと間を置いて60歳の還暦と、3回大きな会を開くのが通例です。今回はしかし「60歳まで待てないよお」との声が高く、50歳にて中間イベント的に開催しました。
100人近くの人が集まり、その後クラスごとに分れての二次会も、より多くの参加者を迎えて、深夜まで駒ヶ根の街を賑わしたようです。私も久しぶりに午前様でした。
私のクラスは40人中20人が二次会に参加、当時の担任の先生(お元気!)も参加していただきました。卒業以来何十年ぶりに会う人もいて、大変懐かしかった。中にはこの年で4人の孫持ちという人や、一方でこれから結婚するという人もおり、羨ましがられたり冷やかされたり。同年生ってのは、見かけの上ではあまり年を取りませんね。大きく変身していた人はいなかったな。
このクラスはとても仲が良く、居心地の良いクラスだったと思います。みな50歳を迎え落ち着いてきて、大人の話ができるようになったはずですが、出てくる話題はやっぱり、昔の馬鹿っ話ですね。
良き仲間たちよ、いつまでもますます元気で。
県粉卸組合 総会しごと
20120621
台風4号、どうやらこの地域のほぼ真上を通過していったようですが、実感としては「普通の雨降り」でした。いつもながら中央アルプスと南アルプスにしっかり護られています。ありがたいことです。
さて昨日は松本で表記の会議。現在私が組合長を務めており、今回で3度目の総会を迎えました。決算予算などのほか、県内の小麦粉卸売業者と、製粉メーカーさんとの懇談を行ないました。
食品卸売業の業界団体というのは(少なくとも長野県では)それほど多くなく、当社が参加している数少ない団体の一つです。今期で「第50期」だそうで、私の生まれた頃から続いているのですから、少し驚きます。昔の業界と今とでは、当然ながらずいぶん様変わりしていることでしょう。当時を知る長老の方がおられたら、ぜひお話を聞いてみたいものです。
組合長は自動的に、県を代表し全国組織の理事として出ていくことになっています。こちらも年1回、6月初めに東京で総会があります。
そこでは全国各地の情勢報告をお聞きしますが、国の小麦制度が大きく変わりつつある中で、物流商流を担う卸の機能をもっと評価して欲しいという声ばかりです。苦労はどこも一緒だな…と思います。
そんな中、いま花盛りの「ご当地B級グルメ」についての話がありました。売り出し中のB級グルメのうち八割方は、粉モノです(中でも焼そば系の多いこと!)。その多くは自治体や商工会議所、飲食店組合などの主導で動いていますが、もっともっと粉業界としてそこへコミットするべきではないかと。
まったくその通りですよね。そうした積み重ねが、新たな消費を生み育ててゆくのでしょう。この分野にも、まだまだいろいろ新しい種があると、心強い発見になりました。