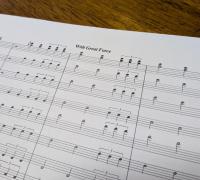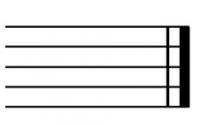12269人のバンド音楽ばなし
20250513
一万人を超えるマーチングバンド。どんな音がしたのでしょう。
------------------------------------------
(読売新聞)大阪・関西万博会場(大阪市此花区)の大屋根リングで11日、関西を中心に集まった1万2269人が行進曲「星条旗よ永遠なれ」などを演奏し、「最大のマーチングバンド」としてギネス世界記録に認定された。(中略)小中高校など約300校の吹奏楽部や一般の楽団から演奏者が色とりどりの衣装や制服で参加し、1周2キロの大屋根リングを時計回りに行進しながら10分以上、管楽器や打楽器によるハーモニーを響かせた。
------------------------------------------
何度か書いていますが私はパレードを見るのが大好きで、消防の出初式(れっきとしたマーチングバンドでしょう)で喇叭と太鼓の音が聞こえてくるとすぐ家を飛び出して見に行きます。
先日東京に行った折、新宿の書店で本を物色していましたら賑やかな音が聞こえてくる。通りに出てみると、交通安全キャンペーンのイベントで警視庁音楽隊がパレードをしています。曲はスーザの「エル・キャピタン」、さすがに上手です。以前ここの音楽隊長を務めていた大学の先輩を思い出しました。
閑話休題、リンク先に今回の万博巨大バンドの動画があります。12269人の演奏するタイミングとテンポをどうやって合わせるのか、どこかにリーダーがいて大画面で指揮を見せるのか? 何百メートルも離れたところで演奏するなら時差が出るのは間違いない。興味津々で観ましたが、何てことはない、合わせようとする気も(あまり)ないですね。各バンド見事にてんでんバラバラでした。ま、無理なものは無理だ。
ピシッと決まったユニホームの団体もあれば、私服でゆるく参加している団体もあり、それぞれです。参加した皆さんにとっては珍しい体験で面白かったのではないですか。あの大きなリングの上を行進演奏することなんて、なかなかできないことだし。
ただ気になるのは、曲目です。何で「星条旗よ永遠なれ」なんですか?学校をはじめとするあちこちの吹奏楽団でこの曲がいま異常に推されているのは、かつて指揮者の佐渡裕氏と「題名のない音楽会」がやたらと取り上げたのがきっかけだと思います。
この曲はよくできた行進曲ではありますが、タイトル通り、アメリカの愛国曲ですよ?日本で開催される万国博覧会の会場で、こうしたイベントで演奏するのは変でしょう。日本の曲でやってほしかったですねえ。
関連リンク: 大阪サンスポちゃんねる
フォースと共に音楽ばなし
20250508
今年のゴールデンウィークは前半後半がはっきり分かれています。11連休を楽しめる人は羨ましいですが、そうでなくても気持ちの良い季節に連休を楽しめることは貴重なことですね。当社のお客様も書き入れ時ですから、しっかり稼いでいただきたいものです。
いろいろなイベントが開かれているわけですが、わが伊那フィルも連休初日、伊那文化会館主催の「伊那ぶんぶん子どもまつり」に参加してオープニングのミニコンサートを行いました。
野外での演奏ということで天候が心配され(弦楽器や木管楽器は太陽の日差しにも雨にも弱い)小雨でも中止という前提で準備されましたが、幸い当日は暑からず寒からずの良い天気に恵まれました。
どなたも聴いたことがあるであろうポピュラーなクラシックや映画音楽を4曲演奏し、来場した(そう多くはない)親子連れなどのお客さんに楽しんでいただきました、たぶん楽しんでいただいたと思います。
「スター・ウォーズ」組曲から2曲を演奏しましたが、ちょうど本番前夜、TVで「エピソード4/新たなる希望」を放映していたという偶然。連休中もいろいろな場面でスターウォーズがやたらと目につくと思っていたら、5月4日が「スターウォーズの日」になっていたんですって。いつからなんだろう、初めて聞きました。
第1作の公開記念日かと思ったら、映画の名台詞「フォースと共にあらんことを May the Force be with you」が、May the 4th と語呂が似ているからなんだと。ふーん、だから何なん…
使った楽譜は作曲者ジョン・ウィリアムスが書いたオリジナルスコアで、きちんとやろうとすると大変難しいのですが、途中にWith Great Forceという指示が出てきます。スコアを見たときは笑ってしまいました。否が応でも力の入る曲想の場面で、なるほどと思います。ほかの曲にも応用できる発想記号(テンポや表現方法を指示する音楽用語)かもしれません。
ストリートピアノ騒動音楽ばなし
20250328
大阪で「ストリートピアノ」の設置者が利用者に注意喚起を呼びかけたTwitterの書き込みが炎上し、結局ピアノ自体を撤去することになってしまったそうです。。
--------------------------------------
(設置者の書き込み全文)ストリートピアノ演奏者の方へ
【お願いです】練習は家でしてください。
この南港ストリートピアノはフードコートの中にあります。つっかえてばかりの演奏に多くのクレームが入っており、このままだとこのピアノを撤収せざるを得ない状況です。
練習は家でしてください。練習を重ねてつっかえずに弾けるようになってから、ここで発表して頂けたら幸いです。誰かに届いてこそ「音楽」です。手前よがりな演奏は「苦音」です。
--------------------------------------
ストリートピアノは生活に潤いを与えてくれるものだと、私も好ましく思っています。この件ではたくさんの人が様々な書き込みをしていて興味深いのですが、誤解をされている人も多いようです。
このピアノはフードコートの中に置かれていたとのこと。そこで飲食する人は嫌でもピアノの音を耳にすることになり、聴く聴かないを自分では選べません。「つっかえてばかりの演奏」を聴きながら食事をしたくない人は当然いるでしょうし、その人たちの気持ちは尊重されるべきです。これは「ストリートピアノ」とは性格が違うでしょう。
興味を持った人が自分の意思でふと足を止めて聴くことができるのが本来のストリートピアノではないかと思います(ピアノの周囲に住む人は別ですが)。設置者にその区別ができていなかったのがトラブルを生んだと言えましょう。
演奏の上手いヘタはあっても、上手くなければ弾いてはいけないわけではありません。誰もが気軽にピアノにアプローチできることがストリートピアノの良さ、楽しさです。
ただ思うのは、置かれたのが公共の場だということ。「弾く人」と同時に「聴く人」がいるのです。弾く人には、自分が鳴らしている音を聴いている人の存在を意識していただきたい。間違えてはいけないなんて全く思いませんが、「練習」のつもりでストリートピアノに向かうのはちょっと違うんじゃないかな。たとえヘタでも、自分の演奏を聴いてみてねという姿勢があれば、つっかえつっかえでも聴く人は快く思ってくれるのではないでしょうか。
弾く人聴く人がお互いを尊重する気持ちになってこそ、ストリートピアノは真価を発揮します。ピアノに限らず街頭での演奏に接する機会がまだまだ少ない日本では、そのような文化の醸成(大きく出たね)には時間がかかるのかもしれません。でもまだ始まったばかり、今回のような軋轢を経ながら、一歩一歩進んでいけばなあと思います。
佐野成宏氏、逝去音楽ばなし
20250113
駒ヶ根出身で世界で活躍したオペラ歌手、佐野成宏氏が59歳という若さで今月10日に亡くなりました。急性心不全とのこと、あまりにも早い訃報に驚くばかりです。
佐野氏は中学校から合唱を始め、大学生時代にアマチュア合唱団の名門「武蔵野合唱団」で活動していました。そこで指揮者の小林研一郎氏に才能を見出されプロの声楽家を志し、東京芸大の声楽科に入り直してイタリア留学するなどめきめきと力をつけていきました。
輝く美声と豊かな声量で国内外のオペラやコンサート公演で重要な役を次々と演じ、日本を代表する名テノールとして活躍しました。お正月恒例のNHK「ニューイヤー・オペラコンサート」(クラシック界の紅白歌合戦みたいなものです)にも主役級で出演していました。もちろん駒ヶ根でもたびたび演奏し、私もナマで何度も聴いています。20数年前に初めて聞いた時の歌声は、それまで様々なオペラ公演で名歌手の歌に接していた私も驚くような素晴らしいものでした。
残念ながらその後、彼は体のコンディションに変調をきたし、全盛時の声を再び聴ける機会は私にはありませんでした。演奏活動をしばらく休止していた時期もあったようです。それからは後進の教育活動に重きを置くようになり「駒ヶ根高原音楽祭」という若手育成のレッスンと発表会+コンサートを当地で何年も開いていました。
佐野氏は私の妹とかつて同級生だったのですが、病気で長期欠席するなど昔は体の弱い子だったと聞きます。プロの歌手になってからもそのハンディは彼を苦しめていたのではないでしょうか。堂々たる体躯を支える心臓の負担はきっと相当なもので、急逝したのもあるいはそのせいもあったかもしれません。
地元出身で世界に通じるオペラ歌手が生まれたことがとても嬉しかったのですが、第一線で活躍できた期間があまりにも短かったことが悔やまれます。本当に惜しいことでした。
ああ!新世界音楽ばなし
20241029
子供の頃に観たドラマです。調べてみると倉本聰の脚本によるもので、75年の東芝日曜劇場で放送され、優秀作品に与えられる「ギャラクシー賞」を受賞しました。子供心にたいへん印象的でよく中身を覚えています。記憶違いがあるやもしれませんが、以下ネタバレで。
…主人公(フランキー堺)はかつてプロのオーケストラの打楽器奏者だったが、音楽の道をあきらめ北海道に移住し、不本意ながらサラリーマン生活を送っている。職場にも地域にも溶け込めない悶々とした日々。理解者はやはりオケ奏者だった妻(南田洋子)だけ。
そんなある時、以前在籍していたオーケストラが演奏旅行にやってくることが決まった。彼は打楽器のエキストラ奏者として、演奏会のステージに乗ることになる。曲はドボルザークの交響曲第9番「新世界より」。この曲にはたった1発だけのシンバルの出番があるのだ。
一発といえども地元の友人たちにいいところを見せるべく張り切るフランキー。日頃さえないフランキーが活躍する姿を見てやろうと、好奇心満々で集まる友人たち。冷ややかなかつてのオケ仲間。夫の夢が最後にもう一度かなうことを願う妻。いよいよコンサートが始まる。
ステージで曲の進行とともに出番を待つフランキー。これまでのさまざまな思いがよぎる。いつしか曲を忘れ没頭し、はっと気が付いた時には、何と唯一の出番を椅子に座ったままやり過ごしてしまっていた。両手で顔を覆う妻。呆然としたままコンサートは終わる。皆が舞台を降りたあとも独り残るフランキー。帰るに帰れず客席に残っていた友人たちの前でシンバルを手にし、苦い悔恨の中で一発をぶちかます。…
この話、結末はどうだったのでしょうか? ぜひもう一度観てみたいドラマですが、どこかにアーカイブが保存されているのかどうか。フランキー堺はジャズドラマーとして鳴らした人ですから、打楽器奏者の役はお手のもの。
伊那フィルでは来月の定期公演で「新世界」を演奏します。たった一発の微妙なシンバルを鳴らすのは私です。ぜひ、お越しください。
------------------------------------------
伊那フィルハーモニー交響楽団 第36回定期演奏会
11月10日(日)14:00開演 長野県伊那文化会館
指揮:横山奏
・ファリャ バレエ組曲「三角帽子」
・ドボルザーク 交響曲第9番ホ短調「新世界より」
全席自由 入場料1000円(高校生以下無料)
------------------------------------------
(三角帽子はティンパニで私の出番がたくさんあり、この日の演奏会で一発しか叩かないわけではありません)
The End of Finale音楽ばなし
20240831
本欄の多くの読者には何のことやら、だと思います。音楽業界に激震が走っております。
--------------------------------
(毎日新聞)国内外の音楽家や音楽出版関係者の間で広く普及している楽譜作成ソフトウエア「Finale(フィナーレ)」の開発を終了すると、開発元の米国メーカー「MakeMusic」が26日、発表した。長らく楽譜出版業界の標準とされてきたソフトが35年の歴史に突然“終止線を引く”ことになり、関係者らは動揺を隠せない様子だ。
MakeMusic社は、現在ソフトがインストールされているデバイスではOSを変更しなければ引き続き動作するとしながら、今後アップデートはされず、2025年8月以降は新たに使用するための認証やサポートを受けられなくなるとしている。コンピューターの基本ソフトのOSの進化により「付加価値の提供が難しくなっている」ことが開発終了の理由だという。
--------------------------------
このソフトは簡単に言うと、楽譜を書くためのワープロみたいなものです。35年の歴史とありますが、長年にわたってプロアマ問わず世界中の音楽関係者に使われてきました。
作曲編曲をする人だけでなく、たとえば大手楽譜出版社の多くもFinaleを使って印刷譜を作ったりデータの管理をしていると聞きます。シェアがどのくらいか知りませんが、かなりの市場占有率であることは間違いないです。世界標準とさえ言われております。
多くの音楽関係者にとってこれが突然終わってしまうということは、Excelが明日から使えなくなる、ことをご想像いただければと思います。新しいものを作れなくなるだけでなく、世界中の人が過去に作った膨大なライブラリが使えなくなってしまいます。(もちろんPDFなどで保存しているでしょうが、修正ができなくなってしまうのは痛い)
私もしばしば楽譜を作る機会がありますが、幸いにもFinaleではなく、Sibeliusというソフトを使っています。Finaleの方が機能は優れている(あくまで両者比較の上での話)らしいですが、使いこなすのに覚えなくてはならないことがやたら多いと聞いたため。私ゃプロじゃないし、Sibeliusだってそれほど使いこなしているわけでもないですが。Finaleは頻繁にヴァージョンアップがあり面倒だとも聞きました。
しかし世界中の音楽文化を揺るがせかねないこんなことを、一企業の都合でホイホイできることに恐怖を覚えますね。これまで使ってた皆さん、どうするのでしょうか。引用の記事「終止線を引く」とはうまいこと言ったもんだ。
夏、松本の音楽祭音楽ばなし
20240812
我が国の音楽界での一大イベントとして名高き「セイジ・オザワ松本フェスティバル」。縁あってチケットをお譲りいただいて、何年振りかで出かけてきました。
92年に始まった音楽祭。近場での開催にもかかわらずチケットの入手が面倒だったりして、私はこれまでよほど興味深いプログラムの時しか行っておらず、4度目です。
今回の曲目は、新進女性指揮者沖澤のどか指揮によるメンデルスゾーン「真夏の夜の夢」抜粋、R・シュトラウス「ドン・ファン」「四つの最後の歌」というやや変則的なプログラム。何が変則かというと、通常だとメインに置かれる交響曲など規模の大きな曲がなく、歌曲でコンサートが締めくくられたことです。
特に印象的だったのは「ドン・ファン」。今回の3曲では最も編成が大きく、名人揃いと名高い弦楽器が分厚く鳴り渡るさまはまことに圧巻で、このオケならではの響きを堪能しました。管楽器のソロも良かったな。
「四つの最後の歌」は老境のシュトラウスが書いた珠玉の作品で、20世紀歌曲の中の最高傑作ともいわれます。南アフリカ出身のソプラノ、エルザ・ヴァン・デン・ヒーヴァーはこのしみじみとした歌を、時に情熱的に時に抑制的に歌い上げ、なかなか聴かせました。この方とっても背が高く、指揮者の沖澤さんは小柄で彼女の肩までくらいしかありません。
4曲目「夕映えの中で」は老夫婦がこれまで共に歩いてきた人生を振り返ります。遠からず人生を閉じるであろう諦念と共に、互いの愛情を穏やかに確かめ合う歌です。この歌を心から味わう心境にはまだ至っておりませんが、素晴らしい歌唱に少なからず心を動かされました。
アンコールはありませんでしたが(この曲のあとでアンコールという雰囲気にはなりますまい)皆がステージからはけた後、再び出演者全員が登場しカーテンコールを受けるという珍しい形でコンサートは終わりました。今年は小澤征爾の追悼の意味合いで関心を集めましたが、カリスマ亡きあとこの音楽祭がどうなっていくのか、注目だと思います。
夕鶴、苦労話など(2)音楽ばなし
20240706
オペラは歌がメインであって、歌をかき消してしまう打楽器の大音量は歓迎されません。たいていのオペラでは打楽器の出番はとても少ないのです。でも少ない音の一打一打に深い意味があり、大切です。
夕鶴も例外ではありません。今回、ティンパニの私とその他5種類の打楽器をすべて掛け持ちしたSさんと二人でやりましたが、ちょっと叩いては100小節、ちょっと叩いては200小節と膨大な休みです。以前やった出番だらけの「カルミナ・ブラーナ」とは大違い。
次の出番まで、休みの小節を数えることが大変。曲を覚えていれば全部を数えなくたっていいのですが、こう長いと紛らわしいところも多い。ふだん私たちが手掛ける曲は「ここで打楽器出番だぞ!」と誰もが思うところに音符があるものですが、前述のようにオペラは突然の場面転換も頻繁にあり、ただ予測するだけでは落ちてしまいます。
ちなみにオケ用語で「落ちる」とは、本来音を出すべきところで出られず、音楽に穴をあけてしまうことです。小節や拍子の数え間違い、思考の一瞬の空白など理由はありますが、100%本人の責任なので周りからは白い目で見られ文字通り落ち込みます。(あまり気にしないメンタルの強い人もたまにいますが)
さらにティンパニには途中で太鼓の音程を変える場所があります。他の楽器が演奏している音や調を耳で聴きながら合わせます。どこから音を取るのかはあらかじめ総譜を見て探し、楽譜に書き込んでおきます。演奏中に音替えをする時はどうしても(私の場合)一時的に楽譜のことがお留守になり、その間に拍子が変わったりするともう大変です。
主人公「つう」が、自らの命を懸けて最後の布を織り始めるところ。ハープのグリッサンドと小太鼓、大太鼓が機織りの音を模した音型を演奏します。つうの正体が鶴であると悪党たちにわかってしまい、「決して織っているところを見ない」と固く約束した与ひょうも逡巡の末、好奇心に負けてとうとう機織り部屋を覗いて見てしまいます。夕鶴のクライマックスです。
私は機織りの場面が始まるといつも、破局に向って止めることのできない時計がついに動き出したような思いがし、胸が締め付けられます。きわめて印象的なハープと打楽器の音型は、与ひょうが茫然自失し家を飛び出し、第二部(翌日の夕方)になっても延々と続けられます。その数、180回!
同じような音型を機械的に繰り返すのではなく、感情の高ぶりや弛緩に合わせて(というより、音楽をリードして)演奏する、とてもやりがいのある仕事です。プロのハーピストと共にしっかり布を織り続けたSさん、お疲れ様でした。
夕鶴、苦労話など(1)音楽ばなし
20240703
木下順二の戯曲に團伊玖磨が作曲したオペラ「夕鶴」。上演回数はこれまで国内外で800回以上、日本人によるオペラでは群を抜いた人気を誇る傑作です。私もこれまで実演に二度接し、2011年9月に小規模な公演を観た感想を本欄に書いてもいます。
中学生の頃、演劇クラブで夕鶴公演に加わった(裏方です)ことがあり、この戯曲には昔から馴染んでいます。人間の弱さ、お金への欲望のむなしさ、そのために失ったものへの惜別、分かり合えない価値観など、民話に題材を取ってはいますが現代の私たちにいくつもの問いを投げかけています。
演劇からオペラになって詩情あふれる音楽の素晴らしさが加わり、物語の魅力を倍増させました。このオペラに自分が参加することになるとは想像していませんでしたが、先日ついに伊那フィルで演奏してしまいました。
伊那文化会館主催の「市民オペラ」として、プロの指揮者、歌手、演出、スタッフたちにアマチュアのオケと児童合唱が加わった企画です。(大人の合唱パートはありません。そもそも原作に他の登場人物が存在しない)
長い曲、初練習の時、正味二時間半の練習なのに曲の半分くらいまでしか音を出せなかったことにまず驚きました。これは大変なことになるなあ、と。
オペラですから、まず歌があります。四角四面なテンポではもちろんなく、場面ごとに(瞬間ごとに)歌手たちは節回しで微妙なニュアンスを表現します。それを支えていくのがオケですが、経験から伊那フィルは曲をある程度つかんで体に入ってしまえば柔軟性を発揮できますが、それまでに結構期間が要るのですよねえ。
昨年末から練習が始まりましたが、予想にたがわず6月末の本番直前まで、ホントにこんな曲できるんだろうか、と思う日々でした。劇と一緒に音楽が進んでいくので、会話の中で驚いたり、突然凹んだり狂喜したりするのを音楽で裏打ちしていくのです。交響曲などではまず現れない、オペラ独特の表現。集中力が問われます。
それでも歌のソリスト(皆さん声量も表現も素晴らしい)と合わせの練習があってからオケも急成長しました。やはり具体的にイメージできると違います。本番前は木曜日から4日連続という伊那フィル史上初めてのハードスケジュールに、皆さんよくついてきたなあと思います。
子どもオーケストラと共に音楽ばなし
20240509
ゴールも近くなりましたが、ちょっと休憩してコンサートのご案内を。来週末、駒ヶ根で伊那フィルのコンサートを指揮します。
今回の目玉は駒ヶ根で活動する「エル・システマ駒ヶ根子どもオーケストラ」との共演です。私はこのオケとは関わりがあり、ピンチヒッターとして指揮したり打楽器で出演したりしたことは過去に書きました。
発足してもうすぐ7年になりますが、60人近い小中学生が目を輝かせて弦楽器を学んでいます。とくに最近めきめきと腕を上げ、市内のイベントなどにも積極的に出向いて演奏を披露しています。伊那フィルとは2019年、22年に続いて3回目の共演です。
4月に合同練習を持ちましたが、難しい曲にもかかわらず(個々の習熟度に合わせた楽譜を使いながら)頑張ってついてきています。伊那フィルにとっても弦楽器の人数が一挙に2倍以上になり、厚い響きを感じられた良い練習になりました。
駒ヶ根公演もこれで通算6回目になるでしょうか。ここ3年ほど駒ヶ根で行ってきたウィーン音楽特集やシネマコンサートなどのテーマは特に設定しておらず、オーケストラの響きを楽しんでいただけるようなポピュラーな曲目を集めております。
どなたもお忙しい時期ではありますが、どうかお気軽にお越しくだされば幸いです。お待ちしています。
--------------------------------
伊那フィルハーモニー交響楽団 初夏の駒ヶ根コンサート
5月19日(日) 午後2時開演 駒ヶ根市文化会館
共 演 エル・システマ駒ヶ根子どもオーケストラ
曲 目
ワーグナー:ニュルンベルクのマイスタージンガー前奏曲
ラフマニノフ:ヴォカリーズ
ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」第4楽章
子どもオーケストラ単独演奏ステージ
グレンジャー:デリー地方のアイルランド民謡(合同演奏)
エルガー:行進曲「威風堂々」第1番(合同演奏) ほか (順不同)
入場料 (たったの)500円 高校生以下無料
指 揮 春日俊也