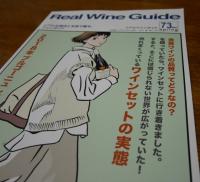文化は不要不急でない日々雑記
20210513
緊急事態宣言を受けてさまざまな施設がクローズを求められているのは、皆様ご存知の通りです。その中、国と東京都の間で都内にある美術館や博物館の開館をめぐってせめぎ合いが起きました。
----------------------------
(毎日新聞)新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が12日から延長されることを受け、文化庁は11日、国立文化施設の休業継続を決めた。当初は営業を再開する予定だったが、東京都からの申請に応じた形だ。
小池百合子知事は10日夜、床面積が1000平方メートルを超える博物館や美術館に休業要請を継続することに基づき、国の施設も従うよう文化庁に文書で求めていた。
これに対し、萩生田光一文部科学相は11日朝の閣議後記者会見で、「芸術は心を癒やしたり、勇気づけたりする効果もある。人数を絞っても開けていこうという姿勢を都に伝えてみようと思っている」と営業再開を模索する姿勢を示したが、11日に都などと協議し、休業継続を決めた。
----------------------------
このような静かな場所での感染リスクはとても低いことは、たやすく想像できますしエビデンスができています。それを踏まえて再開しようとした国に都がいちゃもんを付け、結局強引にねじ伏せた(国側がヘタレた)形です。
美術展を見た後でカフェに寄るのが人流を生むのでいけないというのなら、大相撲やプロ野球で5000人規模の観戦はなぜ許されるの? 理解できません。誰か教えてください。
私の身近なところで先日、ずっと前から計画してきたコンサート開催の是非について主催者会議があり、延期が決まりました。実行委員の一人として企画に参加してきた私としては、残念至極です。今この時期でなくては参加できない人が大勢出てしまうため、単純に一年後にやればいいじゃん、というわけにはいかないのです。
緊急事態宣言下ではともかく、対象外の地域では安全に注意を払って多くのコンサートが行われています。クラシックコンサートや演劇などは大声で声援など行いませんから、飛沫感染リスクは小さいことが様々な研究で立証されています。しかし残念ながらこの情報は多くの人々に共有されておらず、理解いただけないケースも少なくありません。(上記の会議に出席された方々が無理解だと言っているわけではなく、苦しい決定だったことはわかっております、念のため)
生きていくにあたって、衣食住に直接関連しない文化芸術活動は不要不急だと思う方は、もちろんいらっしゃるでしょう。でも人の営みとは、泣いたり笑ったりあったかい気持ちになったり、様々なものに触れて心を動かせることじゃないかと思います。コロナ禍においても、苦しむ人たちを支え勇気づけてくれています。さらにこうした活動を生業としている人たちがいることも、忘れないでほしいです。
つい最近文化庁長官に就任したばかりの作曲家都倉俊一氏が、「文化芸術に関わる全ての皆様へ」とメッセージを発しています。当事者・関係者に向けた文書ですが、関係ないと思われる方にもぜひ読んでみていただきたいと思います。
関連リンク: 都倉俊一文化庁長官のメッセージ
ぼったくり男爵日々雑記
20210511
IOC会長トーマス・バッハ氏のことですよ。散々な言われようです。米紙で、コロナでこんな状況の東京はもうオリンピックを返上したらどうか、との記事が書かれているそうです。代表的なワシントンポストの記事で、バッハ会長を「ぼったくり男爵」と呼んでおります。
「ぼったくり男爵」とは原語で何といっているかと思いましたが、Baron Von Ripper-off だそうです。Ripperは切り裂きジャックJack the Ripperに使われている単語です。私の辞書では切り裂くという意味は載っていますが、ぼったくるという意味までは出ていません。Ripper-offでぼったくるというスラングがあるのですね。
何がぼったくりか。言うまでもなく、IOCと開催地との不平等条約のことを指しています。収益の多くはIOCが持っていき、費用はまるまる開催地に押し付けられる。実施か中止かを決める権限は一方的にIOCにあり、開催地はその指示に従うしかない。さもなくば莫大な違約金を払うことになる。
それを承知で手を挙げたのだから仕方がないだろうとも言えますが、コロナという全世界を覆う大災害の発生なぞ想定されているはずもありませんから、出来ないものは出来ないと言うしかないでしょう、本当に出来ないのなら。
ワシントンポストの記事は、「(日本が開催を拒否したら)そのときIOCは何をするのだろうか。訴訟を起こすのだろうか。しかし、そのときはどの裁判所に訴えるのか。そもそもこれはどの裁判所の管轄なのか。パンデミックのストレスと苦しみにあえぐ国で五輪を断行しようとしているのだ。そんな訴訟を起こしたとき、IOCの評判はどうなるのだろうか。」と言っています。
まったくその通りだと思いますが、それはあくまで東京が「こんな状況でオリンピックなんかできん」とケツをまくったらの話であって、総理大臣も都知事も頑固に「できる」と言いはっているのだから、IOCが気を使って「そんな無理しないで、やめてもいいんだよ」なんて先に言ってくれるわけないですよ。
それはそれとして、本当に、五輪はできるのか。
関連リンク: ワシントン・ポスト記事 (クーリエ・ジャポン)
草枕とオフィーリア読んだり見たり
20210508
連載中の日経新聞の小説は、伊集院静の「ミチクサ先生」という夏目漱石を描いた作品です。肩の凝らぬ楽しい話ですが、漱石のロンドン留学中の記述に、ちょっと気になるエピソードがありました。
美術館を訪れた漱石が心を奪われた絵画。それがジョン・エヴァレット・ミレイの「オフィーリア」だというのです。「絵画というものは、これほどまでに文学作品の物語の根幹、叙情を一枚の絵で表現できるものなのか……。」と漱石は感銘し、「なんとも、風流な土座衛門だ」とつぶやきます。この絵は漱石にとって、後年の小説「草枕」の中で主人公が何度も思い浮かべるモチーフとなるほど、印象深かったのです。
草枕の冒頭「山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に掉させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」はどなたもご存知でしょうが、その先まで読んだ人はぐっと少なくなるでしょう。私も初めて読みましたよ。主人公の画家が絵画や詩をもとに「芸術とは何か」を一人考察する部分が長く、また何度も出てきて正直かなり読みにくい小説でした。
主人公は絵を描くため辺鄙な温泉地に逗留します。旅館には出戻りの、美しいけれど変わった女性、那美がいます。画家は那美に心惹かれますが、彼女に「自分の絵を描いて」と頼まれるも躊躇します。那美には芸術作品のモデルとして何かが足りないと感じるのです。しかし小説の最後に那美と出征する元夫との邂逅を偶々目撃したことで、何が足りなかったかを理解します。
ミレイの「オフィーリア」は何を隠そう、古今の名画の中でも私の最も好きな絵です。何年か前に東京で展覧会が開かれたときにはわざわざ観に行きました。これほどお気に入りなのに、草枕のエピソードを知らずにいたとはお恥ずかしいこと。
仰向けになって川に流されてゆく美少女。死に至りつつある自らの状況も理解できず、無邪気に歌を口ずさむ絶妙の表情です。水を含んで沈みゆくドレス、自ら摘んで手にしている花束とともに、川のほとりに咲く数々の小さく可憐な草花も、オフィーリアの儚い命を惜しんでいるかのよう。何と美しい作品世界であることか!これを風流な土座衛門とは、草枕主人公の台詞ですが、あまり風流でないですね。
裳裾は大きく広がって
しばらくは人魚のように川面に浮かびながら
古い歌をきれぎれに口ずさんでいました。
まるでわが身に迫る死を知らぬげに、あるいは
水のなかに生まれ、水のなかで育つもののように
だがそれもわずかなあいだ、身につけた服は
水をふくんで重くなり、あわれにもその
美しい歌声をもぎとって、川底の泥のなかへ
引きずりこんでいきました
(シェイクスピア「ハムレット」小田島雄志訳)
伊那ロータリーで卓話日々雑記
20210507
あっという間に過ぎていったゴールデンウィーク。いつもの年なら観光も飲食も大きな書き入れ時です。首都圏や大阪などが緊急事態宣言の真っ最中、雨にもたたられましたが、当地でも他県からの入り込みがそれなりにあったようです。死んだような街となった昨年のGWのことを思えば、天地の違い。
さて先月、伊那ロータリークラブ(RC)の例会を訪問して「卓話」をさせていただく機会に恵まれました。
卓話=テーブルスピーチ。RCではほぼ毎週、集まって昼食をとりながら例会を行い、その中で会員やゲストの卓話を聞く機会を持ちます。講演というほどのボリュームではなく、ちょっと長め(20~30分)のスピーチ、といった感じですかね。
この4月はRCで「母子と健康月間」にあたり、駒ヶ根で行っているネパールへの支援について話を聞きたいとして、私にお声がかかったというわけです。光栄なことですし、また他のクラブの例会をほとんど知らないので、喜んでお引き受けしました。行ってみると日頃から存じ上げている方がとても多く、アウェイ感がだいぶ減少しました。
駒ヶ根ではトカルパ村とポカラ市、二つの拠点でネパールでの国際協力活動をしています。山間地のトカルパでのことは私も支援NPOのメンバーとして現地も見ていますが、ネパール第二の都市ポカラでの活動については知らないことも多く、支援の中心になっているネパール交流市民の会、北原照美さんに事前にみっちりレクチャーを受けて準備していきました。
ポカラは山岳観光の拠点として駒ヶ根と環境が似ていることなどから、2001年に交流が始まりました。市長や病院長らが何度か現地を訪れる中で、母子保健の改善が急務ではないかということになりました。
初期には救急車や医療器材を寄付するなど物的支援を行いましたが、より現場に密着した支援をしようと「JICA草の根協力事業」制度を使い、駒ヶ根から専門家を派遣し現場の声を聞きながら健康指導をしたり、現地の保健スタッフを駒ヶ根に招いて専門的な研修をしてもらったりしています。
また赤ちゃんに毛糸の手編み帽子や吊るし飾りを継続的にプレゼントする活動には、中高生や高齢者グループが積極的に参加しており、駒ヶ根の人たちにも様々な気づきが生まれ、一方通行でない民間国際交流の果実を得ています。
伊那RC会員の皆さんにこのような話を駆け足でさせていただきました。話者が拙い故、どれだけお伝えできたか心もとないですが、私自身あらためてネパールと駒ヶ根の交流を整理するきっかけにもなり、ありがたいことでした。
通販セットの実態? 飲みもの、お酒
20210430
酒ネタその2。外出しにくいゴールデンウィーク、家呑みで通販のワインを購入される方もおいででしょう。私も自分でワインを売ってはいますが、あちこちで“○○受賞ワイン”のセット販売の広告を目にして、どんなものだか職業的興味を持っています。
昨年秋だったか、深夜TVのCMで「世界のスパークリングワイン10本セット」というのをやっていて、面白半分に購入してみたのです。1本あたり800円弱という値段でしたから、味に大して期待はしませんでしたが。失敗しても知れてるし。
届いたものはまあ予想通りの味で、特に個性的なものもなし。中に1本、ひどく美味しくないものがあって、私には本当に珍しいことですが飲みきれず流しに捨ててしまいました。もう一度この会社のセットを試そうとは、もちろん思っていません。
「リアルワインガイド」というワイン雑誌(季刊)があります。表紙が江口寿史のイラストで、「旨安大賞」として廉価ワインを評価したり、家庭でのワイン保存の実験などユニークな編集方針で、面白いマニアックな雑誌です。褒めるだけでなく結構辛口のコメントもあったりします。
最新号で「売れまくっているワインセットの実態」なる特集を見て興味を惹かれ、久しぶりに買って読んでみました。入門者を主ターゲットにしている(と思われる)6本~12本入りの通販商品、11セットが俎上に上がっています。
高評価のセットもある一方で、とてつもなく低い評価のものもいくつか。というか、半分くらいはⅭ評価です。中には私の買ったセットもありましたよ。総合評価Ⅽ-、品質Ⅽ-、バリエーション評価不能、コンディションⅭ-。明らかに飲めないほど劣化しているものが何本も入っているとしています。
セットの内容1本毎の評価が書かれていますが、通常は「飲み頃の年」を示す欄には「飲めなくはない」「飲まない方がいい」「飲んではいけない」との凄まじい評価が。100点満点で0点(評価不能)なんてのもありましたよ。この雑誌がこれほどの低評価をつけるのを見たことがありません。私が飲めずに捨てたのも、忘れちゃいましたが、これでしたかね。
このセットが、通販サイトワイン部門のトップ10に入っているんですと。知らずに買って、ワインってこんなもんか、もういいやと思ってしまう入門者がいたら、ひどい話です。しかしよくまあ、こんな辛辣なことを相手の実名入りで書くものですよ。編集長氏、さぞ敵が多いでしょうねえ。でもこういう人の存在も必要なのだと思いますが。
ジョッキ缶ビール 飲みもの、お酒
20210428
禁酒令の記事を怒りをこめて書いたので、引き続いてお酒ネタを。
--------------------------
(食品産業新聞)アサヒビールは4月21日、「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」(340ml/オープン価格)を一時休売することを発表した。
「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」は、開栓するときめ細かい泡が自然に発生し、飲食店の“生ジョッキ”で飲むのような味わいが楽しめるビール。4月20日に全業態での販売をスタートしていた商品だ。
アサヒビールによると、「今後の販売数量見込みに対し商品供給が追い付かない」ため、「計画していた4月製造分を出荷次第、一時休売」せざるをえなくなったという。再発売は6月中旬以降に、数量限定で行う予定だ。
--------------------------
発売時、予想外に売れて品不足になりすぐ休売になってしまうヒット商品?が時々ありますが、本品もその一つ。社内でこのビールが話題になった際、ビール好きの社員がたまたま自分で飲もうと1ケース仕入れたものがありまして、可哀想にみんなに提供する羽目になってしまいました(もちろん有償ですが)。私も2本もらって家で吞んでみましたよ。
どんなふうに泡が出るのかと興味津々でしたが、ちょっと冷やしすぎたのか、蓋をパカッと開けても泡が表面をうっすら覆うだけ。でも缶を両手で温めるように持つと、あら不思議じわじわと泡が湧いてきます。そのままガブガブと呑みます。
従来の缶ビール容器の欠点は、開口部が小さく、缶から直接勢いよく呑めないところです。泡も立たないので炭酸が抜けず、ビールの味わいを十分楽しめない。アサヒのホームページによれば「開栓したときに噴きこぼれてしまうのを防ぐため、缶ビールはそもそも“泡を出さない”ように作られている商品」なのだそうです。
なので家で呑むときは必ずグラスに注いで泡を立てて飲んでいますが、アウトドアなどではそれができないこともありますね。本品は上手にそれをクリアしています。日頃スーパードライ派ではない私ですが、なかなか美味しく感じますよ。
気を付けるべきは、勢いよく呑むので必然的に「飲みすぎる」リスクが高いことですかね。340㎖缶2本飲めば「小さめの大ジョッキ1杯」に相当する様ですので、ちょっとご用心。
次に市場に出るのは6月だそうですので、楽しみに待つとしますか。
禁酒令しごと
20210426
三度目の緊急事態宣言。とにかく人は外に出るな、閉じこもれということで、なりふり構わぬお触れが出されています。百貨店も、本屋も、映画館も、野球場も。(4/28追記、本屋は良いが古書店はダメ、である由)
百貨店の休業に対して支払われる協力金が一日20万円というので、毎日数億の売上を持つお店にそれは何だ、ふざけんなとの声が。当社も似たような状況をつい最近経験しています。規模を考えてくれない施策に文句を言いたいのは、まったく同感です。
本屋が何でいかんのよと思いますが、施設そのものが感染拡大元になるのでなく、施設に行った帰りに人の集まりができることが怖いんだって。こういうのを言いがかりというのでは?ユニクロはいいのですか、店内はずいぶん密になるんじゃないかと思いますよ。
私の業界に切実にかかわるのは、もちろん「飲食店等における酒類提供の禁止」です。これまで午後7時までは認められていましたが、時間帯を問わず禁止、守らなければ罰金と。感染防止のため設備を整え時短に応じ、慣れないテイクアウトに対応してきた真面目なお店は、心が折れることでしょう。
私の言いたいことをすべて代弁してくれている記事がありますので、リンクを貼らせていただきます。筆者の東龍氏は飲食業の繁栄を願ってこれまで様々な視点から問題提起をしています。今回の措置を受けて必ず記事を書いてくれると思っていました。ぜひお読みください!
お酒と飲食業は切り離せない密接な関係にあります。居酒屋やバーなど、酒が売上の多くを占める業態はもちろん、フレンチ・イタリアンなど酒と一緒に楽しむことを前提として長いこと積み重ねられてきた文化もあります。ご自分は飲酒をされないという方にも、その価値はぜひご理解いただきたいです。
飲食業は政治的に立場の弱い業界です。全国で359万人(総務省の「労働力統計」2021.2)、全就業者の5.4%が働いているのですよ。なのに言いたいことを国会で発言してくれる議員もいません。資本力のあるチェーンもありますが、圧倒的多数は中小零細の個人経営のお店です。大きな声で文句を言えないのをいいことに、営業活動に手枷足枷をはめコロナの尻拭いを1年以上も一方的に押し付けてきて、その結果ろくな成果も出すことなく、いよいよとどめを刺そうというわけですか。
どの業種も大変だと言われます。そうでしょう。飲食業も、本当に、大変なんです。
不昧公の銘菓食べもの
20210419
松江は京都や金沢と並んで全国屈指の和菓子どころとして知られています。時間があればそれぞれの菓子屋さんの本店を訪れたいところですが、松江駅に隣接した一畑百貨店でその多くを買い求めることができます。
松江のお菓子文化は松平不昧公(ふまいこう)時代に礎が築かれたと言われます。松平治郷(1751~1818)は16歳にして家督を継ぎ、松江藩の七代目藩主となりました。破綻寸前だった松江藩の財政を、産業振興や治水林産などに注力し立て直した名君と言われます(諸説あり)。一方で治郷は若い頃から茶の湯を熱心に勉強し茶道具を収集し、隠居してからは「不昧」を号として文化人としてその名を高めました。
茶の湯には菓子がつきもの。不昧公が茶事に用いた菓子は大変多く、その流れを引いて歴史ある菓子店が今でも栄えているのです。
畑主税著「ニッポン全国和菓子の食べある記」(誠文堂新光社)を参考に、代表的なものを購入してきました。写真はその中のいくつか、右上より時計回りに、若草(彩雲堂)、柚餅子(福田屋)、菜種の里(三英堂)、生姜糖(來間屋生姜糖本舗)です。
若草は鮮やかな緑色の落雁粉で求肥をくるんだもの。柚餅子は柚子の香り高いふわふわの求肥餅。菜種の里は美しい黄色の落雁で素朴な味。生姜糖は地場産の出西生姜の絞り汁と砂糖を溶かし固めたもの。
若草と菜種の里はそれぞれ「松江三大銘菓」に数えられ(もう一つは「山川」という落雁の菓子)複数のお菓子屋さんが製造販売しています。どちらも彩りが美しく、お茶と一緒にいただくとシンプルながらなかなか味わい深いものです。
柚餅子は全国各地に似たものがありますが、福田屋のものはふわふわに柔らかい食感が楽しく、柚子の香りも高く上質のものだと思いました。
空港で買った生姜糖が意外な掘り出し物。これは松江でなく出雲のお菓子です。キャラメルの包み紙みたいなものに一個ずつ包まれていて、普通の飴と違い口に入れるとカリッサクッと脆く崩れます。生姜の辛さと砂糖の甘さのバランスが絶妙で、ベタベタせずとてもスッキリしたお菓子で、極めて優れていると思います。
菓子は、文化。歴史ある街に伝統の味を伝える誇りと技を思います。
フォークの背にライス食べもの
20210414
フォークの背にライスを載せて食べる。いったい誰が始めた「マナー」なのでしょう。今ではむしろ間違いだと言われるこの風習です。もともと西洋で食事に日本のようなライスが出てくることはないし、存在しない料理を食べるのに正しいマナーがあるはずもありません。
先日TV「バカリズムの大人のたしなみズム」を観ていましたら、驚くべきカミングアウトが。この食べ方は東京銀座の老舗洋食店「煉瓦亭」が始めたというのです。そんな話、初めて聞きましたぞ。検索してもまったくヒットしません。
番組によると、洋食で皿盛りのライスを出したのは煉瓦亭初代の木田元次郎氏が最初である。それまで西洋料理にはもっぱらパンであったが、ご飯も食べたいという客の要望に応えてライスを皿に盛って提供した。その際にフォークの背にライスを載せる作法を「勝手に思いついて」(四代目店主、木田浩一朗氏の話)客に教えたらしい。へえ!
私がフォークの背にライスを載せる人を初めて目撃したのは10歳くらいの頃。家の近所のレストランというか食堂で、背広を着たサラリーマン風の人が食事をしていました。この人は実になめらかな、手慣れた所作でフォークにライスを載せて食べていて、今でも何となく目に浮かびます。よく覚えているとお思いでしょうが、そのくらい印象的でした。
その後、たま~にナイフフォークを使うときにチャレンジしてみましたが、これは難しい!まずフォークの背に載せるライスの適量を見極めるのが難しく、大抵は多すぎますね。そしてもちろん、ポロポロと落っことしてしまいます。何でこんな変なことするんだろう、と子供心に思いました。
それでも何年もたてば、そう苦労しなくてもできるようになります。大人になって、どうやらこれは根拠のない「日本しぐさ」であると知りました。が、食事中基本のポジションが下を向いているフォークを上向きにわざわざ持ち替えることが私には面倒くさく、背に載せる方がむしろラクだと思うようになりました。(さすがに豆とかコーンは無理)
今では…そんなに意識しませんね。持ち替えたり、持ち替えなかったり。特にこうしようと決めてはおりません。どっちでもいいです。
漫画は、以前取り上げたこともある「目玉焼きの黄身、いつつぶす?」おおひなたごう著、からです。
進撃の巨人 完結(2)読んだり見たり
20210412
このコミックの面白さを、ネタバレなしでどうお伝えしたらよいのでしょう。私がなぜハマっているのか、ですよね。
初めは「未知の化け物と戦うアクション漫画」として読み始めました。異形の巨人たち、情け容赦ない殺戮。それと戦う人間の覚悟、立体機動装置の爽快さ、カッコよさ。しかし、いくら戦ってもまったく歯が立たず、人間は巨人を駆逐できない。
そのうちに、さまざまな「謎」に気づきます。人間は壁の外のことをまったく知りません。海を見たこともないどころか、ほとんどの人は海の存在さえ知らないのです。壁の外に別の世界があることも想像しません。(壁内にはそうは言っても、それなりの面積があります。きっと長野県よりは広い)
人々は「調査兵団」を組織し、壁の外がどうなっているかを調べようとしますが、その都度巨人たちと遭遇し、おびただしい犠牲を払います。1回の遠征で生還率は半分くらい?こんな無茶な組織に志願する人がいるのかと思ってしまう。ほとんどの人々が壁の中の生活に安住しているのに対し、調査兵団は壁内に閉じ込められている抑圧に気づき、自由を求める人たちなのです。外の世界を知りたいという熱い思いを抑えきれません。
主人公たちもその輪に加わります。同期の第104期訓練兵団の仲間(少年時代)が最終回の表紙を飾っています。途中で斃れるもの、裏切り、いろいろですが、同期の友情はこの長編作品を貫く一つのベースになっています。
23巻から舞台が大きく変わり、物語が飛躍的に広がりました。こんな大風呂敷、どうやって話をたたむのと思いましたが、きちんと話をまとめて着地しようとしています。それまでの謎は次々に解明されていき(「事態」が解決されているわけではない)物語の初期からこれほどの構想を持って作られてきたことに感嘆します。
多くの登場人物、いずれも魅力的です。人類最強と呼ばれるリヴァイ兵長は、クールな性格と戦場での頼もしさで主人公エレンを抑えて読者の一番人気だそうです。エレン、親友のミカサ、アルミンは物語が進むにつれ迷走しており(未読の方のため、こう書くしかない)解決が待たれます。って、雑誌派の人にとってはもう解決しているんですよね。
私は分隊長(のちに兵団長)ハンジのファンですよ。巨人は憎むべき存在ですが、ハンジは研究対象としての巨人に、科学者として強く惹かれています。33巻のハンジの台詞「…やっぱり巨人って 素晴らしいな」はその人柄を思わせる最高の言葉です。14巻「何言ってんの?調査兵団は未だ負けたことしかないんだよ?」も忘れ難いですね。
ああ、早く最終巻を読みたい。繰り返します、私に結末を教えたりほのめかしたりしてはいけません。