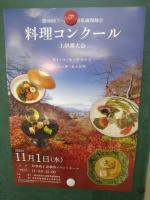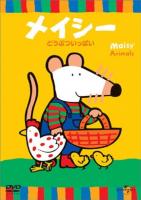じゃこ天騒動食べもの
20231117
殺伐とした舌禍事件が多い中、大人の対応というのはこういうものかと思わせる出来事となりました。。
元はといえば先月の講演で、秋田県の佐竹知事が四国を訪問したことを振り返って「じゃこ天は貧乏くさい」と発言したことです。周囲から批判を浴びてすぐに謝罪しましたが、中村・愛媛県知事が「揚げたてのじゃこ天は格別。きりたんぽ鍋に入れると、もっとおいしいかな」と切り返し、互いの距離がむしろ狭まったというのです。
この15日、秋田県と四国4県が有楽町で合同物産展を開き、各県の特産品を詰め合わせた「なかよしセット」3500円を販売し、仲直りと交流をPRしたとのこと。中身はじゃこ天のほか、きりたんぽや徳島ラーメンなどだったそうで、あっという間に売り切れた由。
佐竹知事は前から放言癖があり物議をかもす場面が時々あったそうですが、最近の熊被害にあたっては銃による駆除を後押し。理不尽なクレーム電話はすぐに切ると言明して、むしろ好感を持って受け入れられました。
じゃこ天発言では変な意地を張らずにすぐ撤回し(お国自慢をけなすのは怖いですぞ)また中村知事の絶妙な助け舟のおかげで災い転じて福とできたことは、大変良かったですね。両県の友情に乾杯ってところです。
私は昨年6月、愛媛宇和島を訪れたときにじゃこ天を食しており、食べた感想も一言だけ当時の本欄に記しております。「これはまあ、見た通りの味ですね」 そう、いわゆるサツマアゲの味で、特別感はなかったな。貧乏くさいとまでは思いませんでしたけど。
こうした食べ物は全国いろんな場所で、それぞれ特産の魚介を原料に作られていますね。できたてのものは、どれも美味しいですよ。じゃこ天は「ほたるじゃこ(別名ハランボ)」という魚で作るそうです。いま検索したら、高級魚ノドグロの仲間だというではありませんか。何となくチリメンジャコが原料だと思い込んでいました。失礼しました。
ガチャガチャ日々雑記
20231114
世の中に右肩上がりで流行しているもの。ガチャガチャこと、カプセルトイの自販機。どこにでもありますよね。つい最近、ご近所に数百台の自販機を揃えた売り場がオープンしました。社員から教わって、日頃は立寄ることのほとんどないガチャ売り場に行ってみました。
ベルシャイン駒ヶ根店2階の一角に「ガチャガチャの森」なるコーナーがあって、まあ確かに森だよな、700台近くのおびただしいガチャガチャが並べられております。
だいたいは300円か400円。よくもこれだけの種類があるものだと感心します。面白いのは、私どもにも日頃から馴染みのある食品メーカーさんの玩具が何十台もあったこと。商品のミニチュアですね。手に取って見たわけではないのでどの位の再現度なのかわかりませんが、これいいなと思うようなものがいくつもありました。
リンク先の記事でも、特に女性たちにリアルなミニチュア食品が好評みたいです。食品サンプルが外国人の土産として大人気ですが、共通するものがありますね。メーカーさん、ノベルティ品としていただけないでしょうかw。
主たる顧客であろう小中高生たちが、どのくらいの金額を使っているのか興味深いです。これだけの種類があれば、お小遣いがいくらあっても足りないでしょう。スマホゲームに課金するよりは親だったら安心できるお金の使い方だと思いますが…。店内には「10000円札両替機」が鎮座していて、何だかオソロシイ。
4年前、岐阜羽島で遭遇したガチャガチャの面白い使い方。新幹線に乗るのにずいぶん探してやっと見つけた無人駐車場。どこにもある自動支払機がなくて、ガチャ自販機が1台置いてある。500円(でしたっけ?)を払ってカプセルを取り出すと、中に1日分の駐車券が入っているのです。これをダッシュボードの上に置いといてね、というわけ。
これは考えましたね。ガチャ自販機の設置費用なんて、駐車券を発行し料金を受払する機械に比べたらタダみたいなものでしょう。1日1回管理人がナンバーをチェックし、日数オーバーした車には何らかの対応をすればいい。たいへん感心しました。他にも賢い使い方があるかもしれません。
スパークリングの栓を抜く 飲みもの、お酒
20231109
ワインの栓を抜く。何だかワクワクする瞬間です。どんな香りか、味か。ラベルから想像はついても、実際のところは抜いてみないとわかりませんからね。
自宅ではもっぱらソムリエナイフを使いますが、スパークリングワインにはソムリエナイフは使えません。特にそれ用の道具はないのです。どなたもやるように、タオルをコルクに巻いてねじるように回して開けます。ここで大事なのは、コルクではなく瓶の方を回すこと。その方が少しの力で回せます。
しかしたま~に、ひどく栓が固く、手が滑るばかりでうまく回せないことがあります。何かうまい方法ないかなあとかねがね思っていましたら、ある店(どこだか忘れてしまったが、スナックみたいな店)で見たことのない簡単そうな器具を使っているのに遭遇しました。
これは面白いと思い、その後通販サイトをのぞいたり、デパートの酒売場に行ったときなど「こんなのありませんか?」と何軒か聞いてみましたが、ないんですね。それどころかワインに精通しているはずの店員さんも、そうした器具の存在を知らないのです。
半年ほど気長に探して、先日ようやく通販サイトで見つけました。「シャンパンキー」という名前で検索すると出てきますが、イタリアのGHIDINIというメーカーのものです。写真のようにレバーをぎゅっと掴んでコルクに歯を食い込ませ(文字通り『歯止め』にして)ひねって開けます。おそらく本来は、大規模な宴会で次々に何十本も抜くときに使うものでしょう。
早速購入して試してみました。以前見たものはもっと簡単なものだったような。写真から想像するよりずっしりと重くゴッツく、まあ確実に抜けます。まだ1本しか抜いてないので、期待したほどスムーズではなかったですが…
勢いよくスパークリングの栓を抜くと「ポン!」と大きな音がします。派手な音を立てるのは実はあまり品が良くないとされ、私も家で抜くときには隙間から少しずつ空気を抜きつつ「パスッ」くらいの音で開栓するのを小さな楽しみにしているのです。初めてシャンパンキーを使ったらとんでもない大きな音がしてギョッとしました。これで静かに抜くのは、もっと何本も抜いて(飲んで)練習しないと。
必聴、少年ピアニスト音楽ばなし
20231105
伊那フィルのコンサートまであと一週間となりました。ご案内です。
今回の目玉は、慶応義塾大学在学中のピアニスト、八木大輔さん(19)がラフマニノフの協奏曲を弾くことです。八木さんは13歳でポッツォーリ国際ピアノコンクールに入賞したのを皮切りに、数々の国際コンクールで史上最年少の優勝や入賞をさらっている俊英です。
昨年5月、伊那でソロコンサートを行い絶賛を受けたことがきっかけで、伊那フィルとの協奏曲共演に至りました。私は残念ながらそのコンサートを聴いていません。だってあの時は、当日が伊那フィルの駒ヶ根公演と重なってしまったんだもの。今回取り上げるラフマニノフの協奏曲第3番。共演にあたり八木さんから提示された候補曲の一つだったのですが、彼にとってこの曲は初挑戦だとのこと。
一般に有名なのは第2番でフィギュアスケートにも定番として使われますが、第3番は音楽的により高い評価を受けている名作です。ピアニストに極めて難しい技巧が求められている超難曲として知られていて、真っ黒な(音符がぎっしり多い)楽譜、鍵盤の上を手が縦横無尽に飛び回る様が圧巻です。
それでありながらラフマニノフ特有のロマンティックな粘っこく甘いメロディーもしっかり聴かせています。例によってw私はこの名曲にこれまであまり馴染んでこなかったのですが、練習が始まって曲に深入りしていくにつれどんどんハマっていき、大好きになりました。
協奏曲をオケだけで練習するのは、メロディー不在ゆえイメージを掴むのがなかなか難しい。先月の顔合わせでこの曲の全貌が私たちにもようやく明らかになって、聴き惚れて自分の出番に出そこなったメンバーが続出しました。気を取り直して本番までにはソロの足を引っ張らないように頑張りましょうね、みんな。
ぜひお出掛け下さい。もう一曲、リムスキー=コルサコフ「シェエラザード」も演奏します。絶妙なオーケストラの響きでアラビアンナイトの世界を描き出す名曲で、どなたにも楽しんでいただけると思います。こちらは打楽器も大活躍しますよ。
------------------------------------
伊那フィルハーモニー交響楽団 第35回定期演奏会
11月12日(日)14:00開演 長野県伊那文化会館大ホール
曲 目
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番
リムスキー=コルサコフ 交響組曲「シェエラザード」
横山 奏(指揮) 八木大輔(ピアノ)
入場料 一般1000円、高校生以下無料
関連リンク: 八木大輔オフィシャルサイト
長野県料理コンクールしごと
20231104
長野県調理師会主催の「料理コンクール」という催しが、県下各地持ち回りで開催されています。以前駒ヶ根市で開催されたこともあり、本欄でも取り上げました(2010.10.6)。今年は地元伊那市で開催ということで、あまり時間がなかったのですが見に行きました。
日本料理(前菜、焼き物、煮物焚合せ)、西洋料理、中華、デザートの各部門に分かれ、参加者はあらかじめ作ったものを持ち寄ります。TVの料理番組みたいにその場で作ったできたてを食べて審査するようなことができればさぞ楽しいでしょうが、莫大な費用と手間がかかると思われます。
必然的に審査は「見た目」でせざるを得ないので、味を評価することはありません。やむを得ないですが料理のコンクールとしてはちょっと残念。一皿の中にすべてを盛り込むこと、信州産の食材や調味料を使うこと、そして食材原価を基準以下に収めることも条件になっているようです。
出品された料理を順繰りに見ていきます。入賞した作品には出品者のお名前と店名、審査員の講評が記され、選外になったものは番号のみが表示されます。全県からの参加ですが、当社お得意様の名前もちらほらとありました。
素人の私には、どこがポイントでこの皿が高評価なのか減点されたのかはあまりわかりません。一皿での表現なので、必然的にかなりたくさんの要素が盛り込まれることになります。それがごちゃごちゃと散漫になってしまうのか、スッキリと仕上げらているのか。あるいはお皿の上に集中できる焦点を作ってダイナミックに見せているのか、などが評価されているのだと思います。
時間を区切って、専門の方に解説付き観覧ミニツァーをやってくれたら嬉しいです。一般のお客さんにはきっと喜ばれるのでは。有料でもいいですよ。
私がもっとも良いと思ったのは、中華部門で最高賞「長野県知事賞」に輝いた作品。この夏に伊那市から箕輪町に移転した「ラーメンレストラン ハヤシ」の荒井秀城さんのもの(写真下)。鮎の動きを生きいきと立体的に表現して素晴らしいと思いました。もちろん当社お得意様で、店名の通りラーメンと、なぜかハヤシライスも売りにしている繁盛店です。おめでとうございました。
おにぎりブーム食べもの
20231029
おにぎりを食べるのに何時間も並ぶなんて。ちょっと信じられないですよねえ。空前のおにぎりブームだそうです。
火をつけたのは東京大塚の「ぼんご」というお店。ずいぶん前から名声は聞いています。かつて「愛の貧乏脱出大作戦」という番組がありました。過去の失敗で人生の崖っぷちにいる人を、厳しい修業で一人前にさせる企画に登場。女性店主がそれは厳しく指導していて印象的でした。
もう20年以上前の放送でしたが、この当時から人気の行列店だったようです。その理由はもちろん味。おにぎりなんてと思いがちですが、いいお米をふわっと柔らかく握った、なかなか真似のできないおにぎりだそうです。
そして50種類以上にのぼる具のバリエーション。しゃけ、たらこ、おかかなど定番品はもちろん、ペペロンチーノとか鶏唐揚マヨネーズとか。一番人気は「卵黄の醤油漬け」なんですって。仕込みには大変な手間をかけているようです。
ちょっと前にはdancyuでこの店の特集をやったり、情熱大陸で店主の右近由美子さんを取り上げたりと、時代の寵児的な勢いです。私もかねがね行ってみたいなと思っていましたが、いくら美味しいおにぎりでも何時間も行列するというのはさすがに無理、人生にはもっと大事なことがあるぜよ。
そのほかにも、27歳東大院卒の女性店長が率いるニューウェイブのおにぎり店「TARO TOKYO ONIGIRI」は多い日は2000個を売り上げるといい、ベンチャー企業として海外を含め100店舗を目指すとしています。
私もコンビニで昼食を買うときには、最近はお腹のことなど考えて?おにぎりが多いですね。珍しいアイテムを試すこともありますが、食べてみるとピンとこないことが続いたため、定番品に落ち着きました。
こうしてみると、かき氷のブームと共通点を感じます。伝統的に慣れ親しまれた題材、基本のおいしさ(ごはんと氷)にとにかくこだわり、味付け(具と蜜)のバリエーションで選ぶ楽しさを提供する。少し前に全国を席巻した唐揚げブームはあっという間に終わりましたが、おにぎりやかき氷はまだまだ人気を集めるような気がします。
(おにぎりとかき氷の共通点は私が自分で考えたのですが、検索したらTV東京の番組で既にやっていたみたいですね)
名刺を忘れたらしごと
20231027
先週はグランドフェア、今週は東京へ二度出張があったりで、本欄の更新も途切れておりました。訪問くださった方、申し訳ありません。これからまた更新していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さてそんな中での失敗の話。出張先で名刺を持っていないことに気づいたら?
これは困りますよね。今回は名刺入れを用意し中身も確認した上で、しっかり机の上に置き忘れて出てきてしまったのです。電車で東京へ向かう途中、気づきました。
今どきのことです、田舎ならともかく、東京でなら何とかなるわいと思ってスマホで検索してみました。最初はキンコーズみたいなビジネスコンビニでササっとやってくれるだろうと思ったのですが、調べるとその場で即時に作ってくれるとまではいかない。3時間くらいはかかるらしいです。
次。スマホアプリで名刺データを入力し、一般のコンビニでプリントアウトするという手があるらしい。コンビニなんてどこにでもありますから、これは便利。
ところがこの方法は、プリンタから出てきた紙を自分で裁断しなくてはならないのです。これは近くに自分のオフィスがあることを前提としなくては難しい。調べたサイトには「コンビニでカッターと定規を買って…」なんて書いてある。出張先でこれは困難であります。私ゃ不器用だし。
当初思い描いた「注文、即手渡し」という名刺ショップは検索のだいぶ下の方で見つかりました。池袋西口から徒歩数分のプリントメイトというお店。15分で完成とあります。
ここはデータを自分の手で入力し、レイアウトなどを調整して用紙を選び、たちまちのうちに名刺を作ってくれました。入店からきっかり15分、看板に偽りありません。料金はさすがに特急のお代、20枚2,010円でした。1枚100エン、なかなか高級な名刺です。(印刷は10枚単位、もちろん枚数や使う色の数などで価格は変わります)
予想した必要枚数はドンピシャで、その日のうちにほぼ使い切りました。まったくありがたいことでした。こんな店、オフィス街ならもう少しあちこちにあってもいいのにね。私のようなウッカリさんは、世の中にあまりいらっしゃらないのかな。
下の画像は子供が小さい頃よく見ていたTVアニメです。私が支度するときに「メイシー、メイシー、どこにある?」と主題歌に合わせて歌ったら(妻に)とても受けました。今でも習慣で、名刺入れを探すときにはついつい口ずさみます。
赤そばの里日々雑記
20231016
秋の里を彩る真っ白いそばの花。この辺りでは休耕田でそばを栽培している田んぼが数多く、一面に咲く可憐なそばの花は「かすみ草」を思わせるような美しさです。
最近では白い花だけでなく、赤いそばの花も時折見かけるようになりました。赤そばを集めて咲かせているそば畑もあるとは聞いていましたが、これまで見る機会がなかったのです。新聞に載っていたみごとな赤そば畑の写真を見て、行ってみたくなりました。
上伊那郡箕輪町上古田。里から西の山へ向かって田んぼの中を走り、駐車場に車を停めて林の中を数百メートル歩くと、突然目の前に広がる一面のピンクの絨毯。陳腐な表現ではありますが、まさにそんな感じなのです。視界の全部がピンクに染まっています。林の中にぽっかりと別世界が降ってきたような。東京ドームほどの広さだそうですが、それよりもっと広く感じます。
これは、ちょっと驚きましたね。人も結構大勢出ていて、何人かの知人にもお会いしました。皆さん新聞を見てきたのかな。
赤そばはヒマラヤの標高3800メートルの所から、信州大学の著名なそば博士、氏原教授が持ち帰ったものです。宮田村でスチール家具を製造するタカノ株式会社と共同で品種改良し「高嶺ルビー」と名付けられました。山間の遊休地を利用してこの「赤そばの里」を開発したのだそうです。
花は赤いですが、出来上がる蕎麦が赤っぽいわけではありません。現地の立て看板によれば、赤そばは観賞用に育てられているもので、そばの実の収穫量は普通のそばの1/3くらいなのだとか。
みごとな眺望に感心しました。今シーズンはこれでおしまいだと思いますが、来年以降機会がありましたら、ぜひ。
関連リンク: 信州伊那高原赤そばの里(箕輪町ホームページ)
藤井8冠とライバル日々雑記
20231013
ここまで来ればあまり驚きもないですよね。将棋の若き天才が、国内の主要タイトルを独占することになりました。
一昨日行われた王座戦5番勝負の第4局。永瀬拓矢王座との戦いぶりは壮絶であったらしく(悲しいかな指し手を見てもわからない)あちこちで取り上げられています。
途中まで永瀬王座がリードし、AI評価は99%永瀬勝利の局面。そこで永瀬が致命的な失着の一手「5三馬」を指してしまい、一気に評価が逆転した由。きっと指した瞬間に気が付いたことでしょう、天を仰ぎ頭をかきむしり、合掌して祈るような仕草を見せる永瀬を見て、将棋はやっぱり生身の人間と人間のぶつかり合いだなと思います。今回の主役は、前人未踏の8冠を達成した藤井よりもむしろ、永瀬ではないかという気さえします。
今日の日経に藤井の師匠、杉本八段の談話だか寄稿が載っています。藤井と永瀬は普段からとても仲の良い長年の研究仲間で、しばしば独自に対局しているそうです。
【さすがにしばらく休止していたが、王座戦が終わった今、二人の研究会はきっと再開されるのだろう。そして今までと同じように盤上に集中し、感想戦では笑顔を見せるのだろう。それを見るのが楽しみでもある。】
年齢は永瀬が10歳も上ですが、こうした関係、羨ましいですね。永瀬も次回は藤井に雪辱する気満々でしょう。お互いに高め合うライバルの姿を見ていくのが、私も楽しみになりました。
それにしても、藤井一強がいつまでも続くのは、野次馬としては興をそがれます。他の棋士たちはもちろん、対藤井作戦の研究に余念がないことでしょう。誰がどこで藤井を倒すのか、興味深いですね。
虐殺の応酬日々雑記
20231011
まったく気の滅入る事態です。ハマスによるイスラエル襲撃、イスラエルの反撃、犠牲になる民間人。
私ゃこの地域の争いの歴史について、平均的な日本人の知識以上のものは持ち合わせていません。どう解決したらいいか、もちろん分からないしご立派なことは言えないのですが、もういい加減にしろよと言いたくなります。
中東地域の地政学の問題に始まり、米・中・ロシア・EU・産油国が石油資源やら武器輸出やらの思惑からどっちかに肩入れし、あるいは傍観を決め込む。争いの柱には宗教が。ここまで入り組んでしまうとこんがらかった糸をほどくことも出来なくなってしまいます。石油輸入国日本は、一体どう動けばいいのか。
ただでさえウクライナ戦争で頭が一杯のところにこんな問題を作り出した(仕掛けたのはハマスですが、背景には当然イスラエルの静かな攻勢がある)ことを恨めしく思う人も山ほどいるでしょう。我々も他人事ではありません。今後の情勢によっては台湾問題にまで飛び火しかねないですよ。第三次世界大戦の不安が冗談では済まなくなったらどうします?
日本メディアの扱いが意外なほど小さくて驚きます。ジャニーズの話ばっかりしている場合じゃないでしょう。
犠牲者を悼み、事態が収束に向かうことを願うしかありません。
関連リンク: ハマスとは何者か 今イスラエルを攻撃した理由は(BBC)