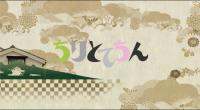バナメイ海老 (1)しごと
20131124
話題の食材!持ち上げられたり落とされたり、忙しいことです。
少し前までバナメイという海老の名前を知る一般の人はそう多くなかったでしょう。以前はお値打ちな海老の代名詞といえば「ブラックタイガー」で、当社の扱いもほとんどはこれだったのですが、数年前から徐々に主流は味が良いとされるバナメイに代わってきています。主にタイなど東南アジアで生産されます。
ところがタイでは、半年ほど前からバナメイに早期死亡症候群(EMS)という病気が流行しはじめました。海老が白くなり大量死してしまう病気で、原因がよくわからず、生産量が激減してきたのです。何しろ原因不明ですからこれといった対策も打てず、養殖業者もお手上げ状態。海老をあきらめ他の仕事に転ずる業者も多いのだとか。ベトナムなどでも大きな被害が出ています。
世界的な生産不足で、日本に輸入されるバナメイの量はどんどん減少し、値段は暴騰しています。大きなサイズのものは特に足りません(子どもの海老が成長し、大きくなる前に死んでしまうから)。バナメイが無いためブラックタイガーに需要が流れ、こちらも価格高騰・玉不足の状況が続いています。中国などに買い負けていることもあるでしょう。
業界では何ヶ月も前から話題になっていましたが、ニュースや新聞記事になって世間に知られるようになったのは10月初めくらいでしょうか。天丼チェーンがメニューから海老天をはずすとか、おせち用の海老確保に百貨店が東奔西走しているとか。
当社も売るものがなくなっては大変ですから、価格はともかく数だけは何とか確保しなければ、といろいろ動いていますが、なかなか潤沢な量を用意することは難しい状況です。10月のグランドフェアで数量限定の特売を打ちましたが、お得意様はまだそこまで危機感がないのでしょうか、用意した枠が余って、少々拍子抜けしました。しかし供給不足解消のめどが立っていないことに変わりはありません。
ところがその一方で…
三芳のいも恋食べもの
20131117
先日、東京から関越自動車道を通って長野に行く機会がありました。駒ヶ根の住民には関越はふだん使う用事があまりなく、私も十年以上通っていませんでした。
埼玉県に入ってほどなく「三芳」というサービスエリアが目にとまりました。三芳…みよし…おおそうだ、「いも恋」を買わなくては!
「のだめカンタービレ」16巻に、ほんの一箇所だけ登場する三芳のいも恋。主人公の師で世界的指揮者のシュトレーゼマンが、高速道を移動中に「三芳の『いも恋』食べタイ」と言っています。マネージャーのエリーゼは「だめです!またなにか変なもの買い食いする気でしょ!?」とスルーしてしまいます。
どんなお菓子(きっとお菓子だと思うんですが)だかわからない、何だろうなあ~と、ずっと思っていたのです。あまり時間に余裕はなかったのですが、車を停めて売店に入ってみました。専門のコーナーがあり、蒸篭で蒸したてのあったかいのを売っていました。
対面した「いも恋」とはいかなるものだったか?これは、想像していたのとちょっと違って、蒸し万十でした。長野の「おやき」みたいな茶色っぽい皮に、粒あん、そして厚さ1㌢弱のふかしたサツマイモの輪切りが入っています。
帰宅して早速食べてみると、おいしい。私はサツマイモというものをそれほど好まないのですが、これは芋のモソモソした感じが粒あんで上手にカバーされており、皮の食感とよくマッチしています。洗練されたお菓子ではありませんが、何というか、バランスが良いのですね。
東京へ出るときはいつも中央道を使うので、「信玄餅」や「月の雫」は見慣れていても、関越沿いのお菓子には馴染みがなく、珍しいものを食べました。群馬県や北信の人たちには「いも恋」もきっとお馴染みなのでしょう。シュトレーゼマンはこのお菓子、いったいどこで知ったのかな?
関連リンク: 菓匠右門 (川越名物いも恋)
展覧会の絵音楽ばなし
20131113
展示会のあとは展覧会。先週末の伊那フィル定期公演で演奏した曲です。ムソルグスキー作曲のピアノ曲をラヴェルがオーケストラ用に編曲したもので、クラシックファンにはもうお馴染みですね。クライマックスの部分は「ナニコレ珍百景」に使われてもいます。
早世したムソルグスキーの友人ハルトマン(画家であり建築家でもあった)が遺したスケッチなどを集めた遺作展が開かれました。ムソルグスキーは友人を偲んで絵を題材にした10曲と数曲のプロムナード(散歩-間奏曲)からなるこの曲を書きました。その後ラヴェルが色彩感にあふれた編曲をしたことで、「展覧会の絵」は世界中のオーケストラの重要なレパートリーになっています。
私は中学生の頃この曲が大好きになり、自分で初めて購入したクラシックのLPはこれでした。当時習っていたピアノの発表会ではこの組曲から何とか弾けそうな3曲を選んで弾いてみたり、学校の「一人一研究」でこの曲を無謀にもピアノ譜から吹奏楽に編曲してみたりしたものです。(結局音にすることはありませんでしたが)その曲を何十年かたって地元のオケで演奏できる日が来るとは、なかなか感慨深いものがありました。
この曲はオーケストラで使われることの少ない特殊な楽器がいろいろと登場することでも知られます。「古城」のアルトサクソフォン、「ビドロ」のユーフォニウム。どちらも登場するのは1曲だけですが、とても重要なソロを割り振られています。中でもサックスのソロを吹いたのは、今回オーディションで選ばれた地元の女子中学生。彼女は出演が決まってから何度かの練習を経て、一回ごとにうまくなり、本番は哀愁を帯びたメロディーをみごとに吹ききりました。
そしてフィナーレ「キエフの大門」には、鐘が登場します。ハルトマンが設計したキエフ市の凱旋門。ついに建造されることなく幻に終わった友人の傑作を、ムソルグスキー=ラヴェルは鳴り渡る「ミ♭」の鐘で彩りました。
この鐘はチューブラーベル(いわゆる、のど自慢の鐘)で演奏されることが多いのですが、せっかくこの曲をやるのだからと、楽器レンタル屋さんから本物の鐘を調達しました。この鐘を鳴らすのは、もちろん私。鉄アレイみたいな重い撥で叩いた合計39発、聴いていただいたお客様の印象に残ったでしょうか。
展示会でのおすすめ品食べもの
20131105
普段プロ野球にあまり興味のない私でも、日本シリーズの激闘には大いに楽しませてもらいました。6戦目でまさかの黒星を喫した田中が、前日160球を投げたにもかかわらず最後の9回に出てくるとは…。少々ヒヤヒヤしましたが、無事抑えきって本当に良かった。何試合も見ごたえのあるゲームを見られて、満足です。
さて、グランドフェアが終わってもう半月が過ぎました。展示会場で私の印象に残った商品を二、三紹介してみたいと思います。まず一品目は㈱太堀の「珈琲煮豆」500g。太堀さんは業務用のお惣菜を中心に営業するメーカーです。
珈琲煮豆なんて、ありそうでなかった品ですね。黒花豆を甘く煮たものがいわゆる「お多福豆」ですが、ほろ苦いコーヒーで煮たことで意外なおいしさが生まれました。お茶請けでも、お弁当にも、またパンの具材にもいいですね!
二品目はギャバンさんの「仁淀川山椒(ミル付)」14g。高知県の仁淀川に面した地域で収穫された、山椒の青い実を乾燥させたもの。あまり量産できるようなものではないとお聞きしています。普通の山椒とは一味もふた味も違う目の覚めるような爽やかな辛味が広がります。
まだ我が家で本格的に試すのはこれからですが、麺類、お豆腐、蒲焼などに。展示会で試食させてもらった、レアチーズケーキにひと振りした相性にびっくり!
どちらもぜひお試しください。
親日国トルコ (2)日々雑記
20131031
(1)を書いたのはGW明けでしたから、えらく間が空いてしまいました。安倍首相が二度目の訪問をし、またイスタンブールにヨーロッパとアジアを結ぶ大トンネルが開通したりして、トルコがまた話題になっていますね。
五輪招致が東京に決定したとき、競争相手だったにもかかわらず真っ先に祝福してくれたトルコのエルドアン首相、とても嬉しい気持ちにさせてもらいました。
24年前のこと、ほんの数日ですが一人でトルコに立ち寄ったことがあります。当時トルコには都市間鉄道がなく(今はどうなのかな?)飛行機でなければ長距離バスで何時間もかけて移動します。エーゲ海に面したイズミルという都市から、やや内陸の世界遺産パムッカレまでバスで往復しました。
バスターミナルでは、○○行は何時発!とバス会社の客引きがそれは賑やか。「ぱむっかれ~ぱむっかれ~、ぱむっかれやれぱむっかれ~」と物悲しそうに客を呼んでいる若者から切符を買ってバスに乗りました。出発するとじきに、車掌が車内を回って乗客に手を出すように促し、何かサイダーみたいな空き瓶に入ったコロン?を手のひらにたっぷり振りかけてくれます。
バスで隣に乗り合わせた30歳くらいの青年が「どこから来たの」と話しかけてきて、日本人だというと喜んでいろいろと会話してきました(英語で)。当方はそんなに話せるわけではなく、自然と短い単語のやりとりになりましたが…バスの中でコロンをかけてくれるのは不思議な風習だ、と私が言うと、「僕もそう思う」と言ってました。
それで話の端々から、どうもやっぱり彼は日本人が好きなんですね。彼に限りません。交通機関や食堂などで隣り合わせたトルコの人は、日本人とみると本当に片言しか英語を話せないような人までもが、目を輝かせて話しかけてくるのです。これには驚きました。
小さい頃から対ロシアの話やエルトゥールル号の話を聞かされているのかどうかわかりませんが、日本人にこれほどフレンドリーなトルコの人たち、これからも大事にしなくてはなりません。かつて風俗施設に彼らの国名を当てていたことは、深く反省しなくては。このときイスタンブールで本場のトルコ風呂(ハマム)に入ってみました。アカスリや飲物がついて、2,000円くらいだったかな。まあ一度くらいは経験してみてもいいか…という感じでした。
写真はパムッカレです。石灰岩の山に湧き出た温泉水が山の斜面を浸食し、お湯の流れる真っ白い棚田が自然に作られました。私が行ったときはこの写真のように多くの人々がお湯に浸かって楽しんでいましたが、今は温泉の乱開発で湯量が激減し、こうした眺めは見られないようです。
お墨付き食べもの
20131029
和食文化遺産の話を聞いたときに、すぐに連想したこと。数年前に農水省が立ち上げた「海外日本食レストラン認証有識者会議」、皆さん覚えていますか?(実際には今回のこととはまったく違う文脈のものでしたが)。
海外諸国で、オーソドックスな日本食とかけ離れた料理を出す「日本食レストラン」が急増している。それも日本人や日系人の店でなく、ロクに日本料理を食べたことさえなさそうな中国、韓国、アジア系移民によるものが多い。このままでは海外での日本料理の正しい理解につながらない…として、正統的な日本料理を出す店に第三者機関の認証(お墨付き)を与えようと、平成18年に提唱されたものです。
しかし内外から批判が相次ぎ、提唱当時の松岡農水大臣(ナントカ還元水の)が在任中に死去したこともあってでしょうか、何となく立ち消えとなって今に至っているようです。
批判の意見は今でもネット上に散見されます。寿司の現代形カリフォルニアロールや、ナポリには存在しないナポリタンスパゲティの例を引いて、美味しければそれでいいじゃないか、本物とか偽物とか、何で政府がそんなお節介を焼くのよ、といったものです。
アメリカのメディアは「日本が『寿司ポリス』を派遣するのか」などと猛反発であったとか。そんなものを押し付けたって、俺たちはこれをウマイウマイと食ってるんだ、文句あるか?ってなものでしょう。
私は日本食認証の趣旨に大いに賛成でした。当時の報道には誤解もあったと思います。アメリカ人が自分たちの好みに寿司をアレンジしたって何の問題もないし、それが美味しいか不味いかを判定しようというのでは最初からなかったはず。しかし、出鱈目な料理を「これが日本料理さ!」とする店が増殖するのをそのままにしておくことが、日本食文化の伝播に役立つとは思えません。「これが当店の日本風料理さ!」ならいいですよ。
私だってアボカドを巻いたカリフォルニアロール、好きです。世界にその愛好者が増えるのも大いに結構。ナポリタンはいま国内でかなりのブームになっていますが、郷愁のケチャップ味に惹かれる人が大人になって思う存分、大盛りのスパゲティを平らげるのも、楽しいでしょう。
しかし、カリフォルニアロールが本来の日本の寿司の姿とは違うこと。ナポリタンは戦後やってきたアメリカ文化が日本に定着したのだということは、できれば食べる人に知っておいてほしいです。「正しいもの」を知った上でアレンジは成り立つのですし、本家に対するリスペクトの気持ちは口に合う合わないとは別に、大切だと思いますから。
世界に日本料理の魅力を伝える手段として伝統をきちんと継承している店の認証は、クールジャパンのひとつの戦略にもなりえたはずで、この話がうやむやになってしまったのは、残念なことだと思います。
世界の文化遺産「和食」食べもの
20131026
大変うれしいニュースです。が、考えさせられることもあります。
---------------------------------
(産経新聞)政府が国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に提案した「和食 日本人の伝統的な食文化」について、事前審査を担うユネスコの補助機関が新規登録を求める「記載」の勧告をしたことが22日分かった。文化庁によると、過去の事前審査で記載勧告された提案が覆されたケースはなく、ユネスコの政府間委員会は12月上旬にも登録を正式に決定する見込み。
---------------------------------
そもそも和食とは何ぞや?という根本的な問題もあるわけで、外国人のイメージする代表的和食といったらスシ、テンプラ、ヤキトリ(ラーメンもか?)だとかだったりするわけでしょう。素材や技術の粋を尽くした高級懐石の素晴らしさは言うまでもありません。
当然これらのものも含まなくはないでしょうが、農林水産省によると、ユネスコに今回登録申請したのは
「自然を尊ぶ」という日本人の気質に基づいた「食」に関する「習わし」
だということです。その特徴として以下の4点をあげています。
―多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重―
日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっているため、各地で地域に根差した多様な食材が用いられています。また、素材の味わいを活かす調理技術・調理道具が発達しています。
―栄養バランスに優れた健康的な食生活―
一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。また、「うま味」を上手に使うことによって動物性油脂の少ない食生活を実現しており、日本人の長寿、肥満防止に役立っています。
―自然の美しさや季節の移ろいの表現―
食事の場で、自然の美しさや四季の移ろいを表現することも特徴のひとつです。季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、季節に合った調度品や器を利用したりして、季節感を楽しみます。
―正月などの年中行事との密接な関わり―
日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである「食」を分け合い、食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。
(以上、農水省のホームページより)
素朴な中にも繊細で変化があり、なおかつヘルシー、というあたりがポイントでしょうか。何だか、いま日本に暮らす私たちが失いつつあるような食生活のようにも思えます。あっそうか、だから未来へ残すべき「遺産」なんだ。日本人向けのメッセージでもあるのかな。
こうして世界に認められ、さてこれをもって海外からの観光客にどれだけ魅力をアピールできるかは、何とも言えません。ここでいう和食をどうやって売り物にするか、工夫がいりますね。上記の要素をさらにわかりやすく噛み砕いてメニュー化することとか。またお金を使ってもらうには、もうちょっと贅沢っぽい要素も必要だろうし。
関連リンク: 農水省ホームページより
展示会無事終了しごと
20131022
先週17日に行われた「伊勢喜グランドフェア」多くのお客様に来場いただき無事行われました。。
当日は好天に恵まれ、まずはひと安心。後からあとから切れ目なく来られるお客様にご挨拶していると、一日なんてもうあっという間ですね。
今年の目玉は「ギョギョ魚!」と題し、北海道の冷凍マグロと愛媛産の鮮魚をご提案しました。お寿司として用意したサンプルが次から次へとなくなり、やっぱり日本人はお刺身だね~、と思いましたな。当社も従来と同じことばかりやってはいられませんし、同業の食材問屋さんとの差別化ということもあります。何とかこの商売、いい形にしていきたいです。
メーカーさん約100社が出展いただきました。展示会も今年で38回を数えますが、出展社の数もバラエティも今が一番多いと思います。(会場の都合もあり、もうこれ以上は増やせない)私もメーカーさんのブースを一通り回って、少しは試食もしてみますが、やっぱりどれもプロ用の品、とても良くできていますよ。
準備には丸々2カ月をかけます。正直、主になって企画する人たちは本当に大変です。わが社くらいの規模では、会場設営にそれほどのお金をかけるわけにもいきませんし、自分たちの手を掛けて作るのですから。でも、この手作り感が当社展示会の「顔」になっているのだと思います。楽しみに毎年顔を出して下さるお客様に心から感謝です。
当日成約した荷物は今週からどんどん入荷しており、順次配送しております。これがきちんと完了できて、ようやく展示会もひと区切りです。
グランドフェアは明後日しごと
20131015
伊勢喜グランドフェア2013、いよいよあと2日となりました。当社にとっては年間を通して最大の行事、営業活動の最大の機会です。「特売品情報」のページをご覧ください。
とはいっても、朝からニュースを見れば台風26号のことばかり。少し重い気持ちですが、こればかりはどうにもなりません。
この記事を書いている時点の予報では、この辺りでは今日15日から明16日の昼過ぎくらいまで雨が降り、そのあとは回復するようです。展示会当日の17日は、うまくすれば晴れるかな?ぜひそうなって欲しいですが。
ただそれまでの雨で駐車場のグラウンドがぬかるみ、駐車スペースがじゅうぶん確保できにくい状況が考えられますので、ぜひ乗り合わせてお越しいただきたいと思います。また会場周辺にも駐車可能なエリアを用意しました。会場まで少し遠くなりますが、送迎バスを準備していますので、どうぞご利用下さい。
会場展示準備の方は着々と進み、昨日は社内で最終ミーティングを行いました。今日から営業社員は会場に貼り付いています。
ご来場のお客様に必ず、お役にたつものを持って帰っていただけるよう、お待ちしています!
ちりとてちん 再放送始まる読んだり見たり
20131010
最近テレビネタが続いていますね。NHKの2007年下期の朝ドラ「ちりとてちん」が今週から、BSプレミアムで朝7:15より再放送されています。知ったのは月曜日(第1回)の放送が終わったあとでした。残念、初回を録画し損ねた。
このドラマは、朝ドラのジャンルにとどまらず、テレビドラマ史上に燦然と輝く金字塔、最高傑作だと思っております。私は本放送当時、昼休みに観て、録画したものを夜もう一度、あわせて毎日二度ずつ観ておりました。これまで機会のなかった方にぜひ観ていただきたいと、ブログ読者の皆様に余計なお節介をしているわけです。
脚本は藤本有紀、出演は貫地谷しほり、和久井映見、渡瀬恒彦、青木崇高ら。朝ドラのヒロインらしからぬ、ヘタレで後ろ向きで根性無しの主人公。塗箸職人の娘が故郷の小浜を出て大阪で落語と出会い、女流落語家として成長していくお話です。
放送当時は視聴率がいま一つかんばしくなかったと聞きます。関西弁が苦手、という方もいたでしょうか。しかし(私のような)熱心なファンもまた多く、DVDの売上は№1だとも聞きます。
このドラマの魅力はそれこそ無数にありますが、
・かつてなかったヘタレヒロインの存在自体が面白い
・物語や設定、登場人物が落語の文脈でできている二重写し(もちろん知らなくてもOK)
・網の目のように膨大に張り巡らされた緻密な伏線と、完璧な回収(これはもの凄いものです。圧倒されます)
・脇役一人ひとりに至るまで、血の通った見事な人物描写と俳優たちの演技
・細部まで凝りに凝った美術や、音楽の素晴らしさ
こうしてみると、落語云々は別にしても結構「あまちゃん」と共通するな、と思われるでしょう。あまちゃんも(最後の一か月は別にして)いいドラマでした。しかし、その前に「ちりとてちん」を観てから言ってちょうだい、と私は思うのですよ。実はあまちゃんの劇中には、明らかにちりとてちんのパロディというかオマージュというか、引用がいくつも出てきています。
本放送の時は、この15分のドラマで毎日笑い、毎日泣かせてもらいました。また半年の間この傑作が楽しめるとは…ぜひ、ぜひ、お勧めします!
関連リンク: ちりとてちん (NHKホームページ)