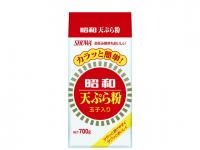指揮者の暗譜 (2)音楽ばなし
20140901
指揮者の故岩城宏之氏は、著書の中でたびたび暗譜について書いています。今振っている曲を、完全に空で楽譜を書き起こせるかと言われれば、「正直言って、僕はお手上げだ。インチキをやっていることを、心から恥じる」と心中を明かしています。そりゃそうですよねえ、そんなこといくらプロでも、やたらとできるわけないじゃないですか。
ところが、彼ならきっとできるに違いないと岩城氏が名前を挙げているのが、マゼールなのです。彼の記憶力はまさに超人的。もちろん音楽史上のすべての曲を憶えているわけではないでしょうが、少なくとも自分のレパートリーとしているものは悉く完璧に記憶しているに違いない…と同業者たちには信じられているようです。
暗譜することと、素晴らしい演奏ができるかどうかは、全然別の話ではありますが…。
暗譜に力を入れるより曲の解釈の方が大事だというのは、まったくその通り。プロの名指揮者でも、本番のステージでは決して暗譜で指揮をしないポリシーの人も大勢います。当然、曲中に膨大に存在する勘所はきちんと憶えているのでしょうけれど。
私もコンサートの指揮台に立つとき、神をも恐れず暗譜で臨んだことがあります。最初はまだ高校生の時、吹奏楽部の定期演奏会で。このときは、一応譜面台にスコアを置きましたが、ページをめくることなく十数曲すべてを暗譜で指揮しました。(狂気の沙汰。いったい、いつ勉強しとったのだろうか?)
最後の曲で、大事故が起きました。複雑な場所で何人かの人が出を同時に間違え、続く人たちがどこで入るかわからなくなって、もう曲が止まる寸前まで行きました。万事休すと思いましたが、一人のメンバーが度胸を決めて吹き始めてくれたおかげで、曲は奇跡的につながりました。このときもしスコアを見ながら指揮していれば、もっと早い段階で多くのサインを出すことができ、早く元に戻れていたかもしれない、と悔やみました。15秒ほどのことでしたが。ああ、若かったですね。
指揮者の暗譜は単なる恰好付けではなく、実はいろいろメリットがあるのです。まず譜面をめくるのに、左手をいちいち使わなくてもいいということ。これ、意外とわずらわしいものです。1曲で数十回もあることですからね。
そしてもっと大きいのは、スコアに目を落とすことなくずっとオケメンバーの顔を見て指揮できることです。指揮者は指揮棒で合図するのではなく、目で指揮するのだ、というくらいですからね。私はそう思うのですけれど。
二度目に暗譜に挑戦したのは、伊那フィルを振るようになって3年ほどたった頃。前回のことがあったので本番ぎりぎりまで迷いましたが、音符一個一個まではともかく、曲の進行はきっちり頭に入った、やれると判断して、譜面台を置かずに指揮しました。メンバーとのアイコンタクトが嬉しく、オケがすごく近くになったように感じました。
それ以来、やり慣れたごく小さな曲は別にして、本番を暗譜というのはやっていません。でも、挑んでみたい気持ちはあるのですが。
ロジャー・バートレット、死す日々雑記
20140826
ついこの間、ヘンドリーの訃報を聞いたばかりなのに。ロジャーも、帰らぬ人となったよ。
イギリスの俳優・映画監督、リチャード・アッテンボロー氏が死去しました。俳優としては「大脱走」「ジュラシック・パーク」など、監督としては「遠すぎた橋」「ガンジー」「コーラスライン」などが代表作ですが、私にとってこの人は何と言っても「大脱走」の"BigX"ことロジャー・バートレット中隊長に尽きます。私と同世代の多くの男性は、きっと賛同していただけるのでは。
小学生の頃、ゴールデン洋画劇場などで何度も放送され、そのたびに繰り返し見た大脱走。当時ホームビデオなどはなく、カセットテープに音だけを録音して台詞や音楽を聴いて楽しみ(三谷幸喜氏も同じことをしていたそうな)、さらには友達と8ミリカメラでこの映画を再現しようと試みたこともあります。台本書きに友人宅に泊まり込んだりし、完成には遠く至りませんでしたが、これは小学生最高の思い出です。
オートバイをかっ飛ばすヒルツ(スティーブ・マックイーン)のカッコよさもさることながら、私は捕虜たちのリーダーとなって沈着冷静に指揮をとるロジャーに強烈に惹かれました。ドイツ軍の捕虜収容所から森へひそかにトンネルを掘り、偽の旅券や身分証明書・衣装までを用意して大勢の捕虜を一気に脱走させる大プロジェクトをやってのける痛快さに、胸がわくわくしました。
ロジャーは何度も脱走計画を首謀したとしてゲシュタポにマークされており、この脱走でもドイツ語フランス語を駆使してドイツ兵たちを煙に巻く鮮やかさでしたが、仲間の不注意から逮捕され、銃殺されてしまいます。計画では250人を逃がすはずでしたが、結局脱走に成功したのはわずか3人でした。
この映画、もう何十回観たことでしょうか。アッテンボローは役者としては大スターと呼ばれる存在ではなかったと思いますが、この1本で私には忘れられない俳優でした。一般には監督としての評価の方がずっと高かったかもしれません。
ちなみに捕虜の一人ヘンドリー(ジェームズ・ガーナー)は各種資材等調達係で、看守から重要書類をスリ取ったり、トンネル掘り用のピッケルを盗み出したり飄々としながらの大活躍ぶりでした。ガーナーも先月亡くなり、これで大脱走の主要人物ほとんどが、世を去りました。
ターンオーバー食べもの
20140823
そんなわけで、目玉焼きの流儀は百人百様なわけですが、私が最近好んでいるのは「ターンオーバー」、つまりひっくり返して両面を焼いたやつです。。存在はずっと昔から知っていますが、何でわざわざそんなことするんだろ?と、試したこともありませんでした。
ホテルの朝食バイキングで、卵料理を目の前で焼いてくれることがありますよね。私はずっとオムレツ派だったのですが、あるとき「そういえば最近目玉焼き食べてないよな…」と思い、そうだ、せっかくプロが焼いてくれるんならと食べたことのないターンオーバーを注文してみたのです。
若いコック氏は平然とうなずき(当たり前)卵2個を使ってたちまち綺麗な両面焼きを作ってくれました。
これがですね…なかなか良かったのですよ。私に言わせれば目玉焼きという料理の弱点は、おいしい半熟の黄身に、味気ない白身が必ずセットになっているところです。その白身の表面にちょっとだけこんがり焼き目が付いたことで、全体を香ばしくおいしく食べることができるではないですか!
黄身には当然のことながら、普通のものより幾分強めに火が入ります。もちろん完全に固くなってしまっては悲しい。でも液体ではなくとろっとして、固体になるかならないか微妙な状態の黄身はいいです!これで私はたちまち、ターンオーバー党の党員になってしまいました。
帰って妻に話したところ、早速作ってみてくれました。最初はやはり、返した時に綺麗な形にならなかったり半熟の火加減がうまくいかなかったのですが、二、三回試すうちに上手にできるようになりました(失敗することもありますが、なあに味には変わりはないさ)。当分この流儀でいこうと思っています。
ところであるホテルでターンオーバーを頼んだら、既に出来上がってお皿に載っていた目玉焼きをもういちど鉄板の上に戻し、反対側を焼いてさあどうぞ、という時がありましたが、何だか釈然としませんでした…
お客はわがままなものですな。
目玉焼き食べもの
20140817
目玉焼きの黄身、いつつぶす?
と題した変てこなアニメを、天下のNHKで深夜に4回連続でやっておりました。。ジローという主人公が、彼女との食事中ちょっとした習慣の違いに驚き(もうすごい驚き様で、笑っちゃいます)さらに職場の上司から第三の方法を教えてもらい、懊悩するというもの。ゲストに壇蜜(実写)ら。この記事を書くために検索したら、原作のコミックがあるのですね。
表題のほか、
・カレーのルーをライスにどうかけるか
・とんかつのキャベツをいつ食べるか
・ちらし寿司にわさび醤油をかけるか
など、一回の放送で二つずつ、さまざまな小ネタを取り上げておりました。
目玉焼きは昔、伊丹十三が「家族ゲーム」の中で、いきなり黄身を破ってお皿に口をつけチュウチュウ吸ったのがおかしかった。妻(由紀さおり)がたまたま固い目玉焼きを作ったら、「こんなに固くちゃチュウチュウできないじゃないか」と文句をつけ、「あなた今までチュウチュウしてたんですか…」と呆れられていました。この家族はいつもてんでばらばらに朝食をとる設定なので、妻は知らなかったわけだ。
伊丹氏は著書で目玉焼きの食べ方について書いていますが、彼がプライベートでこういう食べ方をしているわけでは、もちろんないそうです。
糸井重里氏は、適当に白身を食べていきながらタイミングを見て黄身をつぶし、とろーんとした黄身を白身でぬぐって食べると言っています。お皿も汚れないと。でも、せっかくの黄身のおいしさが白身で薄れてしまいそう。
私は、周りの白身を食べていき、最後に残った大事な大事な黄身をご飯に載せてエイヤッと食べますね。だいたい目玉焼きの白身は、それだけ食べて大しておいしい味のあるものではないし、塩でも振って先に片付け、最後に黄身を楽しんでいます。子供みたいですな。ジローの彼女、みふゆさんもそうしているようです。
上記の二氏だけでなく、目玉焼きの食べ方について検索してみますと、実に大勢の人が言及していることがわかります。誰もが食べているものですが、ちょっとざわざわした気持ちになる、不思議な存在ですね。
最初から玉子2個使えば、1個は早々につぶし、2個目は最後に楽しめると思いますが…一度に玉子2個を目玉焼きで食べるのも、別の意味でざわざわするような気もします。
のろのろ台風日々雑記
20140810
何てことじゃ、せっかくの盆前休日を台無しにしおって!
と、波平さんのように台風11号に文句を言ってみたところでどうしようもないのですが。このおかげで大型連休の出端が少なからず挫かれてしまいました。
普段だと台風災害の少ない伊那谷です。我が家では朝から断続的に降ったり止んだりのお天気で、午後1時過ぎから雨が激しくなっています(現在2時半)。気象庁のHPを見ますともうしばらくは雨が続きそうです。
昨夜のTVでは三重県に「大雨特別警報」が出て、緊張した表情の男性が「これまでに経験のないような大雨となり、すでに土砂崩れや浸水などの重大な災害が発生しているおそれがある」と言っていました。NHKのアナウンサーは「ただちに、命を守るための行動をとってください」と。最近、ただ事ではないぞ、という意思を伝えるためにギョッとするような言い方をするようになりましたね。いいことだと思います。広い範囲で何日も前から相当な量の雨が降っていますが、これ以上の被害がありませんように。
さてこんなお天気の中、以前のブログ(2013.2.12)でご紹介した「トランスジャパンアルプスレース」が今日午前0時にスタートしています。魚津港をスタート、北アルプス、中央アルプス、南アルプスを縦断し静岡市までを走り抜ける(!)山岳マラソンレース。詳しくは主催者のホームページ(すごく重いです)を見ていただくとして。
出場選手一人ひとりの位置がGPSである程度わかるようになっています。過去2回連続優勝の望月選手、今回もぶっちぎりでスタートダッシュをかけているようです。そうはいっても猛烈な雨と風の中、まずは遭難することなく無事に帰ってほしいですね。駒ヶ根通過の際は、ぜひ励ましの声をかけてあげたいものです。
関連リンク: トランスジャパンアルプスレース
節電しごと
20140805
ああ猛暑!
なんていうと、群馬や岐阜など、38度39度というホンモノの猛暑の真っただ中の方々には笑われてしまいそうですが、それでも日中はそれなりの暑さです。さいわい、朝晩はもうだいぶ涼しくなりました。これなら本来の当地の夏の気候ですね。
さて、右肩上がりの電気代節約のため、当社では昨年夏から電気保安協会の「デマンド」という電気使用量モニターを入れています。
ご存知の方もいらっしゃるでしょうが、電気代の基本料は「単価×使用料」。ここでいう「単価」というのは、「一年間で最も電気をたくさん使った30分間」の電気使用量の大小で決まります。つまりピークを低くすることで、むこう一年間の電気代をある程度節約できるわけです。
このモニターが、設定した30分間の電気使用量をオーバーしそうになると、ピーピーと警告音を発して注意を促してくれます。そうすると人のいない場所の照明を消したり、とりあえず使っていないパソコンやプリンターの電源を切ったりして様子をみます。
当社の最大の電気使用元は言うまでもなく、24時間フル稼働の冷凍冷蔵庫です。そのほかには照明、OA機器くらい。中で働く人には申し訳ないのですが、エアコンは使っていません。すでにそれなりの節電環境にあると思っていますので、これをさらに絞るのは、なかなか難しい。
冷凍庫が一日何度か霜取りをします。この時は電気量が目に見えて増えます。以前は数台ある冷凍機が同じようなタイミングで霜取りをしていたため、ピークが高くなっていました。(会社休日のグラフで歴然とわかります)この時間帯を少しずつずらすことで、今はピークは平準化しています。
気温が上がり冷凍庫の開閉が激しい昼近くになると、最近は毎日のようにピーピーと警告音が鳴り、そのたびにみんな大慌てで明かりを消したりしています。今のところは昨年のピークよりかなり低い水準で推移できています。何とかこの苦労が報われると良いのですが…
遠いあと一歩日々雑記
20140728
熱い暑い週末でした。。
高校野球には大して興味がない私ですが、今年は息子の通うT高校が有力チームとして注目されていて、またご近所の農業高校J高校の目覚ましい活躍ぶりが話題となっていました。両校とも準決勝に駒を進めましたので、土曜日は珍しくもTV観戦しました。
J高は好投手を擁し、これまで全試合無失策の堅い守りで、創立以来初めての準決勝進出です。相手は私立の強豪で、かなり力の差があるかなと思って観ていましたが、相手投手の立ち上がりを捉え先行し、息詰まる投手戦を繰り広げました。1-1で迎えた9回裏、エースピッチャーがついに力尽き連打を浴びてサヨナラ負けしましたが、実に締まった好試合を見せてもらいました。拍手。
T高は春の選抜出場校、夏の予選はくじ運にも恵まれて、有力校が次々と敗退する中、着々と白星を重ねました。この時点では、決勝進出は濃厚だと思われました。
初回いきなり3点を先取しましたが、相手も粘ります。私は出かける用事があったためここからはラジオ観戦で、一時は7-3とリードしていたのですが、8回に追いつかれます。9回裏走者二、三塁でT高投手が暴投、あっけない幕切れとなりました。いや残念でした。甲子園に行くことになったら、応援に行こうと真面目に思ってたのに。
期待していた両校が共にサヨナラ負けでしたが、翌日の決勝戦は6点差をひっくり返す逆転試合で、J高を破ったS高校が県代表となりました。準決勝を完投したS高の2番手投手はエースの不調で急遽2回から登板し、予定外のロングリリーフでしたが、気迫の投球、お見事でした。
昨日は石川県大会決勝で、9回表まで0-8だったのを9回裏に一挙9点を挙げて大逆転サヨナラと、信じられないようなことが起きています。普通ならコールドゲームで9回を待たずに試合終わってますものね。高校野球、いろいろなことが起こるものです。
あと一歩のところで勝ちを掴み損ねた高校生たち。さぞかし悔しかったろうと思います。勝負の厳しさはほんの紙一重であることを、たくさん見せてもらった週末でした。
どく入り危険日々雑記
20140723
連日世間を騒がせている「脱法ハーブ」の名称が生ぬるいとして、警察では別な呼び方を募集していましたが、このほど「危険ドラッグ」と命名されることになりました。。
日常さまざまなアイテムにおいて、名前の印象は人々の心情をずいぶん左右します。脱法という言葉に、何となくアウトロー的なカッコよさをイメージしてしまう人がいるかもしれませんし、ハーブというのも、さわやかさを連想させる語感です。脱法ハーブという言葉からはその深刻な危険度は感じにくく、呼び名を変えるのは大変いいことだと思います。
しかし「危険ドラッグ」ですか…何だか、危険性がいまひとつ真剣に伝わってこないような気がしますね。脱法ならぬ、脱力してしまいそう。人気を集めた名称案は上位から順に「準麻薬」「廃人ドラッグ」「危険薬物」ということでしたが、麻薬とか薬物という単語は法令用語と重なるため避けた、そうです。
私は「毒入りハーブ」というのがいいんじゃないかと思いますけど。いくらハーブでも毒入りとなれば、かなり印象悪いでしょう。まがまがしい感じが出ていると思いますがね、いかがでしょうか。
似たような話で、「暴走族」という呼び名が青少年たちの憧れを誘い、カッコいいものだと思わせる一因となっていると、ずいぶん前から言われてきました。若者のやり場のないエネルギーのはけ口として、ポジティブに取る人もいそうです。多くの人々を轟音で威嚇し、無茶な走行で周囲の車両を危険にさらしている多大な迷惑が、この言葉からは感じ取りにくいですね。
匿名掲示板2ちゃんねるでは一頃「暴走族」という呼び名をやめて「珍走団」にしよう、と呼びかけがされたことがあります。ここまでダサい名前であれば、相当な効果がありそうです。一部、警察などでも実際に使われたことがあるそうですが、あまりに冗談みたいなネーミングゆえか、定着しませんでした。
最近は暴走族の数そのものが減少しているらしく、メディアに登場する機会も少ないように思います。毒入りハーブもとい危険ドラッグも、これを機にやたらと手を出す人が減ってくれればいいですが。
指揮者の暗譜 (1)音楽ばなし
20140721
名指揮者ロリン・マゼール氏の訃報が先週伝えられました。84歳。つい最近まで元気一杯でコンサートを指揮していたと聞きますから、急なことだったようですね。まだまだ活躍できる人だっただけに、残念です。
私がマゼールの指揮をナマで目にしたのは過去一度だけ(正確には二回)です。昭和63年秋、ミラノ・スカラ座歌劇場の来日公演「トゥーランドット」をNHKホールに観に行きました。この時の公演は、私がこれまでに経験した舞台(芝居、オペラ、コンサートすべて)の中で最大の感動感激でした。マゼールの音楽は大変アクが強く、異様にデフォルメされてある意味奇怪とも言えるようなものでしたが、彼のスタイルがこの曲にはとても良くマッチし、強烈な印象を残してくれました。
演奏の内容もさることながら、この時マゼールは譜面を開くことなく、暗譜で指揮しました。全三幕、演奏時間2時間半、スコア(指揮者用楽譜)で461ページにわたる大編成で複雑な音符と歌詞をすべて頭に入れ、何も見ずに指揮していたのです!
暗譜とは、楽譜を暗記し、前に置かずに演奏することです。ピアニストもヴァイオリニストも、リサイタルや協奏曲では基本的に暗譜をし、曲を完全に頭に入れ体で覚えて演奏します。プロなら、ごく普通のことです。(高齢な人とか、あるいは複雑な現代曲などでは譜面を見ることも多い)
指揮者の暗譜はちょっと意味が違います。自分で音を出すことのない指揮者は、極端に言えば曲の流れさえわかっていれば、一応オケの前で指揮して曲を通すことはできます(私にも、まあ、できます)。でもそんないい加減なことをすれば、楽員たちにすぐバレてしまうでしょうけれど。
オペラの場合は、そうはいきません。歌手たちがステージで演技し歌うのを把握しコントロールしていくのですが、彼らは楽譜を持っていません。出を間違ったり繰り返しを忘れたりといった「事故」の起こる危険性は、普通のコンサートよりずっと高いのです。いや、実際にもしばしば起こるといいます。
その時指揮者はすかさず、この先数十小節の楽譜を瞬時に思い浮かべ、歌手やオケに合図を出しながら(もちろん口なぞ使えませんヨ)曲をどうにかしてつなげ、音楽の進行を元に戻さなければなりません。動揺する関係者を指揮棒一本で落ちつかせ、何事もなかったようにするのですから、すごいことです。暗譜でオペラを振るのは、そうしたリスクにもきちっと対応できる自信があるということです。
本当の厳しい意味で指揮者が暗譜するということは、すべての楽器の音と流れを完全に頭に入れ、何も見ないで楽譜を五線紙上に再現して書き記せる、ということでしょう。交響曲1曲に書かれる音符のオタマジャクシの数は、少なくても数千個、大規模な曲ならおそらく数万個になると思います(私の勘)。いくらプロの指揮者だからって、いったいそんなことが可能なのでしょうか。
天ぷら粉 こと始め食べもの
20140713
NHKで「COOL JAPAN」という番組があります。何人かの在日外国人たちが日本特有の文化あれこれを体験して、それが「Cool(カッコイイ!)」であるかどうかを英語で議論しています。興味あるテーマのときに見ていますが、先日は「天ぷら」が取り上げられました。
天ぷらはある意味「世界における日本食」を代表する存在になっていると思っていましたが、スシと比べるとまだまだ知名度にかなり開きがあるようですね。番組前半では、スーパー惣菜売り場にずらりと並んだ豊富な種類、料理上手な主婦の工夫(ブリ大根など残り物を使った天ぷら、廃油を固めて処理など)、高級店の薄くて軽い衣へのこだわりなどが紹介されました。油固化材の存在を皆知らないようでしたが、外国にはないのかな。
よく、日本料理はヘルシーで人気だといいます。天ぷらが低カロリーだというのはあまり解せませんが、具が野菜や魚だから、肉食に比べれば意外とカロリーは低いのでしょうか?アメリカでは揚げ物といえばフライドチキンだけ、中国でも野菜を揚げることはないそうです。番組常連の恰幅のいいフランス人女性は「天ぷらなんて全然ヘルシーじゃないわよ、私の国じゃ流行らないわ」と切って捨てていましたが。(この方、いつもずけずけ言いますね)
さて番組後半は、水に溶くだけでサクっと揚がる「天ぷら粉」の開発物語です。当社と大変ご縁の深いメーカーさん、昭和産業の鹿島工場が登場しました。7、8年前かな、社員数名で工場見学させていただいたこともあります。
開発を始めたのは1958年のこと。天ぷらの衣には小麦粉、卵、水が必要だということで小麦粉に卵の粉を加えてみたが、なかなかふくらまない。粉を混ぜるときに卵白が空気を抱えて発泡するのがミソだったのですね。ふくらし粉(ベーキングパウダー)を使ってみますと、ふっくらとはするが、サクサク感が出せません。小麦粉のグルテンが出て、粘りが強くなってしまいます。
あれやこれやと試行錯誤。ヒントは身近なところにありました。鶏唐揚げの衣に片栗粉を使うことに気づき、澱粉、それもコーンスターチを使ってみると見事に成功!プロが揚げたような家庭の天ぷら、完成です。開発開始から一年後のことでした。
満を持して発売したのですが、あらかじめミックスしてある天ぷら粉を使うことは当時「主婦の手抜き」だと思われ、まったく売れなかったそうです。今とは隔世の感がありますな。日本国内では売れませんでしたが、当時日本食ブームが始まりつつあったアメリカで大ヒットし、在庫を掃くことができたのだとか。その後日本でも女性の社会進出などを受け、ようやく売れるようになりました。
知恵と技術の詰まった天ぷら粉。完璧を求める日本人の姿がCoolだと番組で絶賛されました。今では「昭和の天ぷら粉」はトップブランドとして地位を確立しています。当社も昭和の家庭用・業務用のさまざまな天ぷら粉を年間十何トン販売しています。ぜひ、ご利用を。
この記事で当ブログも500回目を迎えました。スタートしたのは2010年4月のことですから、4年3か月になります。最近ちょっと更新ペースが落ち気味ですが、これからもマイペースで書いていきますので、どうぞよろしくお付き合い下さいませ!