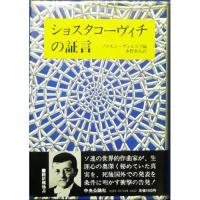強制された歓喜 (2)音楽ばなし
20121129
ヴォルコフによる「証言」は、衝撃的な内容で世界の音楽愛好者たちをパニックに陥れましたが、これが本当にショスタコーヴィチ自身の言葉なのかどうか、発表直後から真贋論争となっています。ヴォルコフの捏造であり信用が置けない、という研究者も数多くいます。当時学生だった私も買って読んではみましたが、この頃は彼の曲をまだそんなに知らなかったこともあり、あまりピンとこないものでした。
さて私自身がこの「交響曲第5番」を半年間稽古してきて、解釈をどう捉えるか、なのですが…
それまでの楽章で次々と現れる、凛と張りつめた悲劇の予感と熱狂、グロテスクなまでの皮肉と嘲笑、凍りつくような孤独感と激情あふれる慟哭。問題の終楽章はこれらを受けて、堂々たる行進から始まります。
しかしそれは、常にせきたてられるような焦燥とうらはらであり、中間部で現れる安らぎもどこか落ち着きのない不安が忍び寄っているように聞こえます。純粋な希望(救い)が感じられるのは、中間部最後のわずか8小節、ハープのソロの部分だけではないかと思います。
そして迎える輝かしいはずの終結部。私にはやはり、このフィナーレを開けっぴろげな歓喜と感じることは難しい。堂々としているけれどどこか空虚な、まさしく強制された歓喜とイメージする方がしっくりします。この場面を仕切るティンパニ奏者(私)の役目は、全オーケストラを威圧し、鼓舞し、強制することです。
でも、これはあくまで私自身の持つ印象であり、聴く人によって捉え方はそれぞれでしょう。いちいち小難しい理屈を考えなくても、豪快な迫力とあふれる抒情を楽しむ聴き方ももちろんOK(むしろこの方が一般的かな)。近代史のうねりの中で生まれた20世紀を代表する名曲を、多くの方に聴いていただきたいと思います。
★ ★ ★ ★ ★
伊那フィルハーモニー交響楽団
第25回定期演奏会
12月2日(日)午後2時開演
長野県伊那文化会館
チャイコフスキー:「くるみ割り人形」組曲
ショスタコーヴィチ:交響曲第5番
指揮・征矢健之介
強制された歓喜音楽ばなし
20121128
今週末、伊那フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会にティンパニストとして出演します。年1回の定期公演、今回のメイン曲は、ショスタコーヴィチ作曲の「交響曲第5番」です。
ショスタコーヴィチは、ロシア革命後のソビエトで活躍した作曲家です。交響曲第5番は彼のもっとも有名な代表作ですが、いろいろと一筋縄ではいかない「曰く」のある曲でして、完成から80年近くを経て今なお、解釈の分かれている曲なのです。
彼は若くしてスターリン体制の覚えめでたく、将来を嘱望されながら活躍していましたが、1936年に発表したオペラとバレエがそれぞれ「支離滅裂、退廃的、反体制的」だとしてスターリンの意思を受けたプラウダ紙上で酷評されてしまいます。この時代、反社会主義者とのレッテルを貼られることは芸術家生命にかかわるばかりか、強制収容所送りにもなりかねませんでした。事実、彼の友人たちにもこうした悲惨な目に遭った人は多く、彼は人生における大きなピンチを迎えました。
彼が生き残りを賭け起死回生の作品として翌年発表した交響曲第5番は、社会主義的リアリズムを見事に体現したものだとして政権から絶賛されました。シンプルな構成、悲劇的な楽想から歓喜へと進む明快さはまさに革命の勝利を想起させるものでした。こうして彼は危機を乗り切ったのです。
ところが後年、彼の死後しばらくして、音楽学者ヴォルコフによって衝撃的な「証言」が発表されました。作曲者自身による回顧録だとしてソ連国外でだけ出版した「ショスタコーヴィチの証言」です。
「証言」は「私の交響曲は墓碑である」という章の中で交響曲第5番の終楽章に触れており、あの輝かしい勝利の凱歌は「強制された歓喜なのだ」と言っているのです。さあ喜べ、喜べ、社会主義の勝利を栄光を祝うのだ、と背中に銃口を向けられながら必死で手をたたき、万歳をしてみせる人々の様子が目に浮かびます。
この証言が真実ならば、今までこの曲に誰もが抱いていたイメージは、まったく正反対のものだったということになります。彼は本当にスターリンをあざむき、見せ掛けの歓喜の曲を作曲し、心の中で舌を出していたのでしょうか。
続きます。
ねぎ豚食べもの
20121123
dancyu「日本一のレシピ」シリーズ第2弾。
結婚してからずっと、男子厨房に入らずを実践しています。ご飯を炊くのとカップラーメンにお湯を入れる以外の調理行為なんて、子供の前では片手くらいしかしたことがありません。自ら手を出すことはないくせに、ああだこうだと我が家のシェフに口を出してはうるさがられているわけですが。
今日は妻が珍しく遠出をしており、私と子供二人で留守番です。普段なら「どっかへ食べに行くか?」なのですが、気まぐれで晩飯を作ってみようなんて思いました。
作りましたのは先日のdancyu誌で「ピェンロー」の次の頁に載っている「ねぎ豚」。豚角煮の超・簡略版です。以前妻が作っておいしかったこともあり、またレシピを見ると、これだけ簡単なら私でも子供の前で父親の権威を失墜させることなく作れるかな、と。
これが、本当に簡単で、果たして料理をしたなんて言えるのかどうか疑問に思うくらいのものなのです。大量のネギを適当な長さに切って鍋に敷き詰め、その上に豚バラブロックを3センチくらいの厚さに切って置きます。紹興酒、醤油、水。あとは火に掛けて90分。ネギがとろとろになるまで煮ます。
出来上がったものは、そうですね、子供が喜んでむしゃむしゃ食うくらいのものにはなりました。「これお客さんに出せるんじゃないの?」なんて、どこで覚えたのかオヤジ殺しの台詞をのたもうたりね。味は腕でなくレシピのお陰だということはとっくにバレてます。
いや実際、なかなかおいしくできましたよ。この作り方でだって、本式の角煮とはホントのところかなり距離があるとは思いますが、材料に皮付きの豚肉を使うとかしたら、結構いい線いくのではないでしょうか。
豚の角煮は大好物です。中でも以前近所の中華屋さんで作っていたものは本当においしかったのですが、残念ながら閉店してしまいました。作り方を教わっておけば良かったなあ、なんて妻と二人で言ったりします。
中身は空っぽ食べもの
20121120
子供が修学旅行で長崎へ行き、お土産に名物だというお菓子を買ってきました。カステラじゃないですよ。
そのお菓子、一○香と書いて「いっこっこう」と読みます。○は口(くち)のことですね。
外見は焼き饅頭を思わせますが、手にしてみるととっても固い。いや固いの固くないのって、容易には歯が立たないくらいの固さです。そして妙に軽いこと。
割って中身を見てみますと…なんと空っぽ!
生地の内側に狐色の飴がへばりついていて、とても変わった独特の食感です。ちょっと粉っぽさも感じますが、全体としては、やはり飴の味わいが主体になっています。ヌガーみたいな感じでしょうか。
製造者「茂木一○香本家」のホームページを見てみますと、中国伝来の焼菓子で、「小麦粉と水あめで練り上げた生地に黒砂糖、水飴、上白糖3種の甘みのある餡を包んでつくるのですが焼き上げるときに中のあんこが沸騰し外に出ようとする力で膨らみ中身が無くなってしまいます」とあります。不思議だ。
この店では170年の歴史を持つお菓子です。長崎のほか佐賀や愛知にも同種のものがあり、また四国では「唐饅頭」という名で同じようなものがあるそうです。からくりまんじゅう?空っぽのまんじゅう?それとも中国の「唐」?いろいろ掛けてあるような名前ですね。
なかなか珍しいものを食べました。
関連リンク: 一○香の歴史 (茂木一○香本家)
信濃路を駆ける日々雑記
20121118
この時期の信州の風物詩「長野県縦断駅伝」が今年も行われました。
長野県の北から南へ22区間、220㌔近くのコースを2日間にわたって走り継ぐ駅伝で、今年で61回目とのことですからなかなか長い歴史を持っています。私の小学生の頃には、授業を一時中断して沿道へ出て応援した記憶もあります。(ということは、当時は平日にやってたのだろうか?)
県下各地から地域ごとの代表15チームが出場しますが、当社の位置する「上伊那」チームは昔から強豪といわれています。過去優勝33回と全チーム中最多の優勝回数を誇っており、それこそ私の子供の頃は殆ど負けたことがなかった強豪でした。しかし近年は他のチームの躍進もあり、05年以来優勝しておりません。
大会2日目のコースは我が家のすぐ近くを通ります。中継所も近く、沿道にはたくさんの人が応援に出ています。上伊那地域を走る区間は応援の人垣がずっと途切れないといわれ、これは他の地域にはないことだそうで、地元選手は否が応でも張り切る由。私も用事で留守している年以外は、必ず人垣に並んで応援しています。
一日目、5位にとどまった上伊那チーム。今日の走りはどうかとガヤガヤ待っていますと、予想したより若干早く先頭の選手が通過。なかなか後続がやって来ません。早く来ないかと待ち焦がれますが、上伊那はトップに約5分遅れ、5位のチームと1秒差の6位で中継所を通過しました。
最終順位はやはり5位で、今年も優勝はなりませんでした。息子の同級生M君も上伊那チームの選手に選ばれ、高校生ながら大人に交じって力走し、区間4位と頑張ったとのことでした。
かつての常勝時代が懐かしく、何とか優勝にからんでほしいと思うのですが…駅伝が全国的なブームとなり、佐久長聖高校の活躍などもあって、県下各地で駅伝人口が増えたこともあるのでしょうか、なかなか昔のようにはいきませんね。
乾坤一擲日々雑記
20121115
ついに伝家の宝刀を抜き、大勝負に出た野田首相。。
党首討論のあったこの日は東京に出張しており、午後は政治記者、岸井成格氏(サンデーモーニングでおなじみ)の講演を聞いておりました。講演の中で岸井氏は、早ければ二日後の16日、遅くても22日には解散をするだろう、と述べ、政局ばかりの最近のニュースに少々辟易していた私は、解散への動きが意外に早く進んでいることに驚きました。
4時頃に講演が終わり質問タイムになると、会場から「いまスマホでニュースを見ましたが、首相が16日に解散すると言ったそうです」との声が。(こういう時代、講師も大変ですね)氏の予測通りになったことで会場は喝采。社に帰って選挙対策本部をすぐに立ち上げねば、と足早に会場を後にする岸井氏でありました。
夜になってTVで党首討論の様子を見ました。野田首相の迫力は凄かったですね。もう失うものはない、と腹を決めた人の強さでしょうか。攻めていた筈の安倍氏は、首相の解散宣言を聞いてしどろもどろ。それまで主張していた0増5減をこの場ですぐに受け入れられず、民主と自民だけで決めていいんですか、などとうろたえたのは、おぬし、役者じゃないな。締め括りに「覚悟のない自民党には政権は戻さない!」と首相に見得を切らせてしまいました。
しかし12月の選挙ですか…商売の上では、弱ったことをしてくれるな、と思います。選挙期間中はなかなか街に人が出ない、というのは経験上わかっています。当社のお客様にとって(そして私たちにも)暮れの一番大切な時、人々が浮足立つのは正直困りものです。でもまあいろいろな記事など読むと、政治的にはこのタイミングしかないらしいですね。どうしようもありません。
この解散宣言で民主党はガタガタになるでしょうが、もうとっくにガタガタになっているのですから、惨敗して傷は深くても、今よりわかりやすい政党にはなるんじゃないでしょうか。
政治に商売の足を引っ張られることはあっても、後押しをしてもらったことなど記憶にありません。決められない政治にそろそろ終止符を打ち、前へ進む体制ができることを望みます。
ピェンロー(扁炉)食べもの
20121111
秋も深まりつつ、鍋物の季節となりました。今日の夕飯は、久しぶりに食べる中国風白菜鍋。
料理雑誌dancyuを91年、ほぼ創刊の頃から毎号購読しています。この雑誌は飲食店情報とともに、名前の通り(男子厨房に入る)かなりのボリュームを割いて料理レシピを掲載していますが、いま発売の12月号では創刊以来の最強レシピを特集しています。その中で、最強中の最強と呼ばれるメニューがこの「ピェンロー」なのだそうです。
これは92年1月号で妹尾河童氏が紹介したメニューです。具は白菜、豚バラ肉、鶏肉、干し椎茸、ビーフン。ごま油。ダシは干し椎茸のだしオンリー。
味付けは、各自でするのです。自分のお椀に塩や一味を入れ、鍋から取った少量のダシで溶いて、これを「つけだれ」代わりに使います。
特に凝ったところも何もない(と思われる)この鍋のおいしいこと。結婚してからあまり作っておらず、ホントに十何年ぶりかで食べました。子供たちはたぶん初めて食べたと思いますが、それぞれおいしいうまいと言いながら、結構ボリュームのあったひと鍋、ほとんど食べてしまいました。
詳しい作り方は検索されるかdancyuを買って読むかしていただければよろしいでしょう。材料がシンプルすぎて、当社の食材の出番があまりないのが残念ですが。でもおいしい塩とごま油を使えば一層の味アップにつながるのは間違いないでしょうね。
無人駅?日々雑記
20121106
まさに青天の霹靂。困ったことになりました。
-----------------------------------
【日経新聞】東海旅客鉄道(JR東海)が長野県内の飯田線の有人駅9駅を来年4月から無人化する方針を明らかにした。飯田線の県内54駅(辰野駅除く)のうち有人駅を伊那市(伊那市)、飯田(飯田市)、天竜峡(同)の3駅のみに減らし効率化を図る。県南部の7市町が関係しており、リニア中央新幹線が通過予定の地元には波紋が広がっている。
-----------------------------------
当社地元の駒ヶ根駅も、今回の無人化の対象となっています。これからさらに観光を地域振興の目玉にしていこうと考える私たちにとっては、まさに冷水を浴びせられたようなニュースです。
記事によれば、駒ヶ根駅の一日当たり乗降客数は568人。平成元年と比べて6割減だということです。一日数十万人が利用する首都圏のターミナル駅とは比較するべくもありませんが、たとえば上諏訪駅など諏訪湖周辺の駅は概ね4000~3000人ほどですから、これらと比べてもかなり少ないことは確かです。(何故かJR東海には各駅の乗降客数を一覧で見られるサイトがないようで、飯田線の状況は私にはわかりません)
しかし、急行列車も走らず、通勤時間帯で30分に1本、日中は1時間に1本のダイヤでは、利用せいと言われても、どうしようもないではありませんか。
通勤通学客の利便性ももちろんありますが、中央アルプス登山の玄関口ともなっている駅が無人駅では、観光客へのサービス低下、イメージダウンは大きなものになってしまいます。オール単線の飯田線、上り下りの交換駅ともなっている駒ヶ根駅ですから、運行や乗降客誘導の安全性も心配です。
JR東海では、地元負担で委託による駅員を配備することは可能、としています。リニア新幹線の駅設置との交換条件というわけでもないでしょうが、リニア新駅と在来線の連絡、飯田線高速化を地域興しの柱に考えていた地元としては、まったくがっかりです。
駒ヶ根駅は現在有人駅であるにもかかわらず、NTTの電話帳に電話番号が載っていないことをご存知ですか?伊那市駅も飯田駅も、このへんの駅はどこも載っていません。何年も前のこと、急用でどうしても連絡を取りたかったときどう探しても番号が見つからず、途方に暮れたことがありました。困ってJR東海に聞いてみても「駅に電話はありません」との返事。そんな馬鹿なこと、信じられますか。
昔から鉄道駅というのは、地域の中心拠点として大きな役割を果たしてきたはずです。その公共性、責任を一方的に放棄されては、地域はたまりません。何とか知恵を出さねばならないですね。
関連リンク: 飯田線の長野県内有人駅を3つに(日経)
上座日々雑記
20121103
どなたがどこに着座するかが、日本の宴席ではとっても大事だといわれます。いや海外でだってきっとそうに違いないと思いますが。
会社の宴会では、社長ですので必ず上座に座らされます。仕事以外の会ではもちろん場面ごとそれぞれですが、どうだろう、年長の方とご一緒する機会が割と多い(俺ってまだまだ若いってことだよね)ように思うので、上座に座ることは少ないです。
年に一回開かれるある会合に先日出席しました。ここでは会の性質上、参加者の席次がすべてきちんと決まっております。といっても大したことではなく、シンプルに年代順ということです。欠席者が出て間が詰められることはありますが、追い越すことはありません。
この会は毎年同じお店の同じ部屋で行われます。仕切れば3つの小部屋に分かれるであろう細長い会場で、私が初めて出席したときはもちろん末席、3番目の間に張り出していました。この会場は畳に2箇所の敷居がありますが、一番奥に相当する席にたどりつくのはずいぶん先のことだと思っておりました。
ある年に敷居を一つまたいで上座に近づいたと思ったら、翌年には参加者が多くてまた元に戻った、なんてこともあり、冗談を言い合ったりしたものです。(この会は気心の良く知れた人の集まりで、べつにヒエラルキーをあからさまに押し出すような会ではありません)
ところが昨年は欠席される方が多くて、二つ目(高いほう)の敷居を初めて越えたと思ったらそれどころか、いきなり上から二番目の席となってしまいました。これはヤバい、うかうかしていると、なんて思っていましたが、今年はとうとう一番上座に座る羽目になってしまいました。いやこんなに早くここにたどり着いてしまうとは…
まあ上座に座ったからって乾杯の挨拶をするだけで、別に緊張するような会ではありませんがね。しかしそうはいっても、私が一番上に座っているようでは、会としてちょっと寂しい。先輩方にもっともっと出てきていただいて、幅広い会になるといいと思うのですが。ぜひもう一度敷居をまたいで戻り、次の間くらいに座りたいです。