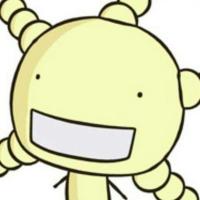台湾パイナップル食べもの
20210307
巷で話題の台湾パイナップル。きっかけは例によって中国です。
--------------------------
(産経新聞)台湾の農業委員会(農水省)は3日、今年の日本のパイナップル購買量が前年比約130%増の5000トンになるとの見通しを発表した。中国が台湾産パイナップル禁輸を先月発表して以降、台湾は輸出の多角化や台湾内消費の拡大を図ってきた。全体でも大幅増の見通しで、蔡英文総統は日本など各国や台湾人に謝意を表明した。
中国政府は2月26日、検疫で害虫を検出したことを理由に3月1日からの輸入停止を発表。習近平指導部は、嫌がらせによって蔡政権への反発が台湾で高まることを狙ったとみられるが、各国の台湾支持拡大や台湾人を団結させる「逆効果」となった可能性がある。
--------------------------
台湾パインの多くは国内消費で(パイナップルケーキの原料か?)輸出の9割が中国向けだったとのこと。今がちょうど収穫期にあたるパイン農家は非常に困るところでしたが、日本を含め各国からオファーが殺到し、蔡英文総統からも感謝のメッセージが出されています。
中国はその巨大なマーケットを利用して、自らの意に沿わない国への嫌がらせをたびたび行ってきました。数年前に作家で民主活動家の劉暁波氏にノーベル平和賞が授与されたことでノルウェーからのサーモンを禁輸し、昨年暮れからは香港問題や南シナ海での領有権で中国への反発姿勢を高めるオーストラリアのワインに懲罰的高関税をかけて事実上輸入をストップしています。両国にとって大きな打撃となりました。
日本と親しい国の窮状をこのような形で応援できるのは、嬉しいことです。中にはうがった見方をする人もいて、判官びいきを利用したマーケティングが大当たりしたのだ、という意見も目にします。まあ、そういう側面もなくはないのでしょうなあ。
それはそれ、貿易ですから互いにウィンウィンの関係を作れれば良し。店頭にももうすぐ並ぶのではないですか。丸のままのパイナップルを買って食べる習慣が日本でどれだけあるのかわかりませんが、台湾パインに接する機会は普段ありませんから、ぜひ味を見てみたいですよ。
大腸の宴食べもの
20210210
あまりにも直球なタイトルです。読者によっては、むしろ食欲を失わせてしまう可能性もあるかも?
先日スーパーの店頭で博多もつ鍋用のセット(調味料、モツ入り)を見つけました。以前食べた博多のもつ鍋を思い出して(→13.9.4)何だかとても食べたくなり買ってみたのです。
夕餉の食卓に出てきたものは、何じゃこれ?と首を何段階も傾げたくなるようなものでして、妻曰く「何でこんなもの買ったのよ、初めからわかってるじゃない」ですって。モツがほんのちょびっとしか入っていないし、あのプリプリした食感がまるでありません。スープの味も凡庸。
そこで思い出しました。2年前くらいの当社グランドフェアで出品した冷凍の牛の大腸。脂たっぷりで柔らかく美味しかった記憶があります。社員に聞いてみると、在庫があってちょこちょこと売れているようです。商品名は「アメリカ産牛大腸カット 500g」いわゆる、シマチョウの脂のついたやつ、です。
早速買って帰り、先日のリベンジをと妻に渡して、改めてもつ鍋をリクエストしました。できたものは写真の通り。比較参考のため一部はフライパンでチャッチャと焼いてみました。(手前)
こりゃうめーやー。プリプリの脂たっぷりで柔らかく、それなりに肉のうまみもあって、結構なボリュームがあります。しつこい脂ではないんですよね。。年のせいか牛肉の脂はたくさん食べられなくなってきたのですが、久しぶりだったせいか、どんどん食べられてしまう。焼いたものより鍋にしたほうが、いくらか脂が落ちてあっさり(こんな言葉で表現するようなものではない)ですか。
臓物臭さはゼロです。大腸の掃除は大変手間のかかるものだと聞きますが、アメリカの業者さんはどうやって加工(掃除)してるのでしょうかね。(追記、私の勘違いで、原料はアメリカ産ですが加工は九州の業者さんでした)
たいへん美味しいですが、この脂とカロリーは体に良さそうな気はしません。食べるときは節度を持っていただきましょうね。ご興味おありでしたら、お問い合わせください。
富山の回転寿司食べもの
20210123
私が回転寿司というものを初めて体験したのはかなり遅く、40歳に近くなってからです。JCの大会で富山に行き、現地をよく知る仲間に連れて行ってもらったもの。結構な行列でした。(書き出しが前回と同じじゃないですか)
何故それまで行かなかったのか、大した理由はないのですが、だいたい私は子供の頃からお刺身というものがあまり好きでなかった(今では大好きですよ!どうして昔は苦手だったのでしょう)ので、お寿司にも食指が動かなかったという、それだけのことです。
その時行ったのは「生け簀回転寿司・いき魚亭」という店で、いわゆるグルメ回転寿司という部類です。ネタには富山湾の幸がこれでもかと揃い、また店内の生け簀からすくい上げられた新鮮な魚介も供され、初めての「レーンを回るお寿司」の楽しさもあいまって(子供かね)心から満足しました。何でこれまで敬遠しておったのやら。
初めて訪れたのがこういう店だったというのは、私にとって幸いでした。(その後何度か行きましたが、何があったかこの店は次第に活力を失い、今は残念ながら閉店)今では100円寿司も好んで時々行きますが、折しも「秘密のケンミンSHOW」で富山の回転寿司を特集したのを観て、いろいろと思い出しました。
回転寿司のコンベアを開発した会社が石川県にあることから回転寿司のメッカは石川だとのイメージが強いです。いや違う、それは富山だ、と富山県民の俳優西村まさ彦氏が力説し、石川県民のダンディ坂野氏と張り合っておりました。
富山湾が数多くの魚種を誇る漁場だとは知っていましたが、日本海にいる800種のうち500種が生存する天然の生け簀だそうです。立山連峰から海に流れ込む豊富なプランクトンが魚の旨味を育てていることは言うまでもありません。
大看板であるブリに始まり、白海老、ぼたん海老やバイ貝、そして昆布締めという余所にはないコンテンツも色とりどりで、まったくお見事といっていいですね。
思い出したらまた富山に行きたくなりました。自由に動ける日が早く来ますように。
カルボナーラ食べもの
20210118
カルボナーラというものを初めて食べたのは、高校生の時。上京した折に銀座の不二家(だったかな)で体験しました。それまで「卵であえたスパゲッティ」を見たことがなく、たいへん美味しいと思いました。
食通で知られた映画評論家、荻昌弘氏のエッセイ「大人のままごと」にカルボナーラを作る話が出てきます。男3人が歓談している中「ハラ減ったな」と思ったならば…
一人はパスタをゆで、一人は玉ねぎを炒め、一人は卵をボウルに溶いて待機、パスタ係がアルデンテのタイミングを計ったらボウルに熱々のパスタと油の回った玉ねぎをぶち込み、じゃかじゃかとかき回せば思いついてから15分たたずに出来あがり、とありました。
これを読んだときは旨そうだと思いましたが、今見れば全然カルボナーラ本来のレシピではなく、それこそ「玉子とじ」ですね。名前の由来である黒胡椒のことなど書いてあったろうか。絶対欠かせないペコリーノチーズどころか、粉チーズも入っていません。まだ70年代、卵でとじたスパゲッティであれば即ちカルボナーラだった時代ですね。
今でもレストランで時々注文したり、市販のレトルトパスタソースを使ってみたりするのですが、どういうわけか美味しいものになかなか出会うことがありません。特にレトルトは、卵の加熱の関係もあり難しいのかな?
先日TVで「冷凍カルボナーラを食べ比べたランキング」なるものをやっていて偶然観たのです(いま調べると昨年11月の「サタデープラス」)。数十種を試食し、商品によってはかなり厳しいコメントが出されたりしていた中で、味の良さ№1に選ばれたのは
ヤヨイサンフーズ「Oliveto 生パスタ新カルボナーラ 260g」でした。
業務用の商品だというし、当社でも扱ってるのじゃないの?手帳に書き留めましたがそのまま失念しておりました。この前メーカーさんが来社したときに思い出して聞いてみたら、サンプルをお送りいただきました。(Kさん、ありがとうございます)
早速戴いてみますと…おお、こりゃ美味しい!卵とチーズの味も、もっちりした幅広麺の具合も、バッチリですよ。よく冷凍でここまでと妻と二人で感心しました。これはお勧めできます。レンジであっためるだけ。カノビアーノ、植竹シェフの監修だとのこと。
完熟の味食べもの
20210114
年末に、小ぶりで美味しそうなメロンを頂戴しました。箱に記載された食べ頃は、12月25日。でもせっかくだからお正月に食べようと、もう少し取っておくことにしました。こんな寒い時期ですからそう簡単に傷むこともないでしょう。
ところが、特に理由はないのについつい食べそびれ、三が日を過ぎてもずっと手付かずのままに。(理由はあります。飲酒しながら夕餉をしっかりいただいてしまうと、果物の入る胃のスペースがないため)
今日こそは食べよう、と言いながらいつの間にか松も取れ、成人の日も過ぎてしまいました。さすがに限界だろうと箱から出してみますと…
メロンの玉をつかむと、ぐにゃぐにゃに感じるほど柔らかく熟しています。ナイフで切るにもちょっと困るくらい。軽くつかんで絞るだけで、全部メロンジュースになってしまいそう。
これがですね、もう最高の味だったのですよ。表面の皮のギリギリまで、どこを食べてもじゅわじゅわと染み出すおつゆ。品よく甘くて爽やかで、甘露ってこういう時のための言葉なのかと思ったほどです。お皿に落ちた果汁までしっかりいただきました。
元のメロン自体がとてもいいものだったのでしょうけれど、よく言われる「腐る寸前が一番美味い」ということですかね。(本来は肉類に使う言葉ですが)もう一日置いたらアウトだったでしょう。これまでに食べたメロンの中では、比べようもなく最高の味だったと申し上げます。
真似をして、もしダメにしてしまっても、文句言わないでくださいね。
今年の一皿 2020食べもの
20201212
ぐるなび総研が主催している「今年の一皿」が先日発表されました。2014年に始まりまだ歴史は浅いですが「優れた日本の食文化を人々の共通遺産として記録に残し、保護・継承するためにその年の世相を反映し象徴する食」を選定しています。去年は「タピオカ」、一昨年は「鯖」でした。
外食受難の今年において食文化に名を遺すようなヒットは難しいと思っていたのですが、選ばれたのは「テイクアウトグルメ」でした。発表当日のTV欄を見ると、ニュース番組など軒並み「今年の一皿は?」と特集を組む気満々だったようですが、ちょいと拍子抜けしたのでは。
選定理由として以下が掲げられています。
----------------------
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、新たな収益源としてテイクアウトを開始する飲食店が急増した。ラーメンや高級料理、アルコール飲料など多種多様なメニューが増え、包材にも工夫が見られた。販売方法においても事前予約決済や店頭以外での購入など選択肢が広がり、テイクアウト市場が大きく進化した。
・生活様式が変化し在宅時間が増えるなかで、自宅でも手軽に飲食店の味を楽しめるテイクアウト需要が高まった。また外食の楽しさや飲食店の存在価値を再認識し、テイクアウトを通じて消費者が飲食店を支援する動きも見られた。
・今後も外食を楽しむ方法としてテイクアウト利用が継続し、新しい日本の食文化として定着する兆しがみられる。
----------------------
どうですかね。テイクアウトが外食の楽しさを再認識するきっかけになったとしたら、それはテイクアウトでは叶えられない、空間や人の交流の大切さだったのでは、という気もします。これがコロナ後も定着したとして「新しい日本の食文化」とまで言えるかどうか、ちょっと何とも言えません。
古くからあった「出前」の文化が廃れようとしていたときに、ウーバーイーツのようなフードデリバリーがそれにとって代わる存在になろうとしているのは興味深いですが、「テイクアウト」とは違いますよね。
選者の方々も「これが今年の一皿でいいの?」と迷ったのではないでしょうか。他にノミネートされたのは「シャインマスカット」「代替肉」「ノンアルコールドリンク」とのことです。私も前二者は候補かなあと思っていましたが、今年を代表する存在というには、ちょっと小粒です。
2020年がこういう年だったということを記憶に残すには、こういう選定も有り、ということですかね。ちょっと残念。
関連リンク: 今年の一皿 (ぐるなび)
豚の丸焼き食べもの
20201111
盗んだ豚を解体し、丸焼きBBQを楽しんだというベトナム人たちが続々と逮捕されています。自分たちで食べるだけでなく販売もしていたといいますから、結構な小遣い稼ぎにもなっていたのでしょう。
本欄は外国人犯罪やその背景について語るつもりはなく、食べものとしての「豚の丸焼き」の話。
豚の丸焼きはマンガの無人島ものなどによく出てきて、子どもの頃は夢のご馳走でした。丸太を組んで豚をしばり付け、下からたき火で焼くやつですよ。ここで「漂流教室」を思い出してはいけません。
当時は我が家の近所にあったとんかつ屋「きらく」さん(今は移転して、休日など大混雑の繁盛店になっています)のショーウィンドーに、仔豚とおぼしき豚丸焼きの食品サンプル、というか飾りが置いてありました。いつかこんなものをたらふく食べてみたいなあと思ったり、友達と語り合ったものです。
だいたいその頃は、鶏でも豚でも何でも「丸焼き」というものにあこがれていました。そういえば鯉の丸揚げ、というのもありましたなあ。最近見かけませんけど。
鶏や鯉はともかく豚の丸焼きは食べる機会がないまま大人になりましたが、長じてスペインを訪れ、記念すべき邂逅に恵まれました。マドリッドの「ボティン」というお店、超有名店なのでご存じの方もいらっしゃるでしょうが、ここの名物が「コッチニージョ・アサード」という仔豚の丸焼きなのです。
残念ながら丸のまま出てはこなくて、切り分けてあるのですが、薪窯で3時間かけて焼いたという仔豚は皮パリパリ、肉はしっとりと柔らかく、本当に美味しいものでした。長年にわたる念願を果たしました。丸焼きでなくとも似たようなものを食べて皮がすごく固いことがありますが、これをパリサクに焼くのが職人技というものでしょう。
ベトナムでは豚の丸焼きは、結婚式やパーティーの定番料理らしく、また街中の飲食店でも日常的に供されているようです。一頭まるまる食べるなら、何人前くらいになるのでしょうね。今回盗んだ豚はさぞかし旨かったのでしょうが、犯した罪はきちんと償ってもらわねばなりません。
まんじゅう可愛や食べもの
20201029
このおまんじゅう、ネットで話題です。山形県南陽市、家族経営の菓子店「六味庵」さんのお菓子ですって。
-------------------------
(同店のtwitterより)当店のかぼちゃまんじゅうは中の甘さ控えめかぼちゃ餡のカスタードのような柔らかさが売りなのですが、その柔らかさが災いして時々皮が破裂してしまうのです…
私「廃棄せず目をつけて売ってみては?」
専務「採用!!できました!!」
私「かわい〜(なんか一部ミーティみたいなのいる…)」
-------------------------
そのままだと売り物にならないと思われたまんじゅうに、黒ゴマで目をつけてみたらこんなふうになりました。可愛いと40個の失敗作がたちまち元の値段で売れてしまったそうです。
昔なつかし、パックマンみたいな顔ですね。いや「もやしもん」に出てくる細菌「オリゼー」の方がもっと似ています。栗の皮をこんなふうに割った笑い栗というのもありました。それで、ミーティって何ですか。
逆転の発想の勝利だとか言われているようですが、そんな大げさな話にしては却っていやらしい。ちょっとした“ひらめき”のおかげで廃棄寸前のまんじゅうを救出できたのは大変良かったです。
このお店が今後、顔まんじゅうを定番商品化するという話はまだ聞きませんが、これだけ話題になったのだからやってみればいいですよ。でもご主人(職人さん?)にしてみれば、失敗作を開き直って売ることに抵抗があるでしょうし、わざと皮の割れたものを作るのも難しいのかも。
ナイアガラ食べもの
20200930
ぶどうの季節です。といっても、今年はもう終わりに近いかな?この辺も産地ですから、方々でぶどう園の看板が賑やかです。
信州産高級ぶどうの代名詞は以前なら巨峰でしたが、一粒一粒皮をむいて食べるのは面倒でした。皮離れの良い、あるいは皮ごと食べられる品種、シャインマスカット、ナガノパープルやフジミノリなどに取って代わられているようです。最近はこの世界も新しい品種が目白押しで、追いつけません。
普及品のぶどうとしては、デラウエアとナイアガラが代表格でした。どちらも健在です。しかしながら、デラウエアの小ちゃな粒を一つ一つむしって口に入れるのは、今の私にはけっこう面倒ですね。年齢とともに気が短くなってきたのかな。
そこへいくとナイアガラは、皮離れが良く粒もほどほどのサイズで、いいと思います。昔から好きでした。高校卒業し東京へ出て、スーパーで見慣れた黄緑色のぶどうを買って食べてみると、皮が身とくっついて、むしゃむしゃ食べられないではありませんか。よく見ると「ネオマスカット」と書いてある。まったく似て非なるぶどうです。
ナイアガラは長野県はじめ寒冷地の特産品種で、皮が薄く保存がきかないため東京にはほとんど出ていなかったのです(たぶん今でも)。調べてみると生食するより、ジュースやワインの原料として使われることが多いとか。塩尻周辺ではナイアガラを使った甘口ワインがよく作られています。
果実はとても甘く、独特の芳香があります。皮と身の間のちょっぴりヌルヌルしたところがとても美味しい。
先日、妻がたくさん買ってきておいしくいただきました。高級ぶどうもそれは美味しいですが、ナイアガラは高貴な味とは言えないまでも、親しみやすく懐かしい味です。信州の秋を彩るのにふさわしい。遠方の方、機会があったらどうぞお試しください。
山賊焼食べもの
20200918
塩尻や松本のローカルグルメとして定着している山賊焼。今では我が家近所のスーパーでも惣菜売場で普通に見るようになりました。
私が山賊焼の存在を初めて知ったのは小学生のときです。学校の帰り道に「梨花」という古びた食堂があって、そのショーケースに骨付き鶏のサンプルが置かれ、山賊焼(サン ゾク ヤキ と振り仮名を振ってあった)というプライスカードが付いていました。値段がいくらだったかは覚えていません。
このサンプルはちょっと小さめでこれまた古びていましたが、骨付きのトリモモ焼が当時一番の大好物だった私にとって、誕生日のご馳走だったトリモモを食堂で食べられるんだ、いつか食べてみたいなと思いながら下校していました。当社のお得意様だった梨花さんは20年近く前に閉店し、ついに頂戴する機会はありませんでした。
山賊「焼」というものの、実際はニンニクや生姜を効かせ片栗粉をまぶした唐揚げです。名前の由来で、山賊は大切なモノやお金を「とりあげる=鶏揚げる」ことからだという説がありますが、かようなネーミングはちと信じがたい。塩尻の山賊というお店が始めたものだという説を私は採ります。
実はこれまで本場のものを食べたことがなく、塩尻の「正和食堂」というお店の山賊焼を前にTVで観て美味しそうだったものだから、近くで用事のあった折に土産にテイクアウトしてきました。予約していったのですが、フレンドリーな老夫婦がとても丁寧に歓待して下さり、恐縮してしまうほど。
持ち帰った品は写真の通り。巨大な一枚のモモ肉にムネ肉の塊までついていて(写真は2人前)一人前で人の顔くらいの大きさがあります。もう、デカさに圧倒されちゃって…
こんなのとても食べられそうもないと思いましたが、サクサク軽やかな衣とトリモモ肉のしっかりした味わいに、私も妻もみるみる完食し、お腹はいっぱいになりました。さすが評判の名店です。
地域に愛され育てられてきた立派なB級グルメだと思います。
関連リンク: 揚げ物なのに「山賊焼き」 長野の豪快鶏肉グルメ