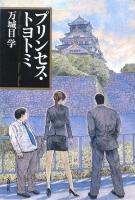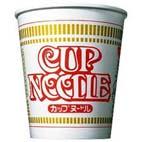代表に背負うもの…日々雑記
20110711
今日が新聞休刊日なのが残念ですね。女子サッカーワールドカップで優勝候補の地元ドイツと渡り合い、見事延長戦で勝ち抜いた「なでしこジャパン」の皆さん、おめでとう!。
日曜は朝早く目が覚めたのですが、テレビをつけたのは5時過ぎのこと。おお、何と!延長前半でまだ0-0ではありませんか。これは一大事。
延長後半開始早々、キャプテン澤の絶妙なパスを受けた丸山が持ち込み、ほとんど角度のない難しい所からゴールを決める。鮮やか!
この後試合終了までの長かったこと。頭一つ背の高いドイツの女戦士たちが猛然と襲いかかります。何度も何度もピンチを守り、相手のシュート精度の低さにも助けられ、ようやく笛が吹かれました。
過去0勝7敗1分と、差を見せ付けられていた世界の最強豪国を破り、4強にまで勝ち進んだのですから、歴史的勝利と言っていいでしょう。
この大会が始まるまで、女子の選手は澤しか知りませんでしたが、何試合か見ているうちにようやく何人かの顔と名前を覚えました。その中で(にわか)ファンになったのが左サイドバックの鮫島彩(さめしま あや)選手です。
ルックスも可愛いですが、それよりも、先月たまたま見たニュースの中で、彼女を見たから。彼女はこの春まで、福島を本拠地とする東京電力のチーム「TEPCOマリーゼ」に所属し、練習の合間には何と福島第一原発で事務をとっていたのだそうです。
震災後の事故で日本中から轟々たる非難を受け、今なお解決が見えない福島第一原発です。当然ながらサッカーどころではなくチームは活動停止。その中で日本代表として戦うこと、どんな気持ちだろうかと思います。
インタビューを受けながら、彼女は絶句し、泣いていました。今の状況で自分がサッカーを続けていいのか。おそらく地元でも、応援してくれる人ばかりではないでしょう。スポーツで被災者を元気づけたい、という簡単な話でもない。あらゆるものを彼女なりに背負って大会に臨んでいるのです。
試合では守備が主であまり目立つポジションではなく、プレーにはいささか危なっかしさも見えなくはないですが(同じ左SBでも、長友じゃないからね…何となく身のこなしとか、女の子っぽい感じがします)背番号15番、全力で、頑張って欲しいな!
(ドイツ戦でゴールを決めた丸山桂里奈も2009年までマリーゼでプレーしていた選手です)
気持ち悪い食べ物食べもの
20110708
何で昨日ピータンの記事を書いたかといいますと、ネットである記事を知ったからです。
何とCNNのまとめた「世界で一番気持ち悪い食べ物」に堂々選ばれてしまったというのです。
-----------------------
(レコードチャイナ)2011年6月29日、中国新聞社の報道によると、米ニュース専門放送局CNNのまとめた「世界で最も気色悪い食べ物」のランキングが発表された。1位には中華料理でポピュラーなピータンが選ばれた。
-----------------------
詳しくはCNNのリンクを見ていただくとして、その気色悪いランキングは
1位 Century eggs, China ピータンは「百年玉子」というんですね。
2位 Tamilok, Philippines マングローブの木の中にいるフナクイムシ。
3位 Fermented chips, Indonesia 大豆発酵食品「テンペ」のこと。
4位 Dog meat and offal, South Korea ご存知、犬の肉と臓物。
5位 Fried tarantula, Cambodia もう説明不要でしょう。
6位 Stir-fried cicadas, Thailand 蝉の唐揚げ。
7位 Fried frog, Philippines これも説明不要。写真をご覧下さい。
何と第1位から7位までアジア勢独占!ここまで欧米感覚丸出しの記事というのも、かえってすがすがしいというか、堂々たる開き直りというか、凄いですね。中国や韓国の方々は、さぞかし怒るでしょうなあ。
Bee worm, Nagano Japan とか、ランキング入りすれば、かえって宣伝になって良かったかも。
しかしこれ、2位から7位までと1位のピータンって、位置づけが全然違うんじゃないですか?ピータンは日常食であり、高級中華にだって平気で出てきますよ。これだけはこのランキング入り、腑に落ちません。
そこへいくと、韓国の犬食はごく一部で強精食として食べられているだけだと聞くし、カンボジアやタイの皆さんも果たして日常食として蜘蛛や蝉のフライを食べてるのかな?
自分たちがうまいうまいと食べているものを、他人にケチをつけられるのは愉快なことではありません。余計な御世話、です。しかしそうは言っても、食べ物として想像もつかないものを食べる異文化に触れることは、恐いもの見たさ、ってこともあり、面白いですよね。
昆虫をはじめとし、いわゆるゲテモノ食の宝庫、信州に住む私として、いずれあらためて一章を設けてみましょう。
関連リンク: CNN「世界で一番気持ち悪い食べ物」(英語)
ピータン食べもの
20110707
人によって好き嫌いの激しい食べ物。いろいろありますが、ピータンもその代表銘柄でしょう。
嫌だという理由は、まず一番には見た目のグロテスクさかな?中心まで真っ黒なネッチョリした卵なんて、知らなければやっぱり手が出ないかもしれません。二番目は、時として感じるアンモニアっぽいニオイでしょうか。
中華料理を食べると前菜盛りには殆ど入っていますが、箸をつけない方が必ずいますね。1人一切れ見当でしょうから、二つ目に手を伸ばしていいのか周囲の空気とタイミングを読まねばならず、何だか気を遣いますが、大体最後まで残っています。
当社でも扱っていますが、これ家で食べるとなると、結構面倒です。とにかく回りにびっしり付いた泥やモミガラを落とすのが大変。本当に堅くこびりついていますから。殻も固くて割りにくく、さらに切ってからしばらく置いておかないとアンモニア臭が抜けません。
でも時間をかけてようやく口に運ぶとき、状態さえ良ければ、顔がほころびます。ガリ(甘酢生姜)を添えるのが定番ですが、別に無くたっていいや。
そのまま食べるよりも、私はピータン豆腐にするのがいいですね。お店でメニューにあれば前は必ず頼みましたが、食べてみるとピータンをケチっていて(笑)がっかりすることもままありました。これは家で食べる方がおいしく食べられるかな。
水切りした豆腐に、ピータン、ザーサイ、長ネギ(+あれば、戻した干し海老)をみじん切りにして載せ、タレ(醤油、ごま油、紹興酒、砂糖)をかけてぐちゃぐちゃに混ぜて食べるだけ。私にだってできますからホントに簡単です。
面倒なのはピータンを剥くことだけです。ポイントはただ一つ、ピータンをケチらないこと!(といっても、豆腐一丁にピータン1個あれば十分ですよ)
日本料理の店で前菜に出てきたことがあります。ここではゴマくらいの大きさに刻んだピータンの黄身(いや黒身というべきか。しかしこんなこと、できますか?)と百合根を和えて、飴玉くらいの団子状に丸めてありました。すぐにそれとは分りませんでしたが、ねっとりした上品な美味しさが今でも忘れられません。
本場の高級店では黄身(黒身)がとろとろの半熟状になったものもあるそうです。雑誌で見てそれはそれはおいしそうで…以前中国旅行の際に「軟心皮蛋」というのを買ってみましたが、味は悪くなかったがイメージしていたものとはかなり違っていました。とろとろのピータンをぜひ食べてみたいな。
プリンセス・トヨトミ読んだり見たり
20110704
その日
大阪が
全停止した。
大げさな映画の宣伝に興味を惹かれましたので、映画ではなく万城目学の原作本の方を買ってみました。出張の行き帰りの車中でほぼ読了しました。
(ネタバレはありません)
これは、面白いですね。発想は奇想天外だ。小ワザが効いているといいましょうか、小気味良いパンチが次々に飛んでくる感じです。
大阪に何百年にもわたって伝えられてきた秘密。いや本当を言うと、金額から言っても指令実行の内容から言っても、それ自体はそんなに壮大な物語ではないのですが、その辺が大阪っぽいというか。(私、大阪にはそれほど馴染みがないもんですから、イメージだけで申しております)
登場人物たちも何となくマンガみたいではありますが、魅力的です。
途中から「父と息子」というテーマが表に出てきます。これには、やられました。私自身も数年前に父を送っており、一方で2人の息子の父親でもありますし。自分の体験と結びつけることなしには、読めません。
クライマックスのイベントが終わり、ここでお仕舞いにすればいいのに、という場面の後で、延々と伏線を回収するのはやや興醒めではありましたが…それはそれで面白い後日談ではあるのですが、もっとサラッとした結末にすれば、また読後感が変ったかも。
でも、なかなか、楽しめましたよ。
ところで何で映画化するとき、主要人物の性を簡単に変えたりするんですかね。旭役が原作のイメージで務まる女優は、なかなかいないかも知れませんが。(滝川クリステルは、女優じゃないし)
冷やしは癒ししごと
20110630
昨日(29日)は東京出張でした。いやあ…もう暑かったこと!伊那もかなりの暑さだったようですね。6月からこんなですから、本格的な夏が来たら、どうなってしまうのでしょう。特に電力削減対象地域でエアコンも遠慮しながら、という方々、本当に大変です。
この状況を見越して、食品業界では「冷やした食べ物」がいろいろと提案されています。展示会でもあちこちで見かけます。(本当は電力問題というよりも、昨年の猛暑を受けてのメニュー提案だと思いますが)
ただでさえ食欲の落ちる夏ですし、家庭の台所でもなるべく火を使いたくない中で、なかなかユニークなもの、おいしいものもありますよ。
既にワイドショーなどで話題となっているのは、冷たい「おでん」。物によってはゼリー状に固めたものもあります。これ見た目はとっても涼しげですが、「つゆ」はひんやりプルプルしていても「おでん種」がどうか暑苦しい食感のものが多く、微妙でしょうか。
冷たい「大学いも」。これはおいしいです。蜜の部分がパリっとしていて、食感も悪くない。もっさりした感じがややスッキリしたような感じ。
冷たい「麻婆豆腐」。冷奴に麻婆たれをかけた、ってことなのかな。試食しましたが、違和感は全然ありません。おいしくいただけます。
冷やして食べるパン用フィリングもいろいろ出ています。葛状のゼリーに粒アズキや宇治抹茶がからんだものだとか。これもとろみのある食感が心地よく、おいしいかった。
だいたい夏場はパンの売れない季節ですが、こうしたフィリングを使って「冷蔵庫で冷やして食べるパン」という提案が流行しそうな気がします。昨日帰りにサービスエリアで買ったリトルマーメイドのクリームパンも、お店のPOPを見て冷たくして食べたら、家族が喜んでいました。
山形には名物「冷やしラーメン」というものがあり、以前食べたことがあります。冷し中華ではなく、丼にスープがなみなみと注がれた普通のラーメン。そこに氷がプカプカ浮いており、スープも麺も冷たいのです。これは、食べたのが10月初めだったこともあって、いささか奇妙な感じでしたが…夏に食べたら、きっともっと旨かったでしょうけど。
ロングセラー (2)食べもの
20110629
この商品が40年を経てなお、カップ麺いや、インスタント麺の王者として君臨し、世界各国でこれまで290億食が食べられている。まったく凄いことですね。袋麺とカップ麺の販売量も逆転してしまいました。
現在コンビニの棚に並ぶカップ麺で、1年後にも生きている商品って、いくつあるんだろう?せいぜい一つか二つ、3年後ともなれば、ほとんどゼロでしょうね。一つの商品が生まれるまでに費やされた開発努力とコスト、包材など考えると、まったく勿体無いことです。まあ最初から、3ヶ月売れればいいと思ってるんだろ?みたいなものもありますけど。
私たちの業界では「大事に育てて売る」という言葉がありました。これはという手ごたえの商品は、一過性のブームに乗せて売るのではなく、街の小売店すみずみまで丁寧に販促活動を行って、じわじわと市場に浸透させていくような売り方です。
今ではそもそも「街の小売店」という言葉がほとんど死語みたいな時代ですし。メーカーさんが大型商品と銘打って大規模な販促をかければ、すべてのスーパーやコンビニに品物は一日で並びます。やりたければCMもバンバンかけられます。そうしてごく一部の例外を除き、何ヵ月後かには「パッと売れて、すぐ飽きられる」商品の山ができていくような気がします。
それも今の売り方ですから、否定するつもりはありません。でもその中で、キラリと光る数多くの商品が埋もれて消えていることも確かです。(とりわけカップラーメンは!私としては個人的好みから、明星食品の「究麺チャンポン」にはぜひ生き残ってもらいたいな)
歴史の流れに乗り世代を超えて愛されるロングセラーは誰もが狙っているでしょうが、実現することは難しい。製販の幸福な共同作業が実を結んだとき、それが生まれます。業界に身を置く者として、ぜひどこかで、そうした場に立ち会ってみたいものですね。
ロングセラー食べもの
20110628
今から40年前の1971年は、食品業界でいくつものロングセラー商品が誕生した年として知られています。。
カップヌードル(日清食品)
レディーボーデン(明治乳業~現在はロッテ)
小 枝 (森永製菓)
小欄の読者も、この3つはいずれも一度は口にされているのではないかと思います。
小学生だった私も、カップヌードルが初めて登場した時のことを覚えています。それは父が家に持って帰ったサンプル品でしたので、一般の方よりは遭遇が多少早かったのだと思いますが…今で言うカップヌードル、カレーヌードルと、そば、カップライスの4種類がありました。
今にして思うと、後の2つはまだ試作段階のものだったかも。
早速家族でそれぞれ少しずつ食べてみました。フリーズドライの見たこともないような小さな海老と、独特の食感の肉が大変印象的でした。(余談、今では「肉」はチャーシュータイプのものに変っていますが、前のミンチっぽい肉の方がいいという人は少なくないようです。私も同感)
カップライスは当時はちょっと…と思いましたが、後年改良されたものを食べたら別物のようにおいしくて驚きました。今でも食べてみたいなと思います。(地域限定で出ている「カップヌードルごはん」は長野県では売っておらず食べたことがないですが、たぶんまったく別物)
カップヌードルが当時最先端を行く食べ物だったことは言うまでもありません。お湯の出る自動販売機が設置されたり、あさま山荘事件で警察の人たちが食べて話題になったとか。他社から類似品(シュリンプヌードル、とか)がすぐ出ましたが、食べる機会がありませんでしたし、容器がいかにも安っぽかった。本家の堂々たる競争相手とは認知されていなかったのでは?
のちに「赤いきつね」や「カップスター」が出るまでは、カップヌードルがカップ麺のオンリーワン的存在だったのだろうという印象です。
続きます。
関連リンク: 日清カップヌードル
「日本一」に異議アリ食べもの
20110623
ソースカツ丼の日本一はどこか?
20日夜フジ系の「ほこ×たて」という番組で、二つの街が対決しました。何か肝心なものが抜けているようですが、野次馬気分で見ましたよ。
登場したのは福井市と会津若松市。福井はソースカツ丼発祥の地とも言われ、薄切りのカツだけをソースに浸してご飯に載せたカツ丼です。
いっぽう会津は厚切りのカツと千切キャベツの載った、私たちにはよく見慣れたカツ丼。
それぞれの街の一押し店を日本文化に詳しい?(と紹介された)3人の審査員が訪問し、どっちが日本一にふさわしいかジャッジをしました。結果は、2対1で福井の勝ち…
それが、何で「日本一」になるの?????
いやこんな番組に、真面目に文句をつけていると思われては癪ですがね。どうして日本一を争うのが福井と会津?どこかで予選会でもやったのかね。他にソースカツ丼の名所をお忘れではありませんか?
駒ヶ根の私としてはまったく憤懣やるかたないのですが、ふと思いついてグーグルで調べてみましたら、
「福井 ソースカツ丼」 277,000件ヒット
「会津 ソースカツ丼」 196,000件
「駒ヶ根 ソースかつ丼」142,000件 (駒ヶ根では公式には「かつ丼」表記です)
…駒ヶ根でこれだけPR活動に力を入れ、B1グランプリにも連続参加しているのですが、いま一歩福井や会津に遅れを取っているということかもしれません。「全国区でトップに認知」されるには、さらにたゆまぬ戦略と努力と工夫が必要ということですかね。駒ヶ根ソースかつ丼会の皆さん、頑張って!
この番組、時々見て面白いと思っていたのです。「どんなものでも絶対にくっつける接着剤」と「どんな力でも絶対にくっつけられない磁石」とか、「どんなシミでも絶対に落とすというクリーニングの達人」と「あらゆるクリーニングに出しても絶対に落ちないシミ」対決とか。技術者魂と誇りの激突。
でも料理対決ってこれまでの番組コンセプトとまるきり違うでしょ?これでは「どっちの料理ショー」ですよ。なにも矛盾してない。番組が始まってそんなにたっていませんが、もうネタが尽きたのかな。
デュヌ・ラルテお店紹介
20110621
東京へ行ったときに、情報収集を兼ねて家族に何かお土産…と、パンや菓子の評判のお店を回ってみたりしています。このパン屋さんはコンセプトがとてもユニークで、いつも刺激を感じるお店です。
何といってもまず、形の斬新さに惹かれます。
たとえば「ラルテ」と名づけられたクロワッサン。ほんとは三日月の形をしていてこそクロワッサンなのでしょうが。しかし単に面白さだけを狙ってこうした形にしたのではなく、バターと粉、特にバターのおいしさを追い求めた結果、この形にたどりついたのだとか。
キュブ(立方体)という2種類のブリオッシュ。一辺4.5cmのサイコロキャラメルみたいな面白い形ですが、その味のしっかりしていること。普通ではありえない「卵を使わないブリオッシュ」だそうです。その心は「卵は熱が入ると固まって、パサパサの食感を生む。卵を使わないほうが、ブリオッシュはしなやかさを増す」(料理通信誌より)
ノワ(胡桃)。胡桃の入ったパンは、胡桃に含まれる物質が作用して全体が紫色に染まりますが、こちらのは普通のパンの色。試行錯誤して特別な方法で胡桃を加工しているようです。ノワだけのものと、レーズン入りのもの、どちらもおいしい。
オリーブヴェルト。オリーブを混ぜ込んだスティック状のパン。これは塩気も効いており、ワインのおつまみ。
奇をてらったような形ですが、専門誌でその形(レシピ)に行き着いた思考過程など読むと、非常に面白いです。当然の事ながら、味がしっかりしていてこそです。パンはどれも小ぶりですし値段はまあ安いとはいえませんが、滅茶苦茶高いってわけでもないと思います。
最初の店がオープンしたときは、南青山のわかりにくい場所に店舗がありました。そのスタイリッシュなこと、高級ブティックみたいな真っ白なお店で、とてもパン屋さんとは見えませんでした。店舗の奥にバー(カフェではなくて!)も併設していたのですよ。最近新宿伊勢丹に店を出して、行きやすくなりました。
d'une rarete とは、たぐいまれな、という意味だそうです。
関連リンク: デュヌ・ラルテのホームページ
「春香」プレコンサート音楽ばなし
20110620
しゅんこう、と読みます。韓国に伝わる悲恋の物語「春香伝」を、作曲家高木東六が戦後間もない時期にオペラにしました。来年6月、伊那市でこの作品が10年ぶりに市民オペラとして上演されます。
その一年前イベントとして、オペラに参加するオーケストラ(伊那フィル)、合唱、舞踊のメンバーと2人の独唱者によるプレコンサートが行われ、私が指揮をしました。
(来年のオペラ本番はプロの方が指揮します)
「春香」プレコンサート
6月19日 長野県伊那文化会館
ロッシーニ:「セヴィリアの理髪師」序曲
シューマン:4つのホルンと管弦楽のためのコンツェルトシュトゥック
ドニゼッティ、團伊玖磨、ヴェルディ、ビゼーのアリア4曲
高木東六:「春香」より第1幕、第4幕のそれぞれ冒頭部分
ほか
指揮 春日俊也
独唱 奥村桂子s、藤森秀則br ピアノ 奥村夏樹
伊那フィル、春香合唱団、春香舞踊団
今回「オーケストラピット」の中で初めて演奏した伊那フィルです。指揮して感じたのは、歌が遠いこと。なかなか声も飛んでこないし、反応が見えづらい。向こうからも指揮があまり見えなかったようです。独唱との合わせは、リハの中でだんだん勝手が分ってきて、何とかうまくできたかな。
舞踊の人たちは、とてもカッコよかった。ずいぶん練習されたと聞きます。
オケは限られたスペースの中で、いつもと全く違う並び方をしましたが、こちらはあまり違和感を感じることなく演奏できたように思います。客席にはどんなふうに聴こえていたかわかりませんが…
言うまでもなく、普段から馴染みのあるような曲ではありません。スコア(指揮者用の総譜)は、広げれば新聞一面の大きさで厚さはタウンページ並み、中身はごちゃごちゃの(失礼)手書き、で読むのが大変でした。今回は合唱部分のさわり、十数分を演奏しただけでしたが、半年後には全4幕すべてを音にしていく練習が始まります。どんなことになりますやら。
前半のオケ単独ステージでは、私の大好きな「セヴィリア」と伊那フィルの大声軍団ホルンセクションを前面に出した「コンツェルトシュトゥック」を演奏しました。シュトゥックのホルンは難曲として知られますが、本番の集中力もありソロ、オケともに力をよく出せたと思います。
この日は中学生の次男を連れて行き打楽器の助っ人をさせました。彼のオケデビューです。日頃やっている吹奏楽とオケの演奏感覚の違い、難しさを味わったことと思います。
進行も含めて四方八方に気を配りながらのコンサートを仕切るのは、経験の浅い素人指揮者にはもう目が回るようでした。楽しんでいただけたでしょうか。
関連リンク: オペラ「春香」成功願う (長野日報)