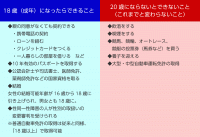大型連休始まるしごと
20220429
今日からゴールデンウィーク。人によっては10連休ということですから、羨ましい限りです。あいにくの雨模様でいささか出ばなをくじかれた感もありますが、TVニュースなどを見ていると、交通機関や高速道路などはそれなりの混雑だったようですね。
コロナが始まってから去年も一昨年も、まともな形の大型連休にはなっていませんでした。20.5.5の本欄で、人っ子ひとりいない高原やサービスエリアを見て落涙しそうになったことを書いています。ここで書いたことが、2年が過ぎてもほとんど改善されていないことに改めて驚きます。
…新型コロナよりも経済規制のもたらす被害の方が、見方によっては既に大きくなっているのではと思っています。医学の専門家だけで、国民全体に関わる重大な問題を決めていっていいのですか。無責任なメディアが煽る集団ヒステリーと無策な政治は、もうたくさんです。…
いまはウクライナと知床海難事故に話題が移っているだけで、コロナに対するメディアの論調ってどれだけ本質的に変わっているのでしょうか。GWを伝えるTVもふた言目には「人が動けば感染者が増えることが予想される」みたいなことばっかし。
まあそれでもね、過去を思えばはるかにマシな今年の連休です。当社にとってはこれでもコロナ前の売り上げ水準に比べれば遠く及ばないのですけど、2年たってようやくここまで来たと、ポジティブに捉えましょう。
皆様ぜひ、遠方の方は当地を訪れ、地元の人もまた地元の食を大いに楽しんでいただきたいと思いますよ。多くの方々が心から楽しめるゴールデンウィークになりますように。
滑ったのは誰のせい日々雑記
20220423
スーパーの床に落ちていた天ぷらを踏んで転んだのは誰のせい。客が店を訴えていたこの裁判、だいぶ前に記事を目にした覚えがありますが、おかしな判決で決着したのかと勘違いしていました。
-------------------------
(共同通信)スーパーのレジ前に落ちていた総菜の天ぷらを踏んで転び、けがをしたとして、客の男性(37)がスーパー大手サミット(東京)に約120万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷は、男性の上告を受理しない決定をした。請求を棄却した二審東京高裁判決が確定した。
男性は2018年4月、サミットストア練馬春日町店でカボチャの天ぷらに足を滑らせて転倒し、膝の靱帯を痛めた。
一審判決は店の責任を認めた一方、二審判決は「安全確認のため特段の措置を講じる法的義務があったとは認められない」とした。
-------------------------
妥当な判決だと思います。スーパーは客の安全に配慮する義務がありますが、それは無制限に求められるものではないでしょう。店の床に何か落ちていたらそれを拾うのは店員として当たり前でしょうが、天ぷら売り場の前ならまだしも、レジ前でこんなものを落とすことまで想定せよというのは無理です。一審判決を出した裁判官の見識を疑いたくなりますよ。
ですが、確かに滑りやすい床を何とかしてほしいと思う場面はあります。都会の立派な建造物のロビーやエントランスにある、鏡のようにツルツルに磨かれた石の床。これは怖い。雨の日にこんなところを通るのは、少なからず緊張を強いられます。この店も綺麗なツルツルの床だったのでしょう。
最近は屋外の床をざらざらした凹凸加工のものにして滑らなくしたところも増えてきて、そんな場所を歩くときは心底ほっとします。雪道も歩いている私の靴だって、滑るときは滑りますからね。
当社の玄関の上り口は、いちおうツルツルではありません。建てた当時はたぶんそんなことまで考えていなかったでしょう。良かったなあとは思いますが、それでも雪の日などは気を使っています。
Pink Moon日々雑記
20220416
今日はピンクムーンの日…だということです。PCを開いたら、出てきたトップページにそう書いてありました。ピンクムーンって何?
-------------------------
(ウェザーニュース)アメリカの先住民は季節を把握するために、各月に見られる満月に名前を、動物や植物、季節のイベントなど実に様々につけていました。農事暦(The Old Farmer's Almanac)によると、アメリカでは4月の満月を「ピンクムーン(Pink Moon/桃色月)」と呼ぶようです。
春の鮮やかなピンク色の花が咲く頃ということに由来するといわれ、実際に月がピンク色に見えるわけではありません。
-------------------------
実際に色がついているわけではないと言いますが、夕方の月を見ると、それでも何となくピンクっぽい雰囲気があるようにも見えましたよ。
唱歌「朧月夜」(詞:高野辰之)には、こうあります。
菜の花畠に 入り日薄れ
見わたす山の端 霞ふかし
春風そよふく 空を見れば
夕月かかりて におい淡し
古語で言う「にほひ」は、①つやのある美しさ ②色の美しく映えること とあります。「香り」の意味ももちろんあるものの、主には視覚的な意味で使われていたようです。この歌詞も、淡く色づく夕月の描写です。
菜の花や霞はありませんが、南アルプス仙丈ケ岳の山の端で淡くにほふ月、なかなか風流でしたよ。
完全試合日々雑記
20220411
日曜日のドえらい快挙。プロ野球ロッテの佐々木朗希選手が弱冠20歳にして一試合19奪三振(13連続三振)、そしてプロ野球で実に28年ぶりの完全試合を達成しました。
野球に詳しくない私だってこの偉業の価値くらいはわかります。午後ネットを見ていて「佐々木連続13奪三振」という見出しが目に入り、おお、凄いと思ったら、まだ試合が継続中で一人のランナーも出していないというではありませんか。
リアルタイムで中継を観たかったですが、ロッテ:オリックス戦のTV中継など長野県ではありません。本拠地の千葉テレビでも普段放送している中継がたまたまこの日はなかったそうで、観られなかったファンは憤懣やる方なかった由。
佐々木は日本人離れした長い手足を存分に使い、164㌔の速球に140㌔台のフォークなどを使ったピッチングでオリックス打線を翻弄しました。スポーツニュースで見て、あんな低めのボール球を何でみんな空振りするのかと思いましたが、野球好きの人によればあのスピードの球が落ちる(フォーク)なんて普通あり得ない、あれでは手が出てしまうよ、とのこと。
捕手として佐々木の能力を生かした松川虎生も絶賛されています。高卒ルーキーが守備の要であるキャッチャーを務めること自体が異例です。20歳と18歳の若いバッテリーが完全試合を達成したというのが胸のすく思いです。
プロ野球でノーヒットノーラン(無安打無得点試合)はそれほど珍しくはないですが、完全試合は本当に久しぶりでした。選手が記録を意識し始めると土壇場で失投や失策が出るのはありがちなこと。「あと一人」でパーフェクトを逃した悲運の投手は1950年の田宮謙次郎をはじめとして4人いるそうです。メジャーに行ったダルビッシュ有も、27人目の打者に股間を抜かれるヒットを浴び完全試合を逃しています。
佐々木は超大物と注目された大船渡高校時代、甲子園への出場を賭けた地区大会決勝で登板せずに敗れ、大きな話題となっています。連投で肩を酷使した結果、将来性ある選手が“燃え尽きてしまった”ことはこれまでもありました。目先の勝利にこだわらず教え子の将来を優先した大船渡の国保監督、さすがだなあと思います。
日本を代表する投手としてますます活躍してほしい。これから彼の登板試合、中継もあるでしょうか?
カムカムエヴリバディ読んだり見たり
20220409
昨日完結した「カムカムエヴリバディ」。久し振りに朝ドラを半年間通して観て、緻密に作られたドラマを満喫しました。
実は番組開始のときは全然ノーチェックだったのですが、脚本が「ちりとてちん」の藤本有紀だと知ってあわてて観始めました。最初の2週間ほどを見逃したのは残念至極なり。
100年、三代にわたる家族の歩みを描いたドラマです。忙しい内容ですっ飛ばし感もなくはなかったですが、3人の主人公がリレーする異例の構成で「安子→るい→ひなた」の場面転換がスムースに流れ、さすがだなあと思いました。
3人の人生に共通して大きく関わった「ラジオの英語会話」と「あんこ」。どちらも一朝一夕には成果を出せない難物でしたが、継続は力なり、努力の嫌いだったひなたがこれほど英語ペラペラになるどころか、英語番組の講師にまでなるとは誰が思ったでしょうか。受験英語しかやってない私も、今から毎日ラジオで勉強すれば10年くらいで外国人とも普通にお話しできますかね。
主役3人は素晴らしく、そして彼らを支える俳優たちも(まあ)良かった。るい(深津絵里)が母親の告白をラジオで聴く、5分間台詞なし表情アップの演技には日本中の視聴者が身じろぎできずに引き込まれたのでは。
親子や孫を同じ人が演じるのは映画「愛と哀しみのボレロ」みたいでいささか混乱しましたが、登場人物の多い連続ドラマの場合、結果的にはむしろ分かりやすかったともいえましょう。そしてオダギリジョーのこういう役柄は、とても新鮮でした。
藤本有紀は伏線の名人ですが、本作ではちょっと期待しすぎだったかな。最終回でいろいろ大忙しでまとめたのは、お遊びの範疇かと思いました。後半で英語の台詞が増え(日本語字幕)画面に集中せざるを得なかったのは、時計代わりの朝ドラとしては結構な冒険だったと思います(視聴率ってどうだったんだろう)。もともとこの人のドラマは「ながら観」を許さないところがあります。観るのに集中を要しますが、それに見合うものは得られるはず。
NHK、藤本氏にもっともっと活躍の場をあげてほしいです。半年間、しっかり楽しめました。
ボッコちゃん読んだり見たり
20220407
星新一の伝説的ショート・ショート。先日TVドラマでやっていたので、懐かしく思い出し読み返してみました。いま読んでも古くないですね。
父の本棚に「さまざまな迷路」があったのを小学生の頃に読んだのが最初かな。かつては中学生や高校生にも相当な人気でした。一話がせいぜい数ページですから誰でも簡単に読めたってこともあるでしょう。いまどきの中高生は、ほとんど知らんでしょうな。
しかし中身は、それぞれ珠玉の完成度です。星新一は創作に関して「アイデアを出すのはすさまじい苦しみ、テストの答案を毎日書いているようなもの。しかもテストはいよいよとなれば白紙で出すこともできるが、ショートショート作家は締め切りを逃げるわけにはいかない。しかも毎回完璧な答案を求められる」と因果な境遇であることを告白しています。
ボッコちゃんは「人造美人」なる短編集に収められ、これも父の本棚にありました。これほどの名作、多くの方はもうご存知だと思うので、以下ネタバレしますよ。
-----------------------
あるバーのマスターが作った精巧な美人型ロボット、ボッコちゃん。簡単な受け答えと酒を飲むことしかできないが、バーカウンターに置かれたボッコちゃんは客の人気を集めていた。誰もロボットだとは気が付かなかった。ボッコちゃんに熱を上げていた若い客が、暖簾に腕押しの状況に思いつめ、彼女を毒薬で殺そうとするが…
マスターが考案した「提供した酒を再利用するシステム」が仇となり、このせこいアイデアのためとんでもない結末を迎えます。客がボッコちゃんに飲ませた酒はこっそり回収され、再び客に提供されていたのです。
これは子供心にも変だと思いました。だってボッコちゃんはいろんな種類の酒を飲むでしょう。ウィスキーもブランデーもビールも、みんな混ざっちゃうじゃないですか。そんな謎のカクテル?を客に出せませんよ。
ドラマでは、酒の種類別に複数の回収容器があるように描写されていましたが、どうやって分けるんだ?口の中にセンサーでもついていて、体内で酒の行き先を分岐していたのでしょうか。
ドラマの結末は若い客が良心の呵責に耐えかね店に戻ってきましたが、原作の方が味わいがありました。ラジオの「おやすみなさい」に応えて自分も「おやすみなさい」を言い、いつまでもツンとした顔で座っているボッコちゃんが不気味です。
成人年齢18歳に日々雑記
20220401
今日から新年度です。しばらく前から言われていた成人年齢が今日から引き下げられ、18歳から「成人」として扱われるようになりました。
成人になると何が変わるのか。できること、できないことの表があったので掲げておきました。
私の感覚では、20歳になったらできることで真っ先に思い浮かぶのは選挙でしたが、2016年に公職選挙法が改正されて18歳から選挙権が与えられるように既になっております。若い人が投票に行くのは大事なことですよ、皆さんの投票率が高くなれば、政党だって若い人の生活や将来にもっと配慮した政策を考えるようになるでしょう。
あと、酒とタバコ。私の頃は建前は20歳からであっても、高校卒業したらまあOKという社会での暗黙の了解がありました。だんだん頑なにこだわる風潮になってきましたが、18歳になれば別にいいと思うのですがね。高校での生徒指導が困るというなら、学校ごとに校則で厳しく規制するようにするしかない(大変だとは思うが)。これを20歳のままにしておくのは、大人が子供たちの行動を管理しやすいというだけではないでしょうか。
(18歳からOKだったのは、パチンコと成人映画がありましたな。私も人並みに待ちわびておりましたが、体験してみればまあ、こんなものかなというところ)
女性の結婚年齢が16歳から18歳に引き上げられると。これは知らなかったなあ。この件で男女に年齢差をつけること自体、明治以前の感覚であったのかとも思います。
各種の契約を保護者の同意なくしてできるようになるというのは、親元を離れてアパートを借りるとか携帯電話を契約するとかが例に上がっています。親との関係は人さまざまでしょうから、これまで切実な問題だったケースもたくさんあったのでしょうね。
論議が絶えない「少年法」の扱い。何故かこの表には出ていませんが、少年法も同時に改正され、18歳以上は大人と同じような裁判を受けたり実名報道が有りになったりします。成人なんだもの、権利だけでなく責任も負うことを自覚してもらわなくちゃね。