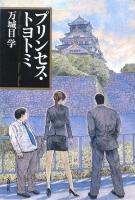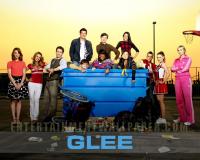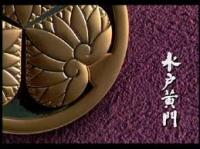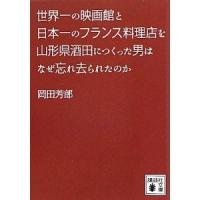切腹読んだり見たり
20110818
ある方から、旧作日本映画のDVDを何枚も戴きました。これはその中から、盆休み中に観た1本。実は少し前に新聞記事でこの映画のことを読み、ぜひ観てみたいと思っていたのです。
若い食い詰め浪人が武家屋敷の門をたたきます。「生活に困窮し、生き恥をさらすよりいっそ切腹して果てたい。ついてはこちらの御屋敷の庭先をお借りしたい」頼まれた方は迷惑至極、いくばくかの金を払って追い返そうとする。実は初めからさらさら切腹する気なぞなく、こうした小金目当ての「たかり」が流行っていたのです。
舞台となる井伊家では、懲らしめ・見せしめのために浪人の申し出を承諾し、本当に切腹させようとする。青ざめる浪人。武士に二言はなく、後に退くことはできません。
用意された刀は何と自分の差してきた竹光。既に困窮のため刀は売り払っていたのです。切れるはずのない竹光で強引に腹を切ろうとする浪人。何度も何度も試み、血みどろになった末に舌を噛み切って絶命する。正視しがたい凄まじい場面です。
数ヵ月後、別の浪人が井伊家を訪れます…
復讐譚の中に、体面を最優先する武家社会への痛烈な批判が込められます。場面は終始屋敷の中と回想シーンだけなのですが、とても目が離せないほどの濃密な迫力が伝わってきます。浪人・仲代達矢、家老・三國連太郎の鬼気迫る演技。緊張感あふれるカメラと舞台。邦楽器を使った武満徹の音楽。お見事というほかありません。
えらいものを観せてもらいました。いま、こういう映画は作れるんだろうか。というか、興業として成り立つんですかね。(HARAKIRIと題して、カンヌ映画祭で特別賞を受賞しています)
SFの巨人読んだり見たり
20110729
作家の小松左京氏が亡くなりました。享年80歳。
多くの作品がありますが「日本沈没」「復活の日」「さよならジュピター」あといくつかの短編しか読んでいません。ほんの一部にしか接していないで大したことは言えませんが、私の読書体験に大きな思い出を残してくれた人です。
代表作「日本沈没」が出版されたのは1973年のこと。たちまち大評判となり、空前のベストセラーとなりました。小学6年生だった私は、夏休みに父が買って家にあったこの本を読み、その大胆な構想、精緻な考証、ぐいぐいと押してくる筆力に感嘆し、只ならぬ興奮を覚えました。背伸びをして大人の本を読んでみる楽しさ、優越感(誰によ?)みたいなものを感じていたのかも知れません。
小説ってのは、これほど面白いものか…。プレート移動理論、日本沈没を引き起こすメカニズムについての記述はいささか手に余りましたが、幾度となく引き起こされる大災害の描写に戦慄し、主人公の活躍に胸を躍らせ、政府首脳や学者たちの苦悩からは、まだろくに知らない政治や社会の構造に何だか近づいたような気もしました。
何度も何度も読み返し、大体の台詞も頭に入ってしまいました。傍点を多用した独特の文体も気に入り、中学校だったと思いますが国語の時間に「これまで読んだ本の文章で気に入った部分を書き出せ」という課題が出たときに、何ページもこの本から引用をしました。先生はきっと呆れたことでしょう。
上下巻あわせて385万部が売れたそうです。当時は高度成長期が一段落したところへオイルショックや狂乱物価などが世間を騒がせ、これもベストセラーになった「ノストラダムスの大予言」などと共に終末ブームをつくった時代背景がありました。
映画化されたのはもちろんですが、当時ラジオドラマにもなったのをご存知ですか?わくわくして聴きましたが、我が家は電波状況がとても悪く(今もです)雑音だらけで、最初の数回を聴いただけで諦めました。
巻末には「第一部 完」と書かれ、第二部では沈没後の日本人の流亡記が書かれるはずでしたが、待ちこがれた続編はいつまでたっても世に出ることはありませんでした。もうとっくに忘れた頃、06年に谷甲州氏との共著として出版された「日本沈没 第二部」は、残念ながら大きく期待を裏切るもので、この本は自分の中では「なかったこと」にしたいと思っています。
その他に印象的だったのは…
「影が重なる時」という短編がありました。日常生活の中に突然現れた、硬直した分身。彼らは何故現れたのか?ぞくっとするような結末が待っています。
「復活の日」は、先に映画を観たのですが、後から原作を読んでこっちの方がずっと面白いと思いました。やはりこうした滅亡パニックものは、上手いですね。
日本のSFを代表する作家としてだけではなく、その構想力を万博などさまざまなプロジェクトに生かして大活躍された著者でした。ご冥福をお祈りします。
プリンセス・トヨトミ読んだり見たり
20110704
その日
大阪が
全停止した。
大げさな映画の宣伝に興味を惹かれましたので、映画ではなく万城目学の原作本の方を買ってみました。出張の行き帰りの車中でほぼ読了しました。
(ネタバレはありません)
これは、面白いですね。発想は奇想天外だ。小ワザが効いているといいましょうか、小気味良いパンチが次々に飛んでくる感じです。
大阪に何百年にもわたって伝えられてきた秘密。いや本当を言うと、金額から言っても指令実行の内容から言っても、それ自体はそんなに壮大な物語ではないのですが、その辺が大阪っぽいというか。(私、大阪にはそれほど馴染みがないもんですから、イメージだけで申しております)
登場人物たちも何となくマンガみたいではありますが、魅力的です。
途中から「父と息子」というテーマが表に出てきます。これには、やられました。私自身も数年前に父を送っており、一方で2人の息子の父親でもありますし。自分の体験と結びつけることなしには、読めません。
クライマックスのイベントが終わり、ここでお仕舞いにすればいいのに、という場面の後で、延々と伏線を回収するのはやや興醒めではありましたが…それはそれで面白い後日談ではあるのですが、もっとサラッとした結末にすれば、また読後感が変ったかも。
でも、なかなか、楽しめましたよ。
ところで何で映画化するとき、主要人物の性を簡単に変えたりするんですかね。旭役が原作のイメージで務まる女優は、なかなかいないかも知れませんが。(滝川クリステルは、女優じゃないし)
glee読んだり見たり
20110613
学園青春ドラマから遠ざかって久しいのですが、現在NHK(BSプレミアム)で放送中のgleeには、いい年をしたオジサンがはまっています。。
全米で大ヒットしたハイスクールドラマで、既に日本のCSでも一度放送されて人気を集めたようです。既に2ndシーズンも別の局でやっているらしいですが、私がいま見ているのは1stのほうです。
glee(合唱部)は学校中からダサいとさげすまれるどん底のサークルで廃部寸前。そのメンバーだというだけで皆から仲間はずれにされたり、カップ入りのジュースを顔にぶっかけられたりするのですから、たまりません。学生時代には花形だったglee顧問のウィル先生は、当時地区優勝歴を持つ実力者。彼は何とかgleeを復活させようとメンバーを集め、奮闘するが…
いわゆる「グリークラブ」的な堂々たる合唱団ではなく、ポピュラー曲を歌って踊る「コーラスグループ」をイメージしてもらえばいいと思います。
何といっても最も魅力的なのは、歌です。毎回毎回素敵なナンバーが満載。この分野にまるで疎い私でさえも、イイと思いますよ。ポップスもラップもオールデイズもミュージカルナンバーも、何でもござれ。そして登場人物が皆、歌のうまいこと!あの国のこと、もちろん役者が自分で歌ってるんでしょうなあ。
次には、多くの登場人物の個性がきちっと出来ている。誰もが輝き、一方で誰もが危うい。微妙なバランスを大変うまく作りあげていると思います。ゲイ、黒人、ユダヤ人、障害者といったマイノリティをこれでもかとばかり主役級にちりばめ、それぞれに説得力のある役割を持たせています。
そして、めまぐるしく動くストーリーのスピーディーな展開がすごい。よく考えると実際の日時はそう経っているわけではないのですが、これだけぎっしりとエピソードを詰め込んでもちゃんと話が進行していきますから、目が離せないのです。高校生にあるまじきwブラックな話題や下ネタもどんどん出てきます。
私は(ゲイの)カート君のファンです。女性の登場人物には今のところ、やな女が多いですね。主役のレイチェルもホントに自分勝手だし、夫がgleeにのめりこむのを快く思わないウィルの妻とか、妊娠騒ぎ(実は他の男との子)でBFを振り回す美人チアリーダーのクインとか。
でも、gleeを目の敵にして絶えず妨害をする宿敵、チアリーダー部顧問のスー先生(写真右端)でさえも、最近では思わぬ一面を見せたりして…いまにこの人も歌いだすのではないかと、楽しみにしています。
1stシーズンは現在半分くらい終わったわけですが、今からでも間に合うと思いますよ。
関連リンク: glee (NHKの公式ホームページ)
英国王のスピーチ読んだり見たり
20110503
ゴールデンウィーク真っ最中。前半戦は雨にたたられましたが、今日からの後半戦は今のところ何とかお天気も保っています。県外車も目立ちます。
ロイヤルウェディングでイギリス王室がホットな注目を集めています。ちょうどタイミングよく、話題の映画を少し前に観てきました。アカデミー作品賞をはじめ、7部門を受賞しています。
(ネタバレあります)
幼い頃から吃音と極度のあがり性に悩む英国王子ヨーク公。いろいろな治療を試したがうまくいかず、妻の勧めで、ある言語療法の専門家にお忍びで指導を仰ぐ。最初は彼の型破りな治療に当惑するが、だんだん2人の間に心が通い合い、吃音は少しずつ回復していく。
一旦は王位に就いた兄が、離婚歴のある女性との交際で退位することになり(世に言う「王冠を賭けた恋」事件)ヨーク公は国王ジョージ6世として即位する。その頃欧州はナチスの台頭に脅かされていたが、ついにドイツ軍が侵攻し、第二次大戦が勃発した。王は開戦にあたって国民を鼓舞し、心を一つにするため、絶対に失敗の許されないスピーチに臨むこととなる。
いかにも英国風に、信頼、友情、責任という堅いテーマを品格とユーモアあふれる映画に作り上げています。
よく言われますが、イギリスの王室ってのはフランクですね!こうした内容の映画が日本で撮られるかといえば、もちろん考えられません。国民との距離が本当に近いと思います。ダイアナ妃の例を引くまでもなく、それが良いことばかりでないのはもちろんですが。
さて前評判が大変高かったので大いに期待して観ましたが、俳優たちの演技がそれぞれ素晴しかったと思うのですよ。(ハリーポッターの魔女ヘレナ・ボナム・カーターが、こんなに魅力的な人だとは知らなかった!)しかし、脚本が、いまひとつかな。
この映画のクライマックスは、戴冠式でのスピーチに持ってくるべきだったのでは。ここを肩透かしのようにすっ飛ばして、開戦のスピーチまで引っ張ったのは、どうよと思いました。結婚式の中継でも見られた戴冠式の式場の荘厳さ、素晴しさが俯瞰で見事に撮られていたのに、もったいないな。
ちなみに実際のジョージ6世の戴冠式には、作曲家ウィリアム・ウォルトンが名曲「クラウン・インペリアル」を献呈しています。私が打楽器を始めたときに演奏した思い出深い曲で、これは全く私の我儘にすぎませんが、ちょっとでも聴かせてほしかったね。結婚式では終了後、主役たちが教会を出てパレードに向かう場面で演奏されていました。
そして重々しい開戦のスピーチに重ねられた音楽は、なんとベートーヴェン交響曲第7番の第2楽章。曲調はそれは良いでしょうが、敵国ドイツの曲をここで採用したのは、この曲にドイツの軍靴の響きを重ねたってわけですか?(映画でこんな重要な場面に流れる曲を無頓着に選曲する筈がないもの)それは…ベートーヴェンの音楽に失礼というものでは。
短時間でバタバタと慌しい中でのスピーチ…確かに緊張感あふれ、歴史的にはもちろん重要な出来事ではあっても、物語の組み立てとしては物足りなさを覚えました。
最後の場面での誇らしい笑顔で、国王の務めを見事に果たした堂々たる風格を見せていましたが、調べてみると、王は吃音を完全に克服できたわけではなく、晩年には大事なスピーチを全うできなかったりしたこともあるようです。
ご承知の通り、彼はいまのエリザベス女王の実父です。56歳という若さで亡くなったのは、もともとあまり丈夫でなかったところへ兄から突然王位を渡され、重責に心身ともに疲弊したこともあるのでしょう。誠実で責任感の強いひとだったそうですが、映画でも彼の人間性はうかがい知ることができます。
期待が大きかっただけにちょっと残念でした。繰り返しますが、出演者の演技は見ごたえがあり満足していますので、決してつまらない映画というわけではないですが。
黄門さま伊那へ来る読んだり見たり
20110301
2月は本当にあっという間ですね…今日から3月。
春 だ !
さて昨夜のTVは8時から水戸黄門ご一行が当地を訪れるということで、地元の家電屋さんの社長が特別出演するとか、前宣伝が賑わしく行われておりました。この番組を1時間通して観るなんて、本当に何年ぶりかな?(ひょっとすると平成になってから初めてかも)
木曽と伊那とをつなぐ権兵衛峠。今ではトンネルが開通し、当社から木曽への商売の基幹ルートにもなっていますが、数年前までは国道361号でありながら冬季には通行止めとなる、細い山道でした。その道を苦難の末切り開いた木曽の権兵衛さん(実在)が前田吟。その娘に佐藤藍子。
ドラマはその権兵衛峠の開通から始まります。意外とあっけなく、感動無く開通してしまったな~。参勤交代行列の到来で急に大量の米が必要になった権兵衛は、娘と共に峠を越え、伊那へやってきて米を木曽へ運ぶ算段をします。
伊那節に歌われる(木曽へ木曽へとつけ出す米は~)ように、伊那の米は権兵衛峠を通って木曽に運ばれました。木曽と伊那の物流ルートを開拓した権兵衛の功績は、正しく偉大だったのです。
無事に手配できたと思ったのも束の間、大事な米は「荒船の雷造」なるやくざ者に買い占められてしまいます。(伊那の勘太郎じゃないのか。もっともご当地ドラマで勘太郎をただのチンピラ悪人には描けませんね)
そこには、権兵衛の娘に邪恋を抱く高遠の米問屋(六平直政)の企みがありました…
例によって8時43分には黄門さまが悪だくみを暴き、娘はかねてから意中の若者と晴れて一緒に、と、おきまりコースをドラマは進んでまいります。
久しぶりに見ましたが、結構笑えますなこれは。花嫁略奪の場面なんておお「卒業」だ、と思う間もなく、折角逃げた2人がのこのこ式場へ戻るって、何でよ?黄門様を現場で迎えるためとしか思えない。セットの安さもなかなか可笑しかった。
黄門さまは私にとっては、やっぱり東野栄治郎です。里見浩太朗が老け作りをしているのは、どうも嘘くさい。そういえば今回は、最後の立ち回り(助さん格さん、懲らしめてやりなさい)がありませんでしたが、毎週やっているわけではないのかな?
悪口を書きましたが、それでもご当地ものは面白いですね。実際伊那のどこかでロケが行われたようには、あまり見えませんでしたけど。
関連リンク: 権兵衛峠 (個人の方のページです)
ハリー・ポッター読んだり見たり
20101206
子供のお供で映画館へ。。
学生時代は結構映画館に通ったのですが、最近はご無沙汰です。3月に子供たちと「アバター」を観に行って以来ですね。大人の映画はしばらく観ていないな。
映画館で映画を観るのは、やはりテレビで観るのとは全然違う充実感があります(たとえカットやCMがなかったとしても)。大画面ゆえに発揮される構図の妙、暗闇の効果、音響の迫力、そして観客の一体感がもたらす劇場全体の空気。
最後の一体感は、個人的になかなか楽しみなのです。コンサートなどでも感じます。残念ながら地元の映画館は大抵ガラガラ(失礼!)なので、この感覚を味わえません。
さてハリーポッター、原作も読んでおらず、前作までの話を全く忘れて行くので、観るたびに良くわからないまま映画が終わってしまいます。物語を構成している世界をいまひとつ把握できていませんし、主要登場人物なのに「この人、いい人なの?悪い人なの?」と判然としないこともあります。さすがに主人公3人組と闇の帝王くらいは分ってますけど。
もっとも話のボリューム自体がかなりあるでしょうから、どうしても筋を追うことが主になり、細かい味わいみたいなものは期待できませんね。私の理解力不足だけでなく、映画自体の説明不足もあるに違いない。
今回作「死の秘宝part1」はこの大長編物語を締めくくる「前半部分」ということで、あれこれと出てきた素材がまるで解決することなく、映画が終わってしまいます。「つづく…」とテロップが出ないのが不思議なくらい。ああ早く最終話が公開にならないかなあ、と映画会社の思う壺にはまっている私。
夢追い人読んだり見たり
20101202
丸谷才一が「裏日本随一のフランス料理」と呼び、開高健や山口瞳が絶賛したレストラン「ル・ポットフー」の名声は、以前に本で知りました。
これはその店をつくった人、佐藤久一の夢と波乱に満ちた生涯を書いた、長い長いタイトルの伝記です。
世界一の映画館と日本一のフランス料理店を山形県酒田につくった男はなぜ忘れ去られたのか
(岡田芳郎著 講談社文庫)
「世界一の映画館」グリーン・ハウス。
佐藤久一は裕福な日本酒の蔵元に生まれ、酒田の名士だった父が買い取って経営していた映画館の支配人を、二十歳の若さで任されます。娯楽に飢えた戦後の日本人が、争って映画館に通った時代。久一はあふれんばかりのアイデアで、グリーン・ハウスを理想の映画館へと作り上げていきます。
映画といえば活劇中心だった中、ここで上映される映画は質の高い文芸作品を多く取り入れ、すべて久一の眼に適った名作揃い。回転ドアの入口を通ると、グレーのスーツ、蝶ネクタイに白手袋で正装した案内人がにこやかに迎えてくれる。
塵一つなく磨かれたロビーや舞台には、季節の花鉢が隙間なく並べられ、高性能の映写機・音響設備と座り心地の良い椅子、清潔で豪奢なトイレを備えた映画館は、女性客がおしゃれをして出かける社交場になるほど。しかも料金はあくまで廉価。淀川長治や荻昌弘もグリーンハウスに魅了され、東京から何度となく足を伸ばして通ったそうです。
「日本一のフランス料理店」ル・ポットフー。
こんな田舎で高級フランス料理を食べる客がいるだろうか?という心配をよそに開いたレストランでした。ガサエビ、ハタハタ、岩牡蠣、数々の山菜、山形牛、鴨などの庄内の豊富な海の幸、山の幸。これらをふんだんに盛り込んだ、東京では絶対に食べられないフランス料理。調理はポール・ボキューズ仕込みの若き名人。そして魅力的なマダム。
久一は食材探しと料理の向上に情熱を注ぎながら、支配人としてホールに立ち、その洗練されたサービスでお客を魅了していきました。店内をいくつかの空間に分け、高級料理をリッチな客層に提供するだけでなく、小さな子供連れの親子にも本格的な食の楽しみを伝えようと笑顔を絶やさず、幅広い多くの人々に愛されるレストラン。名声を伝え聞いた人が遠方から通いつめる店を、久一は作りました。
自分の思いのすべてをかけて作った二つの施設でしたが、映画館は昭和51年、1700棟余りを消失した酒田大火の火元となってしまいます。そしてレストランは、採算を度外視した食材やサービス、それに比べてあまりにも安い価格設定から膨大な借金を作り、ついにオーナーから追放されることに…
凄い人だと思います。これはもうある種の芸術家といってもいいのでしょう。久一にとっては、映画館もレストランも自分の思い描いた理想を具現化したものだったのですから。そのすべてはお客の満足に捧げられました。
それだけのものを提供して、何故店の経営を回していけなかったのか。これほどの心のこもったサービスを安売りせざるを得なかった、地方都市の限界なのでしょうか。最初のうちは、別フロアでの披露宴などでそれなりに稼げていたようですから、こうした道楽のような店もありだったのでしょうが、時代の変化が彼のような存在を許しませんでした。
経営を忘れ、お金を稼ぐことを二の次にしてきたツケは大きなものでしたが、彼が本当に「忘れ去られた」のだとは思いたくありません。佐藤久一という名前を知らない人が増えても、彼が酒田に投じた文化の小石は、大きく広がって人々の心に浸みていったに違いない。
映画館は勿論もうありませんが、ル・ポットフーは当時の流れを汲む人たちによって今もしっかりと続いているそうです。いつか、訪れる機会を持ちたいものです。
関連リンク: 酒田 ル・ポットフー
地獄の厨房読んだり見たり
20101012
地デジが来たけどロクな番組がない、と以前書きましたが、最近になってようやく、ちょっと面白い番組を発見。といっても、番組が作られたのは2005年だそうですが。
BS-11で月曜夜11時から放送されている「ヘルズ・キッチン~地獄の厨房」なる番組。まだ途中の2回しか見ていないのですがね。
主人公は世界的に有名なシェフ、ゴードン・ラムゼイ氏。ロンドンに三ツ星レストランを持ち、日本でも5年前汐留のホテルに名を冠したレストランが作られています。彼の元へ将来のシェフ志望の若手10人くらい(だったのでしょうか…始まったときは)が集まり、苛烈なシゴキに耐えて料理修業をする。しかし毎回1人ずつが脱落し(追放され)最後まで残るのはいったい誰?というエンターテインメント。
このラムゼイ氏が、まあ厳しいこと。若手の作った料理を味見して「こんな変な味の料理を食ったのは初めてだ!犬にでも食わせた方がいい」とか、もう罵倒の嵐なのですよ。
若手は赤と青の2チームに分かれ、実際にお客を入れたレストランで料理を競います。その日の課題に敗れたチームは、仲間の中から追放候補2名を選び、そのうち1人をラムゼイ自身が決定し脱落者が決まります。
このシステムは以前放送されていた番組「サバイバー」にそっくりです。一致団結して危機を乗り越えようとしながら、裏ではライバルを追い落とすための謀略が渦巻く。もともとアメリカの大人気番組ですが、日本では翻案がいかにも中途半端で、あっという間に打ち切りになりました。
「地獄の厨房」ではそれほどドロドロしてはいません。それよりもラムゼイの叱咤とキレっぷりが凄くて、謀略なんぞ練っている余裕はとてもなさそうです。
ディナーのコースを、すべてのテーブルに時間内にきちんとサービスする、という当たり前のようなことが、なかなかできないのです。他の皿がすべてオンタイムで完成しても、最後の一皿が2分間遅れたために、ラムゼイの指示で全部作り直し(冷めた料理を客に出すつもりか!この馬鹿野郎!)。しびれを切らしたお客は怒って次々に帰ってしまう。
それでも彼らが少しずつ成長していく様子もわかります。番組のテンポが早く、ラムゼイの鬼教師ぶり、また誰が残るかのサスペンスもあり、小気味良いです。(日本のバラエティ番組って何でこうつまらないんだろう…スタジオの雛壇芸人なんてホントにいらないと思いませんか)
昨日放送の時点で7人の挑戦者が残っています。最後まで生き残ると、どんな特典や賞金があるのか分りませんが、面白く見ています。
八朔の雪読んだり見たり
20100731
八朔(はっさく)とは、8月1日のこと。花街では芸妓や舞妓が、お茶屋さんや芸事の師匠にお礼の挨拶に回るしきたりがあるそうです。
もう明日から8月ですね。最近読んだ本の紹介です。
高田郁「八朔の雪」 みをつくし料理帖 時代小説文庫
主人公・澪は、故郷の大坂で少女の頃に水害で両親を失いますが、老舗料理屋の女将に拾われ、その天性の味覚を買われて料理修業に励んできました。
故あって江戸へ出た澪は、神田のそば屋「つる家」で店を任されます。旧友との思い出やライバル店の妨害、温かく見守ってくれる周囲の中で成長していく澪の物語を、おいしそうな数々の料理とともに描きます。
人情話で、うーん泣けますねえ…あまりにストレートな話の運びで、特に奥深いとかいう訳ではないのですが、私こういうのには弱いんです。出てくる人が、もうみんないい人でいい人で。(このことは、はっきり言って小説の奥行きをなくしているとも思いますが)
作者は、映像をずいぶん意識しているのでしょうね。漫画原作者でもあるそうですし。そのままNHKの30分時代劇のシナリオになりそうな。(一話60頁ほどの連作小説なのです)
澪は「上方と江戸」の食の違いにたびたび悩みます。味付けのことはもちろんですが、そればかりではなく、それぞれの食習慣や、江戸っ子気質といったものまで含まれ、試作して「絶対これはいける!」と売り出した自信の一品がまったく受けず、困惑することもしばしばです。逆に、江戸ではほとんど食べられていない上方の名物が大ヒットすることもあります。
何といっても出てくる料理がどれもおいしそう!ほっこりとした湯気まで想像してしまいます。
本書は昨年いくつかの賞を受賞し、ちょっとしたベストセラーになっているらしく、すでに続編「花散らしの雨」「想い雲」が出ています。
タイトル「八朔の雪」…8月に雪とはこれいかに。読んでのお楽しみとしておきましょう。