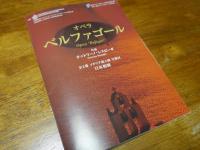銅鑼いろいろ音楽ばなし
20181119
楽器シリーズ。銅鑼のこと、もう少し書いてみましょう。
アジアを中心に、様々な種類の銅鑼があります。タイなど東南アジアの民族音楽に見られるGong(ゴング)というやつは、中心に「おへそ」のような出っ張りがあるのが特徴。定まった音程を持つ大小のゴングを何個か組み合わせて使うことは、現代音楽では珍しくありません。
オーケストラでよく使われるのは、中国系のTam-tam(タムタム)という、平べったいもの。悲愴で使われるのもこちらです。深い響きと驚くほど長い余韻(たぶん1分位は鳴っています)を持ちます。
なんと私も、1枚所有しています。個人で銅鑼なぞ持っているアマチュアは少ないと思いますが、これは昔、妹が中国留学していた時に生産地の武漢へわざわざ行ってもらい、購入し送ってもらったものです。自分で包装して送るのがホントに大変だったと言っておりました。
楽器代が約1万円、送料に同じくらいかかったそうです。当時日本の楽器店で購入すれば、本体で10万くらいはしたでしょう。直径32インチのちょっと小ぶりのものですが、なかなか良い音がして、昔も今もいろんな機会に重宝しています。
銅鑼の活躍する曲といえば…活躍と言っていいかちょっと難しいですけど、悲愴はまあ、筆頭に挙げられるでしょうね。マーラーはすべての交響曲に銅鑼のパートを書いていて、第2番「復活」など、大小2枚の銅鑼を交互に叩かせたりもしています。ストラヴィンスキー「春の祭典」では、トライアングルのバチを使ってこする指示があり、ギーッという強烈な金属音を聞かせます。
これまでやった中で一番しびれたのは、ウェーベルン「管弦楽のための6つの小品」という曲。現代音楽への道を開いた名曲ですが、滅多に演奏されません。この曲の第4楽章は、♩=46という恐ろしくゆっくりなテンポの曲で、銅鑼と低音の鐘が聞こえないくらい静かに静かに、冒頭からいつ終わるともなく何十回も鳴り続けるのです。
当時入手したばかりのMy銅鑼でこの曲をやりました。銅鑼は同じ音を続けて出すことが大変難しい。あれだけの質量のある金属をとても重いバチで鳴らす。しかも前の音が響いているうちに同じ力で次の音を叩けば、楽器の振動が増幅してたちまち大きな音になってしまいます。一発でもやらかしたらアウト、極めて微妙なコントロールが必要なのです。息が詰まるような沈黙で満たされたサントリーホールに、銅鑼の響きがさざ波のように次々と吸い込まれていく。すごい経験でした。
私の知る限り世界最大の銅鑼は、東京高円寺、楽器レンタル業の「プロフェッショナル・パーカッション」の入口に鎮座しています。普通のトラックでは運べないでしょうし実際に使われることはほとんどないそうですが、前回使われたのは、プッチーニのオペラ「トゥーランドット」の、オーケストラではなく舞台装置としてだそうです。(主人公が誓いを立てた証しに、大音響で3発鳴らす場面があります)
悲愴の銅鑼音楽ばなし
20181118
少し台湾から離れて、音楽の話など。。
先週の日曜日、伊那フィルの年一回の定期公演がありました。曲はシューベルト「未完成」とチャイコフスキー「悲愴」という、どちらもロ短調の暗めのプログラム。私は未完成のティンパニと、悲愴ではシンバルと銅鑼(どら)を演奏しました。
未完成はまあいいとして、悲愴ではシンバルが4発、銅鑼が1発しか出番がありません。50分近い曲でこの音符の数はいくら何でも少ないのですが、一つひとつは実に存在感を持った音として書かれていて、少ない労力で最大の効果、のお手本のような曲です。だから、やり甲斐はありますね。
来場した人たちのアンケートでも「シンバルが恰好良かった」というものが3通、そして思いがけないことには「ドラが恰好良かった」も2通ありました。いや皆さん、お目が高い!普段アンケートで打楽器のことなぞ、あまり書いてもらえないのですよ。
さて悲愴の銅鑼の効果的な使い方は、多くの打楽器奏者たちを強く惹きつけています。第3楽章の嵐のような行進曲が終わり、第4楽章で切々と歌われる悲しみ。その慟哭がクライマックスに達し、徐々に力が抜けていく場面で鳴るたった一発の銅鑼は、死の予告、絶望を思わせる実に印象的な暗い音なのです。
楽譜にはP(ピアノ、弱く)と書かれています。といって、決してか細い音ではなく、深く遠い闇の奥底から響いてくるような音。今回直径40インチの大型の銅鑼を前日から借用して使いましたが、慣れない楽器で思い通りの音を一発勝負で鳴らすのは、演奏者としてはかなり緊張するところです。叩いてしまったらもう修正できませんし。
元在京オーケストラの打楽器奏者(故人)のインタビューにありましたよ。「人生の終わりには、悲愴の銅鑼を本番で叩いて、そのままステージで息絶えることができれば本望」ですって。もちろん本気でおっしゃっていたわけではないでしょうが、そのくらい思いの深い一発であることをぜひ察していただければ。
ドイツ・レクイエム音楽ばなし
20180605
今回伊那フィルでチャレンジするのは、ブラームスの大曲。合唱との共演です。
レクイエム=鎮魂曲。モーツァルト、ベルリオーズ、ヴェルディ、フォーレ(これ、前に振ったことあります)ら錚々たる作曲家が名作を残しています。曲名から想像される通り、死者の魂を慰め永遠の安息を願う曲ですから、まあ明るい曲想にはなりにくいですね。
しかしこの「ドイツ・レクイエム」は抹香くさいばかりの曲ではありません。死者を悼むよりも、苦悩から希望、喜びと慰め、復活と救いといった生者へのメッセージがあふれ、変化に富んでいて聴きやすいのではないかと思います。もちろん鬱々とした部分もありますけど。第3曲、第6曲の最後を飾る華麗なフーガはヘンデルの「メサイア」を思い起こさせます。
恥を忍んで白状すると、取り組む事が決まるまで、私自身この名曲を聴いたことがありませんでした。何ともったいないことだったでしょうか。
オケの練習を始めたのは去年の12月ですが、合唱団はそれより一年も前から取り組み始めています。アマチュア合唱団にとっては、ベ-トーヴェンの「第九」よりもはるかに難しい大曲ですからね。どちらも1時間10分ほどの演奏時間ですが、第九は合唱の出番は全体の1/4位なのにドイツレクイエムは全曲通して歌いっぱなしですから、エネルギーの配分も大事です。
オケと合唱の合同練習、初回と2回目を振る機会がありました。初回は信毎さんが取材に来て記事を書いてくれましたが、これを読んだ人は、本番も私が振るものと勘違いするのじゃないでしょうか。取り上げてくれるのは嬉しいですが、名前を呼び捨てにされるのは微妙な気分ですね。ちなみに記事のどこにも「敬称略」って書いてないですぞW。
もう1曲、バレエ「コッペリア」を舞踊団と一緒に演奏します。下の写真は5/27、初合わせ練習の様子。コッペリアにドイツレクイエムとは、まことに不思議なカップリングで戸惑う方もいらっしゃるでしょうが、私も戸惑っています。どちらも素敵な舞台になるよう、本番がんばりますよ!私、コッペリアは小太鼓、レクイエムはティンパニでの参加です。お越しいただければ幸いです。
第1回クラシック音楽の祭典
6月10日(日)14:00開演 長野県伊那文化会館
ドリーブ「コッペリア」より
ブラームス「ドイツ・レクイエム」
横山 奏 指揮、牧野元美(S)、井口 達(Br)
トライアングル (2)音楽ばなし
20171109
かようにポピュラーな楽器ですから、オーケストラではもちろん頻繁に使われます。トライアングルの名曲といったら、まずリストの「ピアノ協奏曲第1番」。第3楽章でピアノと掛け合いをするようなパートがあり、この楽器を初めてソロとして使った例だと言われます。初演の時には、使いすぎだとして「トライアングル協奏曲」とまで(皮肉で)言われたくらい。
グリーグ「ペール・ギュント」の中の「アニトラの踊り」は弦楽器とトライアングルだけで演奏されます。弦による静かなダンスをトライアングルがひそやかに彩る、印象深い曲です。
ワーグナーの「マイスタージンガー」前奏曲と、ブラームスの「ハイドンの主題による変奏曲」。どちらも曲が始まってからずっとお休みですが、曲のクライマックスが近くなったところでおもむろに登場します。トライアングルの一打でオーケストラの色がガラッと変わる、この小さな楽器の大きな存在感を見せている用例と思います。
そして何と言ってもスメタナの「モルダウ」。この曲を今回やるのです。楽器はエーベルを使う予定。
2本のフルートで始まる小さな流れがだんだん集まり、いつしか一つの川となって流れ始める冒頭から、深く澄んだトライアングルが響きわたります。楽譜には「エレガントに」「鐘(Glocken)のように」と指示されています。
出番も多く、森の中の狩り・村の婚礼・月光の中で踊る妖精・そして大河となって雄大に流れてゆくモルダウ川のさまざまな場面で性格の違う表現が求められていて、大変やりがいのある曲になっています。演奏するのがとても楽しみです。お聴きになるときはぜひ、この可憐な楽器にも耳を傾けていただきたいなと思います。
☆☆伊那フィルハーモニー交響楽団 第30回定期演奏会☆☆
11月12日(日)午後2時開演 駒ヶ根市文化会館
(ホームグラウンドの伊那文化会館が改修工事のため使えず、今年は駒ヶ根開催です)
スメタナ:交響詩「わが祖国」より モルダウ(トライアングルやります)
ビゼー :「アルルの女」組曲より(出番は僅かですが、大太鼓やります)
ブラームス:交響曲第2番ニ長調(ティンパニやります)
ぜひお越しください!(もうあまり日がありませんが)
トライアングル (1)音楽ばなし
20171108
どなたでもご存知、幼稚園児にもお馴染みの楽器。叩けば誰でも音が出ますから、私たち打楽器奏者がいろんな方から「打楽器なんて簡単でしょ」と素朴な感想を言われるとき、相手の方の脳裏にはきっとトライアングルかお遊戯のタンバリン、お猿のシンバルの玩具あたりが浮かんでいるに違いありません。
今週末、伊那フィルの定期公演で久しぶりにトライアングルをたくさん叩くことになりました。少しばかりこの楽器への思い入れや豆知識などを書いてみようと思います。
実際には、なかなか奥の深い楽器であることは言うまでもありません。難しいリズムを打つテクニックというよりも、「よい音」の追求に心を砕きます。楽器の構造がシンプルなので、楽器自体の良し悪しも大きく影響します。
写真は私がずっと前から使っている米国製「アラン・エーベル」という楽器で、名門フィラデルフィア管弦楽団の打楽器奏者エーベル氏が作ったものです。独特の形で知られ、日本での愛用者も結構いらっしゃると思います。別にもう1本、ドイツ製「studio49」の大きなサイズのものも持っており、こちらは素晴らしく倍音豊かなリッチな音の楽器です。エーベルもとても美しい音ですが、スタジオ49と比べるとシンプルで素直な音で、曲によって使い分けています。
私は知る由もありませんが、昔の楽器にはそれは素晴らしい響きを持つものがあったそうで、それは素材の鉄そのものの違いだそうです。昔の鉄は今よりもずっと多くの不純物を含んでおり、それが豊かな倍音の基になっていたのだとか。外国で、築100年を超えるような鉄筋建築を解体する話があると、現場へ駆けつけて手頃な鉄棒を拾い、上手に曲げて楽器にしたなんて話を聞いたことがあります。ホントかな?
バチ(トライアングルのバチはビーターといいます)は10本組のセットを揃えて使い分けています。総じて太めのものを使うことが多いですね。そうそう、楽器を吊るす紐も大事で、私は太目の釣り用テグスを使ったりしますが、本当はガット(羊腸)を使ったハープの弦の切れ端を使うのがいいとか。ナイロンは振動を吸収してしまうが、ガットは固いのでむしろ振動を妨げないと言われます。
良い楽器は、ビーターが楽器に当たる位置や角度で驚くほど音が違うのです。1本の楽器がこんなに多彩な音を生み出すことができる…これも技術のうち、というか、これこそが技術ですね。楽器は音楽のための素材ですから、いかにその場に合った音を選び抜いて提供できるかが打楽器奏者の命です。
王滝村へ (4)音楽ばなし
20170630
ファミリーコンサートも、いよいよ終盤です。。
1~3、これは伊那フィルならではの大サービスだと思いますが、休憩時間に「楽器体験コーナー」を行っています。私たちの命より大事な楽器を子供たちに触らせてあげる、まことに勇気ある(学校の教頭先生が終わりの挨拶で言っていました)企画です。
こうしたコンサートでは毎回やっており、行った学校によって子供たちの反応がいろいろですが、王滝の子たちは積極的でどんどん入ってきていました。こうした体験が心に残って、将来オーケストラをやりたい!なんて思ってもらえるといいですね。
4、子供たちと。結局、配置を変えて子供たちを前に出し、歌声がよく聞こえるようにしました。はるか彼方にいるオケは指揮がよく見えず、やりづらかったことでしょうが、音優先ということで。
私が1曲、王滝の音楽の先生が1曲、そして中学生の女の子(ヴァイオリンを習っているそうな)は校歌を指揮し、最後アンコールに定番「ふるさと」を私の指揮で会場の皆さんと一緒に歌ってお開きとなりました。
5、楽器と会場を片付け、トラック(みんなはバス)に乗って伊那に帰ります…
ファミリーコンサートはどこで開いても、子供たちの反応がストレートでいいです。こちらの予想通りノッてくれると「やったね!」という気持ちになります。
王滝は人口800人に満たない過疎の村で、村議会を廃止して直接民主制をとることさえ考えられ始めているようです。地震の被害が少なくて良かったと今にして思います。豊かな自然の中でのびのび育つ子供たちと一緒に過ごした、実に気持ちの良い一日でした。
王滝村へ (3)音楽ばなし
20170626
地震はお二人の軽傷者が出て、余震もあるものの、大きな被害がなかったようでひと安心です。コンサートの一日、続きです。
1、リハが終わって昼食タイム。腹が減っては演奏できぬ。お弁当は、ふだんの定期演奏会などでもそうですが、各自調達です。私は以前はコンサートの前には殆ど食べないようにしていた時期もありましたが、今は普通に(やや軽く)食べています。
2、時間があったので校内をちょっと見せてもらいました。木曽は林業の地ですから、多くの学校で校舎に木材をふんだんに使っています。これは正面玄関に鎮座する校歌のモニュメントで、巨大な一枚板でできています。この校歌は信州が生んだ作曲家で数多くの管弦楽曲も残している、小山清茂氏の作曲によるもの。
3、生徒玄関にも木がたくさん。
4、本日のプログラム。第一部は伊那フィル単独、第二部は小中学校児童生徒の単独ステージ。第三部は特別ゲストの地元声楽家、村上和歌子さんとの共演、そして子供たちとの共演。
5、本番が始まりました。客席は、子供たちも含めて100人くらいかな。音楽教室には必須の「オーケストラの楽器紹介」もやりました。写真は地元木曽から長駆参加しているメンバーK君が、ヴァイオリンの紹介をしているところ。K君の使っている楽器は、木曽にゆかりのあるヴァイオリン製作者、陳 昌鉉氏の手によるものだそうです。東洋のストラディバリとも称される人だそうで、お恥ずかしいが今まで知りませんでした。
6、村上和歌子さんと。木曽で子育てをしながら二期会に参加し本格的な演奏活動もしている方で、これまで何度か伊那フィルと共演しています。美声で、表現も素晴らしいです。
王滝村へ (2)音楽ばなし
20170625
ついつい忙しくて、ブログの続きを更新できていませんでした。今日は王滝コンサートの続きを書こうと思っていた日曜朝、その王滝で「震度5強」の速報。地震発生から2時間ほどたった今のところ、停電・断水・落石などはあるものの大きな被害が出ている情報はありませんが、大丈夫でしょうか?
1984年9月に起こった「長野県西部地震」は王滝村直下を震源とする震度6の地震で、地震による直接の被害というよりも前日までの雨で地盤が緩んでいたために大規模な土石流が起き、死者行方不明29人という惨事になりました。
梅雨入りしたとはいうものの最近は大した雨も降っていませんでしたから、そちらの心配はあまりないようにも思えますが。
また様子を見て記事の続きを書きましょう。なお駒ヶ根では、大した揺れはありませんでした(震度2)。
王滝村へ (1)音楽ばなし
20170619
伊那フィルでは何年かおきに、小学校などを訪れてファミリーコンサート(音楽教室)を催しています。。今年はいつも練習の拠点となっている地元の「富県小学校」、そしてちょっと足を伸ばして、木曽の「王滝小中学校」(子供の人数が少ないため小中が一緒になっている学校です)で二度の演奏会を行いました。
2003年にも王滝でコンサートを行ったことがあるのです。当時私は伊那フィルを休団中で参加していませんが、とても心温まる歓迎をしていただいたとの話は聞いています。
王滝村での一日を追ってみたいと思います。
1~2、王滝には駒ヶ根からクルマで約1時間半かけて行きます。私は楽器のトラックに同乗。学校のすぐ近くまで山で囲まれています。写真2の里山のすぐ向こうに、2014年に噴火した御嶽山がありますが、学校からは見えません。
3、9:00学校到着。数人の先発隊が既に椅子を並べてくれています。楽器を降ろし、セッティングをしているうちに他のメンバーもチラホラと集合していきます。本体のバスが着いたのは9:30頃。(写真3)
4、軽く音出ししたあと、10:00からリハーサルを始めます。コンサートマスターが中心になってチューニング(音合わせ)をしているところ。
5、リハーサル。時間がたっぷりあるわけではないので、確認程度です。
6、学校の子供たちの歌と一緒のリハーサル。王滝小中学校は全校生徒・児童37人です。「翼をください」、嵐の「ふるさと」、校歌などを共演しました。ちょっと子供たち、緊張しているのか声が出てこない。朝ごはん食べてきたか~?と聞いたりしてなごませようとしますが、元気ないですね。どうしよう。
続きます。
レスピーギのオペラ音楽ばなし
20170208
「ローマ三部作」でお馴染みのイタリア人作曲家、レスピーギ。彼のオペラ「ベルファゴール」の日本初演があり、わが音楽の師匠、時任康文氏が棒を振るというので、ちょうど東京に別の用事もあり、観に行ってきました。(2月5日「東京オペラ・プロデュース」の公演、新国立劇場)
レスピーギにオペラがあるなんて、初耳だという方も多いと思います。私も聞いたことがありません。全2幕に加えて長めのプロローグとエピローグを持ち、上演時間2時間以上の堂々たるオペラですよ。
悪魔ベルファゴールが娘を見初め、人間に姿を変えて父親をカネでたぶらかし、無理やり結婚を承諾させる。娘には船乗りの恋人がいるが、航海中で不在。泣く泣く結婚はしたもの、娘はベルファゴールとベッドを共にするのを拒否し続ける。帰ってきた船乗りは娘に事情を訊き、受け入れ難く娘の貞操を疑う。挙式の誓いの際に祝鐘が鳴らなかったことを知って船乗りは納得し喜び、悪魔の油断に乗じて駆け落ちし、結ばれる…
ベルファゴールはなかなかいい男で、娘の姉たちにはモテモテなのに目もくれず、末娘への純情ぶりが可愛いこと。悪魔のくせに人間の娘に惚れてしまった弱み、父親には結果的に大金を騙し取られ(後で取り返したのかもしれぬが)娘への思いも遂げないうちに逃げられてしまう。何だか可哀想ですね。
まあつまらぬ物語ですが、音楽がすごい。管弦楽法の大家レスピーギらしく、大編成を駆使し、バスクラリネット、コントラファゴット、シロフォンなどさまざまな楽器のソロを贅沢に使った、管弦楽好きにはたまらぬ音楽ですな。
主役級歌手たち、良かったです。ベルファゴール役の北川辰彦氏、堂々たる演技と歌唱ぶり。娘役の大隅智佳子、船乗りの内山信吾、父親佐藤泰弘の各氏とも熱唱で、だいたいオーケストラが雄弁ということは歌い手にそれと渡り合う豊かな声量が求められるわけですが、皆さん立派でした。
久し振りに珍しいオペラを楽しみました。