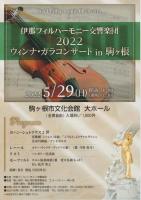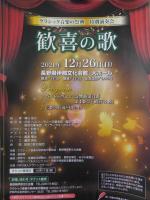北山トライアングル音楽ばなし
20220629
打楽器界で大ブームになっている「北山トライアングル」。この楽器を何十本も比べて試奏する珍しい機会がありました。
この楽器は、アマチュアの打楽器愛好家北山靖議さんが開発したものです。私は3年前「激レアさんを連れてきた」というTV番組で存在を知りました。北山氏はかなり独特な人で、子供のころから音に敏感で奇行も多く、シンバルを自転車のベルの代わりに取り付けて鳴らしながら走ったり、音が良くなるかもと楽器を土の中に埋めて掘り出したりしていたとか。
まあオタクと呼ばれる部類の人だったわけです。私もかつて本欄にも書いた、仙波清彦とはにわオールスターズのライブでご本人をお見掛けしたことがありますよ。TV放映を見たばかり、胸にトライアングルのアクセサリをつけていたのですぐわかりました。
北山氏がトライアングルを作り始めたきっかけはリンク先の記事に詳しいです。試行錯誤の末に完成した北山トライアングル、その美しい音色に魅せられた国内国外の打楽器奏者たちが先を争って購入しているという話。私も関心を持っていましたが、すべて彼の手作りで、できた端から売れてしまい店頭に並ぶことがあまりないとのこと。現物に触れる機会がありませんでした。
このトライアングルの見本をたくさん取り寄せることができたので、ぜひ音を聴いてみませんか、と地元で打楽器指導者・楽器販売をしているWさんから最近電話がありました。伊那フィルが出演するコンサートの前日リハーサル終了後、手伝いをいただく打楽器仲間も集まるということでお願いしたというわけです。30本ほども集められた大小さまざまなトライアングルを全部並べ、片っ端から試奏するという贅沢な機会でした。(ここに並んだもの総額で、250万円以上はするかな)
大きさ、径の太さ、材質がそれぞれ微妙に違います。共通するのは響きの多彩さ。トライアングルの音色は一般的には「倍音」を豊富に含む(音の成分が複雑でいろいろな音が同時に鳴る)のを良しとしますが、この倍音はこれまで経験のないほど豊かです。そして響きの長さも特徴で、一度叩くと信じられないくらい長いこと楽器が鳴っています。中では径の太いものが音が良い(わたし好み)と思いました。
これほど音に特徴があると、オーケストラでは目立ちすぎる場合もあるかもしれません。使いどころは慎重に選ぶ必要はあるでしょう。なかなか高価なものでもあり、打楽器を演奏する機会が減っている私が買うかどうかは何とも…でも美しい響きに包まれて、心と耳の洗濯をさせてもらいました。Wさんありがとうございました。
関連リンク: 北山トライアングル
ウインナガラ ご報告音楽ばなし
20220530
昨29日、駒ヶ根での伊那フィル公演「ウィンナ・ガラコンサート」が500名ほどのお客様を迎えて行われました。来場された方々に御礼申し上げます。
今回はコンサートの構成や選曲、ソリストの人選など、企画のほとんどを私のやりたいように(!?)させてもらいました。任せてくれたオケの仲間には感謝、だからこそ成功に向けてはいつも以上に期するものがありました。おかげさまで好評をいただけたようす。
今回の目玉である今牧香乃さんの素晴らしい歌声は会場の人をもれなく魅了したことでしょう。「歌」と合わせることの難しさを体験するのは私も初めてではありませんが、少ないリハーサルの中で今牧さんの歌にオケが(私が)少しずつ寄り添えるようになっていき、本番ではまあ許容されるかな…くらいにはなれたでしょうか。
ホルン協奏曲のソリストM君の演奏は堂に入ったもの。楽しさあふれるステージとなり本人も満足だったと思います。有志が参加してくれたエル・システマ駒ヶ根子どもオーケストラの子供たちは、こうもりや皇帝円舞曲のタメやテンポの変化に頑張ってついてきてくれました。ウィンナワルツの特徴あるリズムは、今回ゲストコンサートマスターをお願いしたF先生のご指導でめきめき雰囲気が出て、こんなに面白かったのかと私たちにも発見でした。
曲と曲との間を地元CATVの女性アナと私のお話でつなぎました。指揮とトークの二役は準備が大変ではありましたが、私がしゃべりすぎてウザがられることも(たぶん)なく、何とか恰好はつきましたかね。
今回は自画自賛満載の記事で申し訳ありません。コンサートがうまくいったので、嬉しくて。お許しを。いろいろ苦労された実行委員の皆さん、文字通り本当にご苦労様でした。
18日の記事で書いたダウト。チラシにはヴァイオリンの写真がありますが、当然ついているはずの「駒」(写真下、弦を張っている白い板)が何故か写っていません。つまり、駒が無え公演、てことで。チラシを作成したT君(管楽器奏者)は、狙ったものではない、と言ってました。
関連リンク: 今牧さんの歌声響く 伊那フィルコンサート(長野日報)
ウィンナ・ガラコンサート音楽ばなし
20220518
来週末、駒ヶ根で演奏会を行います。今度は「ウィンナ・ガラコンサート」と題して、ヨハン・シュトラウスのワルツやオペレッタほか、ウィーンにゆかりのある曲を集めてお送りします。
ガラコンサートとは「祝祭的な顔見世興行」というような意味です。楽しく親しみやすい小品を集め、ソリストを招いたりしてリラックスして聴いていただけるような演奏会です。お正月に行われるウィーン・フィルの「ニューイヤー・コンサート」と同じ趣向と思っていただければ。「祝祭」の内容によっては聴衆にも正装が求められる場合もありますが、今回はもちろん普段着でOKです。
今回は伊那市出身の新進ソプラノ、今牧香乃さんをお迎えしてシュトラウスやレハールらのアリアを歌ってもらいます。今牧さんは現在藤原歌劇団などで活躍中の人で、これまで何度か彼女の歌を聴いたことがあり、いずれ伊那フィルで共演してみたいとかねがね思っていました。声量も表現も素晴らしいです。
それから団員M君がソロを務めるモーツァルトのホルン協奏曲。自動車販売会社社長をつとめ、なおかつオケでは運営委員長の要職にありながら、演奏技術向上へのたゆまぬ努力でメンバーの尊敬を集めています。
「こうもり」序曲や「皇帝円舞曲」、またウィーンとつながりの深かったハンガリーということでリストの「ハンガリー狂詩曲」など、どなたにも楽しめる曲を集めております。通常練習はあと1回を残すだけですが、まずまずの仕上がりになっているかと思います。ぜひご来場いただければ幸いです。
---------------------------------------------
伊那フィルハーモニー交響楽団駒ヶ根公演
「ウィンナー・ガラコンサート2022」
5月29日(日) 14:00開演 駒ヶ根市文化会館大ホール
曲 目
モーツァルト ホルン協奏曲第2番変ホ長調
リスト ハンガリー狂詩曲第2番
J.シュトラウス 「こうもり」序曲、チャルダッシュ、皇帝円舞曲
レハール 「メリー・ウィドウ」ヴィリアの歌 ほか
今牧香乃 (ソプラノ)
松井秀之 (ホルン)
春日俊也 (指揮)
入場料1000円 全席自由
----------------------------------------------
ところで、実はこのチラシにはダウトがありますが、それが絶妙のシャレになっていることにお気づきでしょうか?(「アンネポルカ」のことではありません)
寅年ソング音楽ばなし
20220123
Eテレ(NHK教育TV)で毎朝6時55分から、その名も「0655」というミニ番組をやっています。出勤前の5分間、ペット自慢投稿の歌やちょっと気の利いたアニメなどを放映しています。
新年を迎えてからしばらくの間は干支にちなんだ歌を放送していて、今年はもちろん「寅年ソング」が流れています。その題名は「トラ太郎とトラッタラッタオーケストラ」。動物たちのオーケストラで、トライアングル奏者のトラ山トラ太郎が活躍する歌です。軽快なアップテンポで、主役のトラ太郎君が可愛いです。
雨の日も風の日も朝早くから夜遅くまで一所懸命練習し、ついに迎えた本番ではリストのピアノ協奏曲ばりにソロでオーケストラとの掛け合いをカッコよく演じます。(リストの曲は音楽史上初めてトライアングルをソロ的に扱った曲として有名です)
演奏は【トラ太郎とトラッタラッタオーケストラ【歌:堀江由朗+トラッタラッタ合唱団/演奏:藝大フィルハーモニア管弦楽団/パーカッションソロ:早川千尋】とのこと。トライアングルを演奏する早川千尋さんは長野市出身で、小諸高校から国立音大に進み現在フリーで活躍されている方だそうです。彼女によれば、収録ではトライアングルのみならずシンバルなど他の打楽器も(多重録音で?)演奏したとのことですよ。
さてオーケストラで「トラ」といえば、関係者の誰もが真っ先に思い浮かべるのはエキストラでしょう。さまざまな理由で正団員以外の方に助演としてオケに入ってもらうときに、手伝ってくださる方をエキストラと呼びます。メンバーの少ない伊那フィルでは演奏会の都度、何人ものエキストラをお願いしています。N響などプロのオケでも大きな編成の曲ではトラを呼ぶことは全然珍しくありません。
歌詞にも「オーケストラのトラ」とありますがトラ太郎がエキストラであるような描写はありません。トラッタラッタオーケストラはアニメ画面で見ると弦楽器5名、管楽器3名、ハープ1名に打楽器5名というかなり特殊な編成ですから、この曲のために集まった臨時オケなんでしょうなあ。
もう一月も終盤ですから、まだ放送してくれるかな?今のところ公式の動画はwebでは見られないようです。
関連リンク: 早川千尋さんのホームページ
第九終わる音楽ばなし
20211227
10日もご無沙汰してしまいました。この師走、ありがたいことにもう忙しくて忙しくて…。目標にしている年間100記事に届いてから、ついつい後回しになっておりました。この間に本欄を訪問くださった方、申し訳ありませんでした。
さて昨日、第九公演が(殴り合いになることもなく)無事終了しました。三週前に合唱合わせをした記事を書きましたが、合唱もオケもそれから格段の進歩があり、前日にマスクを外してもらってリハを行ったときにはその変貌に驚きました。本番では集中力もあってさらに良くなり、とてもいい形で演奏ができました。公式発表ではありませんが久しぶりに千人近くの大勢のお客様もお迎えでき、じつに気持ちが良かった!
地元4人のソリストは皆さん安定感のある方々で、前回の練習でもう大丈夫と思いましたが直前にブレスの場所を整えさせていただいたりして、本番はさらに素晴らしい歌を披露いただきました。
第九の第4楽章は人々の心を集める不思議な力を持つ作品だと思います。もちろん歌詞自体がそのような意味合いを持っていますが、誰にもわかりやすい曲想で日頃音楽に馴染みのない人のハートにぐいぐいと迫ってくる曲の構成がすごいですね。そこをあざといという人もいますが、私はこの曲のシンプルな魅力に気持ちをゆだねたいです。
今回は伊那フィルのみならず、南信地域の4つのアマオケによる合同オーケストラという形でした(実態は伊那フィルに他オケの方々に加わっていただいた)。中にはコロナのため練習や演奏会がまだ思うように活動できていないオケもあり、その鬱憤を晴らして?存分に腕を振るっていただく場になったかも。
アマチュアでありながら第九の棒を振ることができるとは、嬉しく有意義な経験でした。本当は今回演奏しなかった1~3楽章が素晴らしい音楽なのです。願わくは、いつかは全4楽章を振ってみたいものです。なんて欲張りな。
関連リンク: 「歓喜の歌」観客を魅了 県文で特別演奏会(長野日報)
第九へ(あと3週間)音楽ばなし
20211207
一か月前の記事で少しだけふれましたが、12月26日に伊那で「歓喜の歌」と題するコンサートがあり、私が指揮をします。メイン曲は年末お馴染みのベートーヴェン「第九」、ただし合唱付きの第4楽章のみの演奏です。先週末にオーケストラと独唱者、合唱団の合同練習がありました。
いやー難しい。合唱付きの曲を振るのは初めてではないですが、今回のように声楽の情報量の多い曲はなかなか交通整理が大変です。コロナ禍ということで合唱の方はみなマスクをしていて(本番では別)声が通らず不明瞭なことおびただしく、歌がどういう状態になっているのかよくわかりません。
加えて大幅改修された伊那文化会館で、初めてのオーケストラピットを上げたスタイルのため、音の聴こえ方がこれまでと全然違い、オケの皆さんもどこにタイミングやテンポを合わせていいのかかなり戸惑ったと思います。
今回、いろんな都合で合唱もオケもいつもよりかなり短い練習期間で曲を作っていくことになっています。プロならぬ身の我々には、良い演奏のためには曲を把握し体や意識に覚えこませるプロセスが必要で、そのためにはある程度の時間がどうしてもかかります。
これができてようやく、きっちりしたアンサンブルを組み立てたり周囲を聴きながら互いに触発しあったり、わずかな変化やに対応することが可能になるのですが、あと3週間で、さてどこまでできるかな。
私自身についていえば、第九の経験は(ティンパニや下棒などで)何度かあり曲の流れは既に頭に入っていますが、歌のパートまでは正直、今回練習を始めるまで勉強したことがありませんでした(加えてドイツ語の歌詞も)。第九の歌詞は繰り返しが多く、言葉の量としては膨大とは言えませんけど、慣れないものはしょうがないですねえ。
やるべきことがたくさんありすぎて、さあどうやって形にしていきましょうか。腕が鳴りますよ。
****************************************************
クラシック音楽の祭典 特別演奏会「歓喜の歌」
12月26日(日) 14:00開演 長野県伊那文化会館大ホール
入場料1,000円(全席自由)
ベートーヴェン:「エグモント」序曲
ベートーヴェン:交響曲第九番ニ短調より 第4楽章
浅井洌作詞、北村季晴作曲:信濃の国
独唱 村上 和歌子S、村上 莉奈A、飯島 竜也T、藤森 秀則B
伊那フィルを中心とした特別編成オーケストラ
歓喜の歌合唱団(中学生から70代まで、110名だそうです)
指揮 春 日 俊 也
****************************************************
8番、そして9番音楽ばなし
20211108
本欄読者の方には事前のご案内ができませんでしたが、伊那フィルでは昨日、2年ぶりとなる定期公演を開催しました。来場のお客様はいつもより少なめではありましたが、久しぶりに皆様に演奏を披露できる嬉しい機会となりました。
オケのメンバーには様々な事情でまだ活動に復帰できていない人も多く、今回はヴァイオリンにとても大勢のエキストラ(助っ人)をお願いすることになりました。本来の実力にかなり下駄を履かせていただいたことは否めませんが、お客様には弦楽器の充実した響きを楽しんでいただけたかと思います。
曲目はハイドンの交響曲「時計」、ベートーヴェンの「エグモント序曲」「交響曲第8番」で、私は久しぶりにティンパニを演奏し、本番のプレッシャーを存分に味わいました。ベートーヴェンの書いたティンパニの譜面は大胆かつ多くの演奏上の課題にあふれていて、奏者にとっては9つの交響曲はバイブル的な存在になっています。小さな失敗をあちこちでやらかしながら、何とか終わってやれやれというところ。
今回のメインとなったベートーヴェン8番。大作「第九」の直前に書かれ、ベートーヴェンの交響曲の中では演奏頻度は少ない…と書こうと思ってちょいと調べたら、日本オーケストラ連盟の2010年度の調査では何と全作曲家全作品の中で堂々2位にランキングされています。これは意外、びっくり。例外的な年だったろうとは思いますが。
「運命」「英雄」「田園」などの愛称付き交響曲と比べると地味な存在ではありますが、約30分のコンパクトな曲ながらきりりと引き締まってユーモアにもあふれる、たいへん魅力的な交響曲です。かく言う私も練習を重ねる中で曲の素晴らしさに気づき、大好きになった一人です。(なんだか毎回、同じようなことを言ってますね)
さて8番があれば9番、というわけで、12月は第九の演奏会を迎えます。もっとも全曲ではなく合唱付きの第4楽章のみですが、地元の合唱団とソリスト、伊那フィル中心のオケによる特別演奏会で、さらに特別なのは、私が指揮者です。
全楽章でないとはいえ第九の棒を振るとはまことに光栄なこと。貴重な機会、一か月少々という短い練習期間ですが無い能力を振り絞って臨みたいと思っております。お近くの方、ぜひお出掛け下されば幸いです。
追悼 エディタ・グルベローヴァ(2)音楽ばなし
20211024
ミュンヘンで目の当たりにしたグルベローヴァにすっかり魅了され、来日したら絶対に行こうと決めた私。その機会は意外と早く訪れ、90年、93年、95年のソロリサイタルに行くことができました。
90年12月の「コロラトゥーラの芸術/オペラ・アリアの夕べ」の白眉はなんと言ってもドニゼッティ「ルチア」の“狂乱の場”。超絶技巧と深い表現力が問われる難曲です。後半のフルートとの会話、絶妙でした。またドリーブ「ラクメ」“鐘の歌”の軽快さ、トマ「ミニヨン」の“私はティターニアよ”の豪奢な響きも素晴らしい。
93年春の公演ではドニゼッティ「連隊の娘」の堂々たる歌で聴衆を引き込み、バーンスタイン作曲の「キャンディード」のアリア“きらびやかに楽しく”という珍しいレパートリーを披露してくれました。
そして95年春。妻と一緒に訪れた公演はアリアの夕べではなくて「ウィンナー・ガラ」と題し、ヨハン・シュトラウスのオペレッタを中心にしたニューイヤーコンサートのようなプログラム。このとき妻は第一子がお腹にいたのですが、初めて赤ちゃんが動いたと驚いていました。胎児をも感動させる驚異の歌唱力!
きらびやかで楽しいリサイタルでしたが、超絶技巧の歌曲も聴きたかったなあ…と思っていたら、アンコールにコロラトゥーラの名曲「セヴィリアの理髪師」“今の歌声は”を歌ってくれました。もちろん彼女の十八番、前奏が始まったとたんに客席から大拍手。やっぱりみんな、待ってたんですね。最後に粋なサービスでした。
一般にコロラトゥーラソプラノの歌手生命はあまり長くないと言われます。喉にかかる負担の大きな超高音を歌い続けることは難しく、また年齢による声質の変化で歌える役柄が変わってくる(レパートリーを変えていかざるを得なくなる)からです。
ところがグルベローヴァは昨年73歳で引退を表明するまで、驚異的な長期にわたって第一人者として活躍しました。音楽雑誌のインタビューでその秘密を聞かれて「努力の賜物」と答えています。シンプルなお答えですが、そうなんでしょうねえ。天から与えられた美声を保ちさらに磨きをかけていくには、余人には想像もつかない凄まじい努力が必要だったことでしょう。
家にあるCDを順に聴きライブでの幸福な体験を思い出しながら、偲びたいと思います。
関連リンク: 追悼 エディタ・グルベローヴァ(日本舞台芸術振興会)
追悼 エディタ・グルベローヴァ(1)音楽ばなし
20211023
世界最高のコロラトゥーラ。輝く高い声を自由自在に操り人々の心を震わせた歌姫の訃報が伝えられました。スロヴァキア出身のソプラノ歌手、エディタ・グルベローヴァ。全盛期の彼女の生演奏に4度も立ち会えたことは、私の音楽の経験で最も素晴らしいものの一つだったと思います。
クラシックファンでありながら、声楽に強い関心を持っているわけではなく歌い手の名前はそれほど知りません。「音楽の友」誌で評論家や音楽記者が選ぶ「コンサート・ベストテン」というのが毎年あり、80年代後半からグルベローヴァという名前がたびたび上位に登場するようになってこの人の存在を知りました。どんなすごい歌手なんだろうかと想像していました。
CDで彼女のオペラアリアの数々、いわゆる「狂乱の場」を集めたものを聴いて、度肝を抜かれました。「ランメルモールのルチア」「ロミオとジュリエット」「ラクメ」などの超難曲を軽々と歌いのける高度な技術を持ちながら、曲芸に堕することなくしっとりした情感のあふれる歌に魅了され、ぜひ一度生演奏を聴いてみたくなりました。
その最初の機会はミュンヘンで訪れました。一人旅をした89年夏のヨーロッパ、ミュンヘンのオペラ祭でのR.シュトラウスの「ナクソス島のアリアドネ」上演に接することができたのです。
このオペラのツェルビネッタ役は「魔笛」の夜の女王とともにグルベローヴァが世界の楽壇に燦然とデビューした役。80年のウィーン国立歌劇場来日公演でも歌い、日本のオペラファンを驚愕させました。その姿を本場ミュンヘンのオペラハウスで観ることができようとは…すごい期待をして会場に向かいました。(海外でオペラを観ること自体、初めても同然でしたしね。このためだけにジャケットなぞ持って行ったのです)
ツェルビネッタは、道化芝居の踊り子です。主人公アリアドネを終始からかうコミカルかつ小悪魔的な役柄で、演技力も求められます。そしてオペラの終盤に有名な「偉大なる王女様」という、15分以上にも及ぶ長大かつ超絶技巧のソロがあるのです。プロ歌手だったら誰でも歌えるといった役柄ではありません。
低いささやくような声から、ある評論家によれば『成層圏のような』超高音までグルベローヴァの声は小鳥のさえずりのようにころがり、駆けめぐり、ホールを揺らし、世界中から集まった(そういうオペラ祭でした)聴衆は固唾を呑み圧倒されていきました。劇場を満たしたすごい緊張を今でも覚えています。ソロが終わったときの爆発するような拍手!世界最高の本物の存在が目の前にあることの感激を味わえました。
そこを叩くんじゃない音楽ばなし
20211013
忘れた頃に登場する打楽器シリーズの番外編です。
「のど自慢の鐘」といえばあれか、と誰でも思い浮かべることができる楽器。名称は「チューブラーベル tubular bells」もしくは簡単に「チャイム chimes」と呼ばれることが多いですかね。オーケストラでも20世紀後半以降の曲ではしばしば使われる、れっきとした打楽器です。
新品の値段は安いものでも70万円くらいし、私の子供の頃は公立学校ではおいそれと手の届かない贅沢品でしたが、最近は中学高校の部活でも普通に備えられるようになりました。時代を感じます。
我が家では朝見る番組は日テレの「Zip!」が多いです。先日は家庭で役に立つ裏ワザを特集していて、登場したKing & Princeのタレント岸優太が感心したネタにチューブラーベルを鳴らして評価する、というコーナーがありました。彼が楽器を鳴らすところを見てびっくり仰天!
ご覧の通り、楽器のパイプの中間場所をハンマーで叩いております。これは絶対にいけません。パイプが凹んでしまいますし、だいたいまともな音はしません。部活などでやらかしたら、間違いなく先輩からキビシイお仕置きです。凹んだらまず直せないのでそのパイプを何万円もだして交換しなくてはなりません。
正しくは、パイプの上部にあるキャップ状の部分(もちろんパイプと同じ材質の金属)を斜め上から叩きます。今度のど自慢を見るときにご確認ください。
私はほとんど観ていなかったのですが、何年も前「伊東家の食卓」という人気番組がありました。この中で伊東四朗が同じような場面で毎回チューブラーベルを叩いていて、やはりパイプの途中を叩いていました(これも日テレだ)。プロアマ問わずあらゆる打楽器奏者が激怒し、打楽器の専門ウェブサイトでも話題になりました。TV局に抗議した人もきっといたと思います。ずいぶん経ってから正しい場所を叩くようになったとか、ならなかったとか。
楽器を登場させるのに演奏法もロクに調べないのは、この業界では普通のことなのですかね。ここで使われた楽器が日テレのものなのか、どこかの楽器レンタル業者から借りたのかわかりませんが(放送局ならチューブラーベルを持っていても、まあ不思議ではないかな)レンタルしたものならば、前歴もあるし二度と貸してくれないのでは。