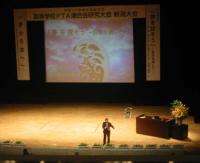夏山侮ることなかれ日々雑記
20130731
昨日は駒ヶ根市が各局のトップニュースになりました。中央アルプスでの韓国人ツアー遭難死事件の話。我が家から歩いて行ける駒ヶ根警察署の前では、国内各TV局はもちろん、韓国のTVも来て現地中継をしていたようです。
4人死亡と、地元では最近ちょっと記憶にない大量遭難事件です。調べたわけではありませんが、もしかすると「聖職の碑」事件以来ではなかろうか(大正2年、中学校の集団登山で11人が遭難死した)。
遭難した方にはお気の毒なことです。あくまで結果論であろうとは思いますが、やはり無理があったとしか言いようがありません。山小屋のオーナーは出発の朝に「天気が良くないから登山はやめた方がいい」と止めたそうです。麓でも激しい雨風だった29日の天気で、山のプロならともかく、高齢の外国人が登山をする環境ではなかったということです。装備も軽装に近く、日本仕様の携帯電話も持っていなかったようです。
私は遭難現場からそう遠くない、駒ヶ岳ロープウェイの終点に位置するお得意様「ホテル千畳敷」さん(標高2600m)に何十回と荷物を運んでいました。ここは夏でもホントに涼しく、好天の日でも長袖でなくてはちょっと肌寒いほど。14℃くらいですかね。ロープウェイで麓から一気に上がると、下界の熱さが嘘のような爽快さです。
天気が良ければともかく一昨日はかなりの吹き降りと濃霧ですから、体感気温は一桁、日本の山に慣れていない韓国の人たちには想像できないものがあったのだと思います。
起こってしまった事故は残念なことですが、このことでいまハイシーズンの中央アルプス山岳観光に悪いイメージがつかないよう願います。本当はもっと明るい話でニュースになって欲しいものです、まったく。
うな丼の未来 (2)うな丼の未来
20130728
ご存知の通りウナギの生態は謎に包まれたものでしたが、最近になってだいぶいろいろなことが分ってきました。
遠くマリアナ海嶺で卵から孵化したニホンウナギの稚魚は、黒潮に乗って台湾→中国→日本へと回遊して(流されて)きます。淡水を求めて河口をさかのぼり、川の上流で成魚となって、また産卵のために川を下りはるか沖へと泳いでゆきます。
いわゆる「シラス漁」の対象となるのは河口付近でのこと。広い海では細かいシラスを採取することなどできませんが、河口に集まってくるシラスを、まあ言葉は悪いが一網打尽にしていたわけです。(といっても、そんなに大量に採れるわけではありません)
ウナギの養殖業者はこのシラスを購入し、養鰻池(ようまんいけ)で成魚になるまで育てて出荷します。産卵の段階からシラスを育てるなど、シラスそのものを増やす技術は実用化されておらず、シラスが採れなければ養殖は成り立ちません。いわゆる「完全養殖」ができている水産物との大きな違いです。
さてそこで…
近年シラスの採取量が激減しているというのは、まぎれもない事実です。それに伴ってシラスの価格が跳ね上がり、㌔当り200万円を超えるケースもみられるようになりました。原料資源がこうですから、流通が川下に行くほど価格はさらに高騰し、蒲焼の店頭価格も大変な値上がりとなっているわけです。
なぜ減っているのか。1に乱獲、2に河川環境の悪化(ダムとコンクリートのためウナギが遡上できない)、3に気候現象の変化(エルニーニョなど)です。3は短期的な話で、今後気象条件によって事態が改善することも期待できますが、1と2は楽観的な見方はとてもできないのが実情です。
中でも乱獲→暴食の影響は深刻です。世界中のウナギの7割は日本人が消費しています。国産がいなくなったら中国から輸入すればいいという人、中国の養殖ウナギだってみんな日本に来ているのですよ。ニホンウナギのみならずヨーロッパウナギにまでおよび、世界のウナギを日本人が食べつくす勢いなのです。
写真は、あるところで撮影したシラス。針のような細さです。体長3センチくらい。どこで撮ったかは、またあとで。
うな丼の未来 (1)うな丼の未来
20130723
昨日は土用丑の日。ウナギをおいしく召し上がった方も大勢いらっしゃることでしょう。私は昨日は食べていませんが、今月初めに近くの和食屋さんで、飲み仲間たちと蒲焼をいただきました。久しぶりで大変おいしかった。
蒲焼にわさびをちょっと添えるのは、伝統的ではないのかもしれませんが、私は好きですね。山椒よりも合うように思います。でもお店で最初から写真のようにして出てきたのは、初めて見ました。「白焼きにわさび」は定番ですけど。(そういえば白焼きもしばらく食べてないな)
しかしご存知の通り、うなぎのお値段は近年、文字通りうなぎ上り。鰻屋さんの価格もスーパーの店頭価格も、驚くほどの高値になりました。うな重なんて、そんな高級店でなくても3千~4千円近くだったりします。これではおいそれと注文できません。
背景は、これまたご存知の通りで、漁獲量の不足です。養殖ウナギの元になる稚魚(シラス)が獲れないのです。モノがないので市場価格は跳ね上がり、老舗の鰻屋さんが「とてもこの値段ではお客に出せない」と店を畳む事例が、続出する事態となりました。
一方で「企業努力で安値を実現しました」という大手スーパーが現れて庶民の味方みたいに言われたり、東南アジアやアフリカの異種ウナギをどこぞの商社が見つけてきては、日本の食文化を守るための救世主になるか!?なんてニュースになったりしています。
ウナギは本当に減っているの?
だとすれば、その原因は何なの?
世界の知られざる地域のウナギを開発すれば、まだまだ食べられるの?
私たちはこれからもずっと、今のようにウナギを食べることができるのかな?
私は2年ほど前からこのことに強い関心を持ちはじめ、自分なりに情報を集めたりしてきました。その中で三重大の勝川俊雄氏の存在を知り、彼の書いたものを読んで日本の水産業にまつわる諸々の問題の根深さに心を痛めもしました。
丑の日を前にして、ウナギを扱った報道が山ほど伝えられましたが、その視点はさまざまで、本当にウナギの将来を考えているのか首を傾げざるを得ないものも相当あったようです。ちょうど良い機会だとも思いますので、専門家でない私の知る範囲のことを、ここで何回か続けて書いてみようと思います。
鼻歌交じりに命がけ日々雑記
20130716
先週末、PTAの北信越大会に参加するため、新潟市へ行ってきました。
長野県と新潟県はお隣の県ですが、駒ヶ根から新潟市までは両県をほぼ縦断し、片道300㌔以上の遠路です。普段行く用事はなかなかなく、私もこれまで一度しか訪れたことがありません。
大会は二日間にわたって行われ、1日目はセレモニーと分科会(各校の事例発表など)、2日目には記念講演として、東京藝術大学学長の宮田亮平さんによる、たいへん面白く興味深い講演がありました。
宮田さんは地元新潟の佐渡出身、金属工芸を専門とし、イルカをモチーフとした数々の作品で知られます。以前NHKで爆笑問題が藝大に乗り込んだ「ニッポンの教養スペシャル」という番組に登場したのを観ましたが、きわめてフレンドリーに学生の中に溶け込んでいた様子が印象に残っています。
講演ではいきなり2階客席から登場する奇手に出て、会場を驚かせました。その後もステージ上にとどまることなく客席を歩き回りながら(たぶん…2階席だったので1階客席の様子はわからず)参加者との距離を縮めて自由闊達な話を聞かせました。
とてもポジティブな人だと思いました。藝大を出ても自分の作品制作で食べていける人は一部でしょう。だからこそ、お高いゲイジュツ品を作っていればいいのではなく、お金の稼げる芸術の制作を大学では学生たちに示唆しなければなりません。しかしそこが決して卑近にならず、むしろ感嘆をも呼ぶような豊富なアイデアが湧き出てくるところが凄い。
卒業式で、ここ何年か書道パフォーマンスを見せているそうですが、心底楽しんで、それがまた学生たちに勇気を与えていることがわかります。失敗談もありましたが、いかにしてそれをリカバリーしたか、ここで記すことは憚られますが、傑作でした。
「鼻歌交じりに命がけ」というのがモットーだそうです。失敗したっていい、そこから新たな発見があり、次なる成功へとつながる…というのは様々な場所で何百回も聞くことですが、それを悲壮感なく「鼻歌交じり」でやってのける前向きさが、とても魅力的な方でした。
PTA大会の講演のときよく思うことですが、親である私たちだけでなく、子供たちに聞かせてやりたいと思います。この話を聞いて美術を志す人がさらに増えるかも知れません。でもそのために、現在でも20倍を越すと聞く藝大美術科の競争倍率が、余計に高くなってしまうかも。
新津駅にある、鉄道を題材にした陶板作品の話題が出たので、帰りにちょっとだけ回り道をして新津に寄ってみました。うん、本物はすごい(辛子レンコンと呼ばれたそうな)。講演を聴いた人が千何百人いたか知りませんが、すぐ新津まで行って現物を拝んだ物好きは、あまりいなかったのでは?
関連リンク: 藝大ホームページ(過去の学長挨拶が載っています)
あまちゃん東京へ読んだり見たり
20130708
一気に話が跳び、舞台を東京へと移した「あまちゃん」。目まぐるしい展開に、じぇじぇじぇ!と目が点になってしまいます。
三陸の漁村で海女の技を習得しながら地域おこしをしていくドラマだと思っていたら、実はテーマは「アイドルの時代」だった、ということですね。しかし放送開始から3か月たっての大回頭は凄い。週刊誌の見出しを見るとネタバレ裏情報?がひっきりなしに掲載され、さてどこまでホントなのか、首を傾げてしまいます。(読んでしまってはつまらないので読みませんが)
まあまあ、面白いドラマといっていいでしょう。私はキョンキョンや薬師丸ひろ子が活躍していた何年間か、テレビを持たない生活をしていましたので、アイドルに心ときめかせた経験はあまりなく、彼女らが登場しても別に感慨はありませんが、それ抜きでもじゅうぶん楽しんでいます。キョンキョンの少女時代を演じる子、よくそっくりな娘を見つけてきましたな。
主人公の能年玲奈、とても魅力的です。最初の数回を見なかったので、何で東京育ちの主人公がこんなに訛っているのか不思議に思っていました。これは、三陸に来て周囲から「うつった」のですってね。1年やそこらで大したものだ。影響されやすい子なのかな…
今日の放送で、彼女の台詞にちらっと沖縄ことばみたいな語尾がみられ、おっと思いました。今は日本各地のお国ことばの中で暮らしてるんだから、当然ありえます。だんだん三陸ことばが薄まっちゃったりしたら、ご当地アイドルのアイデンティティに関わりますよ、死活問題だ。
共演陣もそれぞれ良い印象ですが、中でこの間までの相棒だったユイちゃん(橋本愛)の無愛想さがずっと前からとても引っかかっています。そこがいいのよ、という人もいるんでしょうなあ。
そうは言っても、舞台は何らかの形で三陸に戻るのでしょう。クドカンの脚本がどんな形でこの大風呂敷を畳むことができるか、見ものだと思います。
国境の風音楽ばなし
20130701
この歌は、北朝鮮による拉致被害者やその家族に思いを寄せた歌です。荒木とよひさ作詞、南こうせつ作曲。
昨日伊那市で「ふるさとの風コンサート」と題した演奏会に出演し、指揮しました。拉致被害者家族連絡会の事務局長、増元照明さんの講演を挟んで15団体が次々とステージに立ちました。伊那フィルは地元の男声合唱団と合同で唱歌のメドレーを、そしてコンサートの最後には会場全員の合唱と共に、この「国境の風」を演奏しました。
増元さんのことは様々なメディアを通じて皆さんよくご存知だと思います。実姉のるみ子さんは1978年に拉致されました。るみ子さんは当時24歳でした。
肉親がある日突然消えてしまった喪失感、その実態が北朝鮮工作員による拉致の可能性濃厚だと知った時の衝撃、被害者家族の訴えを門前払いし黙殺し続けた警察、政治、メディアへの怒りと絶望感。2002年、時の小泉首相訪朝時に金正日が拉致を認め謝罪し、日本国内の空気は一変しましたが、それ以後5人の拉致被害者が帰国できたものの、他の人たちについては依然として消息不明のままです。
そんな状況で何年も何年も、あきらめず、粘り強く、被害者救出活動の先頭に立って活動してきた増元さんが、講演のあと、「国境の風」をステージで合唱団と一緒に歌うことになりました。
指揮者の私、前にはオーケストラ、その奥に増元さんと男声合唱団。背後には客席を埋めた当日の出演者たちとお客さんたち。
曲を始めます。流れるような、しかし力強いメロディー。後ろから聴こえてくる歌声の、予想を大きく超えてあふれる響きに少し驚きながら、顔を上げて正面の増元さんに目をやると…
増元さんが、顔を真っ赤にして、ぼろぼろと涙を流して、泣きながら歌っているのです。それを見た私は、いま演奏しているこの歌で、この人の思いに全力で応えたい!という気持ちで胸がいっぱいになりました。会場のみんなの共感を増元さんに、家族の方に、国境を越えたどこかで必ず生きている被害者の方々に届けるんだ、と。
演奏中増元さんを見ることのできないオケの人たちにも、何かが伝わったのだと思います。指揮台の上では常に頭を離れることのないテンポやタイミングやバランスを忘れ、熱さと思いだけで指揮をしたのは初めてです。指揮者として決して褒められたことではありませんけど。
これもひとつの、歌の力でしょうか。
拉致被害者の方々が一日も早く、ご家族のもとへ帰ってくることを願います。
関連リンク: 「国境の風」歌詞