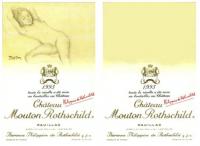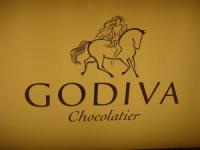閏日生まれの画家日々雑記
20120229
2月29日に生まれた人は、4年に一つしか年を取らない…なんて子供の頃に言ったりしましたね。閏年以外の年に誕生祝いをする日は、前日の28日なのか、それとも翌日の3月1日なのでしょうか。
2月29日生まれの有名人を調べてみますと、
ロッシーニ(1792年生まれ、イタリアの作曲家)
バルテュス(1908年、フランスの画家)
マキノ雅弘(1908年、映画監督)
兼高かおる(1928年、旅行ジャーナリスト)
原田芳雄 (1940年、俳優、先日亡くなったばかり)
赤川次郎 (1948年、作家)
飯島直子 (1968年、タレント)
というような方々がいらっしゃいます。
バルテュス。ご存知ない方が多いかと思います。私も大して知識はありません。唯一、ワインつながりで1枚の絵を知っているだけです。
ボルドーの銘醸、超高級ワイン「シャトー・ムートン・ロートシルト」のラベルは、毎年異なった著名な画家による絵を採用することで有名です。ダリ、ミロ、シャガール、ピカソ、ウォーホルら錚々たる画家たちが、このワインのために絵を提供しています。(その報酬は、ムートン1樽だそうです)
1993年に白羽の矢が立ったのが、バルテュスでした。彼が描いたのが、写真左の少女の絵です。(いったいこの絵は、完成品なのでしょうか…?絵心の乏しい私には、どう見ても描きかけにしか思えない)
ところがこの絵が、児童ポルノではないか、とアメリカで物議を醸しました。結局アメリカではこのラベルでの販売が許されず、ムートンは仕方なくアメリカ輸出向けに「無地」のヴァージョンを出荷することになり、この年だけは2種類のムートンが存在することになったのです。
以前にある人から、お子さんの生まれた年(93年)のワインを注文いただいて、探した末にこのムートン(オリジナルラベル)をお届けしたことから、このエピソードを知りました。お子さんが20歳になったら開けてお祝いをする、と言っていましたので、来年には熟成し飲み頃を迎えた銘酒を楽しまれるのでしょう。
ちなみにバルテュスは来日したとき出会った日本人画家、出田節子と結婚していますが、節子夫人もムートンのラベルを委嘱されており、夫のバルテュスよりも2年早く、91年のラベルを描いています。
関連リンク: ムートンのラベルを描いた画家たち
樽香 飲みもの、お酒
20120224
先日あるところで、ちょっと変わった焼酎を飲みました。芋焼酎を、シャルドネのワイン樽で貯蔵した、というもの。ほほう、芋に白ワインとは、いささかミスマッチのようにも思えますが?
グラスに注ぐと、パッとたちのぼるのは確かに白ワインの香り。芋焼酎独特の香りは、ほとんどありません。飲んでみた印象も、芋というよりワインを使ったリキュールという感じかな。度数33度と、ややアルコール強めの焼酎でしたが、ロックでおいしくいただきました。
お酒を木の樽で貯蔵すると、当然樽の香りがお酒に移り、独特の風味が生まれます。たとえばワインでも、フレンチオークの新樽を使ったものにはバニリンという成分が、ほの甘いバニラの香りを醸しますし、スモーキーな香りも樽から生まれます。新樽とそうでないものでは、明らかに香りも違ってくると言われています。
白ワインでバターの香りがすることもありますが、これも新樽に由来するそうです。ワインにバターの香り?と思われる方もいるでしょうが、我が家の家呑みでも時々お目にかかります。当然ながら、バターを使った料理との相性はバッチリですよ。
ほど良い樽香は心地よいものですが、樽香がプンプンするいかにもわざとらしいワインもあります。何ごともほどほどが肝心だということですね。樽香を避けるため(今では良質の樽はなかなか高価になっていることもあり)あえて木の樽を使わずにステンレスのタンクを使うことも多く、要は味の終着点をどこに持ってくるかでしょう。
もちろんワイン以外にも、樽の香りをつけるお酒はたくさんあります。CMなどでお馴染みのように、ウイスキーの熟成には樽が不可欠ですが、本来全然別のお酒である「シェリー酒」の樽で熟成させたウイスキーは、高級品として愛飲されています。
シェリーはスペインのお酒で、分類上はフォーティファイド(酒精強化)ワインと呼ばれ、普通のワインとは少し造り方が違います。葡萄を原料に樽を使った独特の「ソレラ・システム」という熟成過程を経てできあがるのですが、そこで使われた樽には豊潤な香りがつくことで、他のお酒の香り付けにも珍重されるのです。
「通」の方は樽の種類にまでこだわってテイスティングをされるのでしょうが、私はワインならともかくウイスキーでは、そこまでとても研究(ったって飲むだけですが)が及びません。ただただ美味しいと喜んで杯を重ねるばかりです。
シェリー樽で寝かせた焼酎をだいぶ前に飲んだことがありますが、これは実に芳しい上品な香りに満ちたお酒で、魅了されました。もう一度飲んでみたいと思うのですが、検索するとえらく高い値がついており、驚きました。これでは簡単にいただけません…
関連リンク: 本格焼酎 刻の一滴
ヒロインは豪傑読んだり見たり
20120220
そろそろ話も終盤へと移りつつあるNHK朝ドラ「カーネーション」。前作とはまったく対照的なこのドラマはなかなか面白く、最初の二週間ほどを除けば欠かさず録画して観ています。
ご存知、ファッションデザイナー・コシノ三姉妹の母をモデルにしており、主人公の小原糸子役は尾野真千子が演じています。この女優を私は本作まで知りませんでしたが、好演です。とてもいい味を出してますね。
糸子は小さい頃から父(小林薫)にそれは厳しく育てられます。この親父がまあ、娘に平手打ちは見舞うは卓袱台はひっくり返すは、「星一徹」みたいな頑固オヤジで。父親に物凄い反発を抱きながら家業の裁縫屋で仕事を始める糸子なのです。
その父が亡くなり、夫も戦死します。当時まだまだ珍しかった洋裁の仕事をしながら3人の娘たちを育ててゆくのですが、どんどん親父そっくりの頑固母になっていくのが面白い。台詞もモノローグも、まるで男です。おろおろしながら父をなだめていた母(麻生祐未)が、今では娘を叱る糸子を同じようになだめたりして。
家族の夕餉に、女主人が燗酒で毎日晩酌し、そのまま居間の畳に寝転んで眠ってしまうなんて映像、ドラマで見たことありますか?飲兵衛の父の血を受け継いだそうで、初めはお猪口で飲んでいたのが、この前はコップ酒になっていました。
脚本は非常にテンポが良く、いやむしろあっさりしすぎて拍子抜けするような時もあります。糸子の夫なんて、いつの間にか結婚しいつの間にかいなくなってしまったみたいな。「おひさま」の一週間分を1日で放映しているようなスピード感です。
三人の娘たちが大人になってから、ドラマの重点は彼女たちに置かれ、糸子は少し引っ込んだような印象があります。ちょっと淋しい気がしますが、その分、二女役の川崎亜沙美の存在がすごい。女子プロレスラー(!)と女優の二足のわらじの人だそうですが、もうコシノジュンコ氏に瓜二つ。物語の舞台、大阪岸和田の出身でもあるそうで、よくこんな人を見つけてきたと感心します。
朝ドラでは一週間通しのサブタイトルがつけられていますが、このドラマではそれがみな「花言葉」になっています。先週の「あなたを守りたい」はエンゼルランプ、今週の「鮮やかな態度」はルドベキアだそうです(どんな花だか聞いたことがありませんが)。
そういえば何でこのドラマのタイトルが「カーネーション」なのか、知りませんが、あるいは「母」と関係があるのかな。花言葉は「真実の愛」「情熱」だそうです。
フーターズお店紹介
20120217
話題のお店に行く機会がありました。といっても、オープンして既に1年3ヶ月もたっていますが。
フーターズ。アメリカ中心に450店舗を展開するカジュアルレストランで、日本では現在、東京・赤坂見附に唯一の店を構えます。評判は前から聞いており何度か近くを通ることもありましたが、そのたびにサラリーマンたちの行列ができているのを見て、興味津々だったのです。
ここの一番の「売り」は何かといいますと、店で働く元気のいいウェイトレス(フーターズガール)たち。白のタンクトップにオレンジのホットパンツが目に眩しい、チアリーダーをイメージしたようなユニフォームです。胸元も大きく開けて、いささか目のやり場に困るような…
誤解のないように慌てて付け加えますと、店内の雰囲気は極めて健康的かつ開放的で、いやらしさなんて全然ありませんよ。女性客も結構見受けられます。男性客の鼻の下がいつもよりちょっぴり長いことは、否定しませんが。
フーターズガールたちはまことにフレンドリーで、お客が来店着席するとテーブル担当の子が自己紹介をし、話しかけられればノリの良いリアクションを返し、写真撮影も(隠し撮りはNG、必ずひとこと断ってから)OK。サービスもなかなか気のつく、気持ちの良いホスピタリティです。
もちろん美女揃い。少し話した子は、こんど東スポの何とかコンテスト?に出る、なんて言ってました。この店をきっかけにして、モデルなどを目指している子もいるんでしょうな。
料理はチキンとハンバーガーが中心で、格別おいしいものを食べに行こう、という種類の店ではありません(もちろんそれなりの水準はキープしています)。味よりも雰囲気を楽しむ、こうしたお店があってもいいでしょう。同種のレストランと比べてそう値付けが高いわけでもないですね。ちょっと私には、BGMがやかましいのが残念。
写真のフーターズ・キティちゃん・ピンバッジは購入したのではなく、ちょうどサンリオとコラボしたバレンタインのキャンペーン中で、ちょっとした「訳あり」でもらったものです。店内の写真はupしませんので、代りにこれをご覧になってフーターズガールたちの姿をご想像下さい。
(いや、これじゃ何だかマラソンの選手みたいだな)
関連リンク: フーターズTOKYO
鹿の肉どうする (続き)食べもの
20120214
言うまでもなく長野県は鹿肉の消費拡大に向けて音頭を取っており、ジビエの普及に熱心な茅野のレストラン「エスポワール」の藤木徳彦氏らによって県下各地で幾度となく料理講習会や試食会が開かれています。。
今日の昼間もあるところで鹿肉の話題が出ましたが、その会話を聞いていて気がつきました。どうやら鹿肉は、それほど魅力的な食材とは思われていないらしい、ということです。刺身で食べたり焼肉にしたりする程度では、一度は食べてみても「また食べたい!」と思わせるほどのものはあまりないのではないか。
これでは消費が拡大するわけないですよね。私だって今まで何度か鹿肉を食べてはいますが、じゃあ牛や豚よりもうまいかと言われると、どうでしょう。そうしてみると、鹿肉を珍しさだけでなく、心からうまいと思わせるようなメニュー開発は、やはりとても大事なのだと思います。
(そういえば何年か前に仲間で「鹿のレバ刺し」を食べたことがあります。普段レバ刺しを食べない私も珍しいので食べてみましたが、すこぶるうまかった。当然それなりにリスクのある食べ物だったでしょう…今のご時勢では、とても食べさせてもらえるものではありませんね)
ハンターが仕留めた鹿を衛生的な環境で解体し、移送保管を担う流通ルートはあるものの、まだ十分とは言えないようです。あまりこの部分にカネがかかっては、最終的に飲食店から消費者へと提供される価格もそれなりのものになってしまいますし。ある程度こなれた、メニューに使いやすい価格で安定的に流通させるようなシステム作りが急がれます。
当社もできれば、その一翼を担ってみたいという気持ちはすごくあるのですがね…もちろんウチには解体加工の設備はありませんが、県内には現在15箇所ほど鹿肉の処理施設があるようです。多くのお客様を持つ私共の販売ルートを生かせるような仕事があれば、と思っています。
鹿の肉どうする食べもの
20120212
野生の鹿があまりにも増えすぎて、長野県下でも農林業に深刻な被害が出るようになって随分たちます。一昨日のニュースでは、いま県下に生息するニホンジカは約10万5000頭。今年はそのうち、何とか3万5000頭を駆除したい、と関係者が話していました。
実際に3万5000頭を仕留められるかは分かりませんが、これまでも2万頭ほどの実績はあるようです(伝聞なので正確でないかも知れません)。
こうして獲った鹿の肉ですが、残念なことに有効活用(食用)にされているのはその中の一割にも満たないそうです。ほとんどは埋められてるってことでしょうか?いろいろ事情があるのだとは思いますが、もったいないことですよね。これでは鹿も成仏できまい。
いかんせん需要が少なく、流通に乗せるほどではないということでしょう。鹿の肉をわざわざ食べたいと思う人は、あまり多くはないようです。
鹿の肉を召し上がった方は、どのような印象を持たれたでしょうか。私にはそれほど癖のある肉だとは思えませんが、人によっては(羊の肉を嫌がる人が一定数いるように)普段食べつけている牛豚鶏と違うということで、おいしく感じられないこともあるようです。
当社お得意様「アンデルセン」さんで、鹿肉のカレーなどをメニューに載せたと地元のCATVで放送されたのを見て、翌日伺ってみました。生肉をそのまま焼いたもの、パン粉をつけて揚げたもの、下煮したものを少しずつ試食させていただきました。
焼肉だと肉の特徴が強調されるようですが、揚げたり下煮したものは、すっかり癖が消えてどなたにも食べやすい味になっています。
続きます…
食の縁結びしごと
20120209
飯田市で、ご当地食品・食材の展示商談会が行われ、行ってきました。
「食の縁結び・南信州うまいもの商談会」
県下伊那地方事務所の主催です。野菜や畜産品などの生鮮素材や、ジャムやジュース、漬物、調味料などの加工品あわせて出展は40社ほど。NHKなどテレビ局も何社か取材に来ていました。
全国や世界各地の品物を地域にお届けすることは流通業者の主要な仕事です。その一方で、地元産の優れた食材を世に出すお手伝いをすることもまた、大事な任務であると思います。残念ながら当社はこの部分で、まだまだ力を発揮できていなかったのではないかと反省をしています。
今年は地元産品の掘り起こしに今まで以上に力を入れていこうと思っておりまして、米粉パウダーを発売したのも、その一環といっていいでしょう。
試食をする中で感じたのは、「信州黄金シャモ」の抜群のおいしさ。歯ごたえ、噛み締めたときの中から湧いてくる旨味。当社でも少しずつ取扱いをしているのですが、改めていいものだと思いましたね。もっともっと注目されてもいい食材です。
信州特産品である「りんご」「柿」の加工品もいろいろ出品されていました。世に類似品は多く、南信州産の色を出す工夫がさらに必要だと思いますが…何か統一ブランドをうまく使ってみたらどうでしょう?
泰阜村名産の「柚餅子(ゆべし)」は鄙びた素朴な味わいで、とても印象に残る良いものだと以前から思っています。大量生産するようなものではないですが、もっと多くの人に知ってもらいたいですね。
いろいろ気がつくことがありました。ぜひ私たちの商売にも繋がりますように!
関連リンク: 長野県園芸畜産課「信州黄金シャモ」
ゴディバ食べもの
20120205
もうすぐバレンタインデーですね。先週末東京出張の折、新宿のデパ地下に寄りましたら、フロア中もうチョコレートだらけ、という様相でした。今回は高級チョコの代表格、ゴディバについて書いてみましょう。
ちょっと前、たまたま英語の辞書を引いていて、同じページで近くにあった言葉が目にとまりました。
Peeping Tom
のぞき見のトム(Godiva夫人をのぞき見して目がつぶれたといわれる仕立て屋)
ピーピングトムなる単語はもちろん知ってますが、その由来はこれまで聞いたことがありませんでしたな。それで、Godiva夫人とはいったい何者でしょうか?
Lady Godiva
ゴダイバ夫人(11世紀英国の貴族の夫人;夫がCoventryの町民に課した重税を廃止する約束で町内を裸で馬に乗って回ったという)
ふむふむ…これを読んで、ピンときたわけです。そういえば、ゴディバチョコレートのパッケージに必ず刷り込まれている馬に乗った人の絵!あれが、このゴダイバ夫人の絵に違いない!
そう思ってゴディバのホームページを探してみますと、まさしくその通り、ゴディバの由来はこのゴダイバ夫人のことだったのですね。詳しくはリンク先を見ていただくとして、20世紀ベルギーのチョコレートになぜ大昔のイギリス女性の名がついたのか?
ゴディバの創始者ジョセフ・ドラップスと妻ガブリエルは、レディ・ゴディバの勇気と深い愛に感銘し、1926年ベルギーに誕生した自らのブランドに「ゴディバ」の名を冠した、ということです。なるほど。
ちなみにゴダイバ夫人が恥ずかしさを省みず全裸でコベントリーの町を騎行したとき、町の人たちは皆、夫人の優しさを慮って窓を固く閉ざし、夫人の姿が目に入らないようにしたのですが、たった一人仕立て屋のトムだけが覗こうとし、天罰が下って目を潰されてしまった…これがすなわち「ピーピング・トム」の由来だそうですよ。(細部については諸説あり)
翻ってわが国でも、まさに重税が市民に課せられようとしておりますが。どなたか裸で街を走り回って、時の政府を諌めようとする美しい方は、おられませんかな。
---------------------------------------
(追記)1月末の記事で御神渡りについて書きましたが、その後寒気はますます強まり、4年ぶりにようやく諏訪湖に御神渡りが出現したと報道されました。最も寒かったという2月3日、私は東京にいましたが、この朝は駒ヶ根でもマイナス14℃!の冷え込みだったそうです。ブルル。
関連リンク: ゴディバのエピソード
吹雪の日日々雑記
20120201
夜明け前から窓に当たる強い風で目が覚めました。朝になってから雪が降り始め、みるみるうちに前も見えないような吹雪に。雪は一日中降り、夕方になってようやく止みました。
あっという間に1月が終わりました。この月、駒ヶ根市内で製造業2社が相次いで経営破綻しました。長引く不況の中、それでも駒ヶ根はあまり大きな事故なくこれまでやってきただけに、地元では衝撃的なニュースでした。
どちらの社長さんも私より少し年上の先輩で、中国にもいち早く進出するなど市内の製造業をリードしてきた方たちです。会社の業務内容のことは大して知りませんでしたが、経営者としても人間的にも魅力を感じていたこの方たちがこんな形で会社を畳むことになるとは、大きな驚きでした。
リーマンショックから未だ抜け出せないでいるところへ、大震災のパンチを喰らい、あげくにこの超円高不況ともなれば、市内の多くの製造業の方々の苦しさは言い尽くせないものがあるでしょう。それにしても…
今日は小中高と一緒だった友人の葬儀があり、弔問に伺いました。私と同年ですからまだ50歳です。彼は海外で仕事をしていたりしてここ十数年会っておらず、消息も知らなかったのですが、意外と近いところで暮していたのだということを知りました。バリバリ活躍していたさなかの急死だったそうです。本当に、残念です。
心が重くなる知らせが相次いだ、この一週間でした。
吹雪は止みました。気持ちを取り直して進んでいかなくてはなりません。