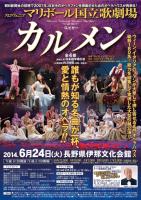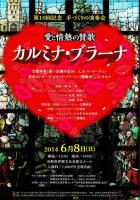アンサンブル音楽三昧音楽ばなし
20141203
1日の日経最終面文化欄に、田崎瑞博氏の記事が出ています。アンサンブル音楽三昧というグループの紹介です。クラシックファンでも誰もが知っている存在ではないと思いますが、私は以前からこのグループの演奏が好きで、何枚かCDを購入し折に触れて聴いています。
このグループは5人の奏者による室内楽です。編成がフルート(各種の笛持ち替え)・ヴァイオリン・チェロ(ヴィオラ持ち替え)・コントラバス・チェンバロ(ハープ持ち替え)という、他にあまり類のない形態で、レパートリーはすべて田崎氏による楽団オリジナルの編曲によります。
選曲がユニークで、大編成の管弦楽曲を縮小編成で演奏したり、逆に独奏ピアノのための曲を室内楽に拡大したりしています。そのアプローチは、よくあるエンタテインメントとは対極で、きわめて真摯な取り組みです。聴き慣れたはずの曲が全く違った姿を見せるのに驚きます。
たとえば、ショスタコーヴィチの交響曲第5番(一切カットなしの全曲)を取り上げたディスクがあります。金管打楽器の鳴り渡る大袈裟な原曲を5人でいったいどうやるのかと思いますが、聴いてみると実に厳しく内省的な曲となっています。元からこういう編成の曲だったのではと思わせるだけの説得力があります。
一方でドビュッシーの「ピアノのために」では、原曲の華々しいグリッサンドが何と上から下へおりてくる!このユニークさ。ピアノ曲にせよ管弦楽曲にせよ、この編成で演奏するにはそれぞれ異なった超絶技巧が求められるようで、特にピアノ曲で10本の指を動かして演奏される早いパッセージを弦楽器で弾くのは、それは大変なことでしょう。
ぜひ一度、生演奏を聴いてみたいとおもうのですが。普段はそれぞれ別の場所で活躍している人たちで、音楽三昧としてのコンサートはそうちょくちょくあるわけでなく、残念ながらまだ機会がありません。
関連リンク: 音楽三昧のホームページ
ラプソディー・イン・ブルー音楽ばなし
20141116
半月も更新をさぼっちゃって…今月は出張やら何やらで忙しく、ついついブログが後回しになってしまいました。。
表題の曲、「のだめカンタービレ」ですっかり世間に有名になりました。中間部のゆったりしたメロディーはTVCMにもよく使われますから、聴いてみれば「ああ、あの曲か」と思われるでしょう。協奏曲と名前はついていませんが、単一楽章のれっきとしたピアノ協奏曲です。
この超有名曲、演奏するものではなく聴くものだと思っていましたが、なんと先週の伊那フィル定期公演で取り上げました。ソロは地元伊那市のピアニスト、林智子さん。
クラシックとジャズを融合させた曲だと評されています。お堅いプレーヤーがいくら楽譜通りきちんと演奏しても様になりません。今回、ピアノのソロはお任せにしても、オケがはて、冒頭のクラリネットの艶めかしいグリッサンドから始まり、カップミュートを使ったトランペットやトロンボーンの色っぽいソロなど、あまりやったことのないジャズっぽさをどこまで出せますかな?
ピアニストとの合わせの練習が前日リハを含めて3回ありました。初回のリハーサルから林さんの意気込みがびしばし伝わってきて、これはいいぞ、と思いました。驚くことにはその後、林さんのピアノが一回ごとにどんどん即興性を高め、凄みを増してくるのです。それを感じたのは、私だけではないはず。
こうなると、オケも燃えますよ。だいたいこの曲はピアノソロの場面が多く、オケの出番はそう多くないのですがね。本番ではさらに洗練さを増したピアノに負けじとオケも頑張り、なかなか良い演奏ができたように思います。お客様からの評価もまずまずだったようで、何よりでした。
今回のメインはブラームス「交響曲第4番」という渋めの曲でしたから、いいコントラストになったと思います。楽しい曲体験でした。林さん、とても良かった!
指揮者の暗譜 (2)音楽ばなし
20140901
指揮者の故岩城宏之氏は、著書の中でたびたび暗譜について書いています。今振っている曲を、完全に空で楽譜を書き起こせるかと言われれば、「正直言って、僕はお手上げだ。インチキをやっていることを、心から恥じる」と心中を明かしています。そりゃそうですよねえ、そんなこといくらプロでも、やたらとできるわけないじゃないですか。
ところが、彼ならきっとできるに違いないと岩城氏が名前を挙げているのが、マゼールなのです。彼の記憶力はまさに超人的。もちろん音楽史上のすべての曲を憶えているわけではないでしょうが、少なくとも自分のレパートリーとしているものは悉く完璧に記憶しているに違いない…と同業者たちには信じられているようです。
暗譜することと、素晴らしい演奏ができるかどうかは、全然別の話ではありますが…。
暗譜に力を入れるより曲の解釈の方が大事だというのは、まったくその通り。プロの名指揮者でも、本番のステージでは決して暗譜で指揮をしないポリシーの人も大勢います。当然、曲中に膨大に存在する勘所はきちんと憶えているのでしょうけれど。
私もコンサートの指揮台に立つとき、神をも恐れず暗譜で臨んだことがあります。最初はまだ高校生の時、吹奏楽部の定期演奏会で。このときは、一応譜面台にスコアを置きましたが、ページをめくることなく十数曲すべてを暗譜で指揮しました。(狂気の沙汰。いったい、いつ勉強しとったのだろうか?)
最後の曲で、大事故が起きました。複雑な場所で何人かの人が出を同時に間違え、続く人たちがどこで入るかわからなくなって、もう曲が止まる寸前まで行きました。万事休すと思いましたが、一人のメンバーが度胸を決めて吹き始めてくれたおかげで、曲は奇跡的につながりました。このときもしスコアを見ながら指揮していれば、もっと早い段階で多くのサインを出すことができ、早く元に戻れていたかもしれない、と悔やみました。15秒ほどのことでしたが。ああ、若かったですね。
指揮者の暗譜は単なる恰好付けではなく、実はいろいろメリットがあるのです。まず譜面をめくるのに、左手をいちいち使わなくてもいいということ。これ、意外とわずらわしいものです。1曲で数十回もあることですからね。
そしてもっと大きいのは、スコアに目を落とすことなくずっとオケメンバーの顔を見て指揮できることです。指揮者は指揮棒で合図するのではなく、目で指揮するのだ、というくらいですからね。私はそう思うのですけれど。
二度目に暗譜に挑戦したのは、伊那フィルを振るようになって3年ほどたった頃。前回のことがあったので本番ぎりぎりまで迷いましたが、音符一個一個まではともかく、曲の進行はきっちり頭に入った、やれると判断して、譜面台を置かずに指揮しました。メンバーとのアイコンタクトが嬉しく、オケがすごく近くになったように感じました。
それ以来、やり慣れたごく小さな曲は別にして、本番を暗譜というのはやっていません。でも、挑んでみたい気持ちはあるのですが。
指揮者の暗譜 (1)音楽ばなし
20140721
名指揮者ロリン・マゼール氏の訃報が先週伝えられました。84歳。つい最近まで元気一杯でコンサートを指揮していたと聞きますから、急なことだったようですね。まだまだ活躍できる人だっただけに、残念です。
私がマゼールの指揮をナマで目にしたのは過去一度だけ(正確には二回)です。昭和63年秋、ミラノ・スカラ座歌劇場の来日公演「トゥーランドット」をNHKホールに観に行きました。この時の公演は、私がこれまでに経験した舞台(芝居、オペラ、コンサートすべて)の中で最大の感動感激でした。マゼールの音楽は大変アクが強く、異様にデフォルメされてある意味奇怪とも言えるようなものでしたが、彼のスタイルがこの曲にはとても良くマッチし、強烈な印象を残してくれました。
演奏の内容もさることながら、この時マゼールは譜面を開くことなく、暗譜で指揮しました。全三幕、演奏時間2時間半、スコア(指揮者用楽譜)で461ページにわたる大編成で複雑な音符と歌詞をすべて頭に入れ、何も見ずに指揮していたのです!
暗譜とは、楽譜を暗記し、前に置かずに演奏することです。ピアニストもヴァイオリニストも、リサイタルや協奏曲では基本的に暗譜をし、曲を完全に頭に入れ体で覚えて演奏します。プロなら、ごく普通のことです。(高齢な人とか、あるいは複雑な現代曲などでは譜面を見ることも多い)
指揮者の暗譜はちょっと意味が違います。自分で音を出すことのない指揮者は、極端に言えば曲の流れさえわかっていれば、一応オケの前で指揮して曲を通すことはできます(私にも、まあ、できます)。でもそんないい加減なことをすれば、楽員たちにすぐバレてしまうでしょうけれど。
オペラの場合は、そうはいきません。歌手たちがステージで演技し歌うのを把握しコントロールしていくのですが、彼らは楽譜を持っていません。出を間違ったり繰り返しを忘れたりといった「事故」の起こる危険性は、普通のコンサートよりずっと高いのです。いや、実際にもしばしば起こるといいます。
その時指揮者はすかさず、この先数十小節の楽譜を瞬時に思い浮かべ、歌手やオケに合図を出しながら(もちろん口なぞ使えませんヨ)曲をどうにかしてつなげ、音楽の進行を元に戻さなければなりません。動揺する関係者を指揮棒一本で落ちつかせ、何事もなかったようにするのですから、すごいことです。暗譜でオペラを振るのは、そうしたリスクにもきちっと対応できる自信があるということです。
本当の厳しい意味で指揮者が暗譜するということは、すべての楽器の音と流れを完全に頭に入れ、何も見ないで楽譜を五線紙上に再現して書き記せる、ということでしょう。交響曲1曲に書かれる音符のオタマジャクシの数は、少なくても数千個、大規模な曲ならおそらく数万個になると思います(私の勘)。いくらプロの指揮者だからって、いったいそんなことが可能なのでしょうか。
カルメン・5分間のステージ (2)音楽ばなし
20140707
当日。観客・兼・関係者という微妙な立場で客席入りします。公演パンフを見ると、出演する子供たちの名はもちろん、合唱指導として私の名前まで出ているではありませんか。日頃ご一緒する音楽仲間、とりわけ合唱関係者の皆様は「何で春日が?」と思ったことでしょう。
オペラは有名な「前奏曲」に引き続いて開幕します。舞台装置はビデオで見た通りのもの。
すぐにやってくる「衛兵の交代」は信号ラッパの合図で始まり、子供たちがキャーキャー叫びながら走って入場してきました。(キャーキャー言って駆け込んでくる、というのも、やってみると案外難しかったりします)衣装がよく似合っています。足踏みをしながら歌い始めます。
心配だったのは、大ホールの雰囲気に呑まれて声が十分出なかったら、と、テンポが走ってしまわないか、の2点でした。指揮者はいつもと違ってオケピットの低い位置にいますし、オーケストラも同様。音の聞こえ方が違います。デモビデオの子供たちも結構走っていましたから、余計に心配。もっとも経験豊かなオペラ指揮者であれば、そんなことはどこ吹く風で、子どもたちにちゃんと合わせてくれるでしょうけれど。
しかし、本番、バッチリでした。声はまあ、本格的な児童合唱団にはかないませんが、あれだけできていれば、私は良しとしましょう。役のキャラクターからいけば求められるのは天使の美しいハーモニーではなく、元気一杯の悪ガキ風の方がふさわしいと思いますから。演技の方は問題なくできていました。(ジュニアオケの子たちが普段から悪ガキだというわけではありませんよ)
テンポが走ることもなし。2回登場する2回目の最後でちょっとだけ声が弱かったかなと思いましたが、オペラの中にきちんとはまり、立派に務めてもらいました。ほっと一安心、あとはリラックスしてオペラを楽しませてもらいましょう…
伊那公演では主役二人はいずれもトリプルキャストの三番手だったようですが(地方公演の常、まあ、仕方がないね)、カルメン役のグアダルーベ・バリエントスさんは女傑的容姿と演技、豊富な声量でなかなか見応え聴き応えがありました。ホセ役のアリヤシュ・ファラシン氏は、この役には声が少々しんどかったかな。演出では、最後に闘牛士エスカミーリョが大怪我を負い、カルメンとホセが対峙する間によろめきながら現われ、そのままカルメンより先に死んでしまう、というのは珍しかったと思います。
こんな大舞台にちょっぴり関わらせていただき、ユニークな経験でした。子供たち、カッコ良かったぞ。
カルメン・5分間のステージ (1)音楽ばなし
20140702
先日、伊那文化会館でスロヴェニアのマリボール国立歌劇場による「カルメン」の公演がありました。こんな田舎でも、毎年のように外来オペラの公演が行われています。私はそれなりにオペラの生鑑賞経験はありますが、超名作カルメンの舞台を全幕きちんと観るのは、実は恥ずかしながら初めてなのです。(ビデオも観たことなかった。音だけだったら全曲版CDで、いちおう聴いていますが)
このオペラ、第1幕冒頭まもなく、子供たちの合唱「衛兵の交代」が出てきます。わずか5分程度の出番ですが、印象に残る場面です。今回マリボール歌劇場は全国各地で19回ほど公演を持ったようですが、児童合唱は本国から連れてくるのではなくて、それぞれの公演地の合唱団の特別参加でまかなったらしいです。十数名~二十数名の子供たちを一ヶ月間帯同する経費と手間、出番の少なさを考えれば、無理からぬこと。事前に楽譜とビデオが送られてきて、当日のリハーサルで歌や演技を一通り確認し衣装を合わせ、即、本番となります。
各公演地それぞれ、地元の児童合唱団などが役を務めたようです。伊那公演ではどうだったかというと、主催の伊那文化会館ではあれこれ考えたようですが、会館付属のわれらがジュニアオーケストラにお鉢が回ってきました。最初に話があったのは1月頃だったかな。
「へえ、いいお話ですね。子供たちにはきっとすごい体験になりますね。…で、誰が合唱指導してくれるんですか?」
「誰って、ジュニアオーケストラ指揮者である春日さんに決まってるじゃないですか」
ええええええ?合唱指導だなんて、声楽のイロハも勉強したことのないこの私が?そんなの、できっこないじゃん!
駄目です。逃げられません。通り一遍のなんちゃって指導でお茶を濁すには、舞台が大きすぎます。入場料も高額です。そして持ち時間は月1回、1回30分の練習のみ。何たるミッションでしょうか。
出番は少なく、譜面もそう難しいものではありませんが、問題は歌詞!フランス語の歌詞を子供たちに覚えてもらわなければなりません。私は学生時代、第二外国語でやっただけ、しかもお情けで単位をもらった口ですが、幸いに私の弟が以前フランス留学経験があり、彼に頼んで歌詞に「ふりがな」をふってもらいました。いやたいへん助かりました。
ジュニアオケのメンバーに地元の声楽教室で歌を習っている子供たちも加わり、小中高、あわせて二十数人の大所帯となりました。オケの子たち、ふだん学校以外で歌なんか歌ってないだろう、どうなるかなと思っていましたら、音程とか初回からバッチリ取れています。日頃から自分で音程を作るヴァイオリンの稽古をしている子たちですから、耳が訓練されているんですね。これにはちょっと驚きました。
4月の1回目の稽古で譜読みをし、2回目にはもう暗譜と細かい歌の表現。3回目は振付も入り歌も演技も本番に近いところまでリハが進み、もうあれよあれよという感じです。(私、演出家でも振付師でもありません!)ビデオを各自家で見てもらいながらですが、皆ちゃんと覚えてくるから感心です。
4回目(本番3日前)最後の練習、声楽教室のO先生に大ホールで後ろまでしっかり聴こえるよう、発声をみていただき、あとは入場から退場までを繰り返し稽古して、私の仕事は終わりました。あとは本番を楽しみに待つだけですが…。
打楽器冥利音楽ばなし
20140529
カルミナ・ブラーナのオーケストラパートには大きな特徴があります。さまざまな打楽器を実に豊富に使い、リズムの強調と多彩な音色効果を打ち出していることです。
私たちがふだん演奏するオーケストラ曲の打楽器を挙げてみます。ティンパニ2~4台(演奏者一人だけ)という曲がまあ基本です。それに加えて大太鼓、シンバル、トライアングルあたりが加わるのはよくある編成。「第九」やハンガリー舞曲などがそうですね。
曲によってはさらに小太鼓、タンブリン、銅鑼など。それ以上増えれば、かなり大き目の編成と言っていいでしょう。マーラーの交響曲とか。ただ、楽器の種類は多くとも、一人当たりの音符の数は実は結構少ないものです。ティンパニ以外の楽器は一曲に数小節、あるいは数発だけ、ということもしばしばあります。
それがカルミナ・ブラーナでは…今回の演奏に当たり私たちが用意したもの、列挙してみましょうか。
・ティンパニ5台 ・大太鼓 ・小太鼓2台 ・合わせシンバル2対 ・吊りシンバル2枚 ・アンティークシンバル(おちょこ位の小さな肉厚のシンバルで、甲高く澄んだ音がします)2個 ・トライアングル2本 ・タンブリン2個 ・銅鑼 ・鈴 ・カスタネット ・ラチェット(機械式のガラガラ)・テューブラーベル(のど自慢の鐘)・カンパーネ(音程を持たない鐘)・A(ラ)のハンドベル ・グロッケンシュピール(鉄琴)3台 ・シロフォン(木琴)
もちろん伊那フィルはこんなたくさんの楽器は持っていません。伊那文化会館のティンパニに加えてご近所の中学、高校、一般吹奏楽団、それに個人持ちのお品を拝借します。タイのアンティークシンバルとインドの鈴は私が以前から持っているもので、とてもいい音だと我ながら思っています。「音程を持たない鐘」は親しい管工事屋さんに頼んで作ってもらいました(写真下、大太鼓の手前にぶら下がっています)。グロッケンシュピールはどこにでもある楽器ですが、3台同時に鳴らす曲などまずないでしょう。
これらを6人で演奏します。驚くことに6人ともがほとんど出ずっぱりです。ほぼ全曲を通して打楽器がドンジャカチンパカと鳴り渡る、これが珍しい。25曲の中で打楽器が完全にお休みの曲はわずか2曲だけ、中には弦楽器も管楽器もお休みで、ピアノと打楽器だけが声楽の伴奏を務める曲もあります。
そういうわけで、打楽器奏者としてこんなにやりがいのある楽しい曲は滅多にありません。伊那フィルには打楽器奏者はふだん2人しかいませんので、今回は各地の打楽器仲間に応援を頼んでいます。いずれも百戦錬磨の腕利き揃い。ステージにズラリと並んだ打楽器と多彩なリズム・音色をぜひお楽しみいただきたいと思います。
カルミナ・ブラーナ音楽ばなし
20140528
来月初めのコンサート、宣伝も兼ねて。。
「手づくりの音楽会」と称し、地元の公募合唱団と伊那フィルの合同企画が多くはこの時期に、ほぼ隔年で行われております。10回目を迎える今回の曲目は、カール・オルフ作曲の大作「カルミナ・ブラーナ」です。先日会場練習が行われ、地方紙にも記事がやや大きく載りました。大編成の管弦楽、2台のピアノ、合唱、児童合唱、3人の独唱者、そして舞踊を伴う大曲です。(普通は舞踊なしの演奏が多い)
この曲は、どなたにとっても、聴いて大変面白い曲だと思います。歌詞は中世ヨーロッパの修道院に伝わる、無名の修行僧たちの落書きみたいなものです。厳しい戒律に縛られた生活とうらはらに、春を愛し、酒におぼれ、男女の性愛をもあけっぴろげに賛美した歌詞がこれでもか、と綴られます。はっきり申してかなり下品なところもある詩なのですが、そこには人生の喜びを歌うエネルギーがむんむんと詰まっています。そして最初と最後には輪廻としてめぐる無慈悲な運命が登場し、世の厳しさをどんと思い知らせます。
近代ドイツの作曲家オルフがこの詩に曲をつけました。作曲年代は第二次大戦直前で比較的新しいのですが、書法は極めてシンプルで、原始的で、血が湧き起こるような激しいリズムが特徴です。内容は25の小曲からなり、冒頭の曲「おお、運命の女神よ」はTVCMなどでいやというほど用いられていますから、お聴きになれば「ああ、これか」と思われるでしょう。
私はずっと以前からこの曲のファンで、世の中にCDというものが登場し、30年ほど前、人生初めて購入したCDはムーティ指揮のこの曲でした。夢だった全曲演奏を地元でできることが今でも何だか信じられないような気がしています(吹奏楽アレンジなど、抜粋ではしばしば取り上げられますが)。初めての合唱合わせ練習で冒頭の音が轟然と響き渡ったとき、鳥肌が立ちましたな。
準備は着々と進んでおります。本番は6月8日(日)午後2時開演、伊那文化会館にて。あわせてベートーヴェンの交響曲第2番も演奏します。ぜひ多くの方にご来場いただきたいです。
カルミナ・ブラーナに使われるたくさんの、たくさんの打楽器については、次回で…
関連リンク: 第10回記念 手作りの演奏会 facebook
偽装交響曲音楽ばなし
20140212
語られることは語られつくした感がある、偽ベートーベン事件。水に落ちた犬を、もう日本中がすごい勢いで叩きまくっておりますな。私も格好のブログネタだと思いましたが、出張ということもありすぐに記事を書けませんでした。それでもせっかくの音楽ばなしですから、少しふれてみたいと思います。
代表作?とされる「交響曲第1番HIROSHIMA」は、ほんの一部を聴いたことがあるだけです。以前東京のCDショップに寄ったとき、店内でさわりの部分を繰り返し繰り返しかけていました。マーラーの交響曲第3番の終楽章にとてもよく似ていて、マーラーにこんな曲があったかな?というのがそのときの感想。同じことを多くの人が指摘していますね。
あまり何度も続けてかかるので、いったい何だろうこの曲は、と怪訝に思いました。改めて見てみると店内にはあの長髪黒眼鏡のポスターが貼られこの曲のCDが山積みされ、クラシック売り場では珍しい大掛かりなプロモーションでした。耳ざわりの良い曲でしたが、CDを買ってまで聴こうとは思いませんでした。
まんまと騙されて佐村河内氏をスターにしてしまった例のNHKスペシャルは、たまたまテレビをつけたらやっていて、終わりのほうだけ観ました。「名曲探偵アマデウス」で解りやすい楽曲分析をしていた野本由紀夫氏が、スコアを見ながら「一音符たりとも無駄な音がない」と激賞していました。こんな褒められ方をするような曲なのかと違和感を感じたのは、後だしジャンケンではなくて、本当です。
ゴーストライターだった新垣隆氏は、私はこれまで知らない人でしたが、現代音楽の世界では作曲家・ピアニスト・指導者として著名な人だそうです。彼の本来の仕事である前衛的な作風と「佐村河内テイスト」とは全く異なるもので、芸術的な内なる欲求とは全然別のところで作曲の職人技を駆使し、誰にもわかりやすい「名曲」を書いたということになります。(聴いていないので、私にはこの曲そのものへの評価はできませんが)
曲本来の魅力で勝負するのではなく、「聴覚障害者の被爆二世が独学でこんな素晴らしい曲を書いた!現代のベートーベンだ!」という物語が売られ、十万枚を超える大ヒットになりました。ベートーヴェンは、耳が聞こえないのに作曲したから凄いのではなくて、作った曲そのものが彼以前にも以後にも全くないような独創的で素晴らしいものだったから、凄いのです。彼が聾者でなかったとしても、音楽史の頂点に輝く存在であることは間違いありません。
第二の物語はクラシック界のみならず日本中の人々を呆れさせるスキャンダルになりました。こうなってしまっては、この曲が演奏されることは二度とないでしょうね。CDも廃盤間違いなし。異常に持ち上げられた曲が、今度は強烈なバッシングを受け奈落へ落とされるこの状況を見ると、曲に罪はないのに、とも思います。そのうちブックオフの100円コーナーででも見かけたら、買って聴いてみましょうか。
いや待てよ、それより伊那フィルの定期公演で演奏すれば、きっと結構な話題になるな。だいぶ編成がでかい曲らしいから、手がけるのは大変かもしれませんけど。
新春はオペラアリア音楽ばなし
20140113
ニューイヤー・コンサート。ウィーンフィルのものは世界中に衛星中継され絶大な人気を集め、皆さんご存知ですね。伊那でもここ何年かにわたって声楽を中心にした企画で行われてきましたが、今回私も初めて出演することになりました。
今年の企画は伊那市出身イタリア在住のソプラノ、白鳥千絵さんの独唱。前半はピアノ伴奏でイタリア歌曲など、後半に室内オーケストラ伴奏でオペラアリアを数曲。後半の指揮をしました。
ベッリーニ/ああ、いくたびか (カプレーティとモンテッキ)
プッチーニ/王子様お聞きください (トゥーランドット)
マスカーニ/カヴァレリア・ルスティカーナ間奏曲(この曲はオーケストラのみ)
プッチーニ/私が街を歩くと (ボエーム)
ロッシーニ/今の歌声は (セヴィリアの理髪師)
プッチーニ/私のお父さん (ジャンニ・スキッキ)(アンコール)
どうしてイタリアの作曲家はみんな同じような名前なんでしょう。なんてことはどうでもいいのですが、年末年始4回の練習(うち歌合わせ2回)という突貫工事で曲を作ってきました。
独唱の人と協演することは私もオケもあまり経験がありません。ベッリーニ以外は私は馴染みのある曲ではありましたが、聴くと振るとはいや大違い…「メンバー誰もやったことのない曲」を短期間で仕上げるのは、プロならぬ私たちにはかなりハードルは高いですねえ。
1月4日に初めて歌合せしたときは、オケもまだ全然弾けていないし、私も自由自在に伸びたり縮んだりする歌にどうやって合わせたらいいのかついていけず、本当に一週間後に本番?と思いました。まあ勉強不足ってことですわ。
しかしオケは数日の間に曲をだんだん飲み込んで棒についてきてくれるようになりました。私も白鳥さんの節回しや歌詞(もちろんイタリア語ですよ)を聴いて合わせながらオケをコントロールできるようになってきて、これなら本番いけるかな?と思ったのはコンサート前々日のこと。まだ心配な場所はいくつもありましたけれど。
当日、会場いなっせは超満員。不安の残った場所はどこもうまくいきました。緊張して指揮しながら聴くオペラアリア、本当に美しいメロディーばかり!白鳥さんの明るく艶のかかった歌声に合わせて、イタリアの歌心を楽しむことができました。
私の指揮の師匠はオペラを専門としていて、彼の振るオペラを時々観に行きますが、よくあんなに楽々と振っているものだと改めて思います。ぜひまたオペラ曲を演奏してみたいものです。
p.s.打上げでお話ししていましたら、白鳥さん、私の高校の「吹奏楽部」の後輩だとわかって、これはびっくり。