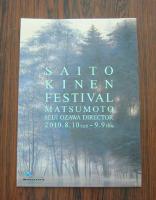ゲルギエフ vs 諏訪内晶子音楽ばなし
20101126
ロンドン交響楽団公演
指 揮 ワレリー・ゲルギエフ
ヴァイオリン 諏訪内晶子
曲 目 ヴェルディ:「運命の力」序曲
シベリウス:ヴァイオリン協奏曲
ムソルグスキー:展覧会の絵
長野県松本文化会館(11月25日)
人気絶頂のスター2人の共演です。オーケストラも含め、素晴しかった。
どちらもナマで聴くのは初めてです。ゲルギエフはとにかくチャーミング!ヴェルディではリズムが躍動し、果汁が弾け飛ぶようなフレッシュ感をイメージしました。緩急が絶妙です。
ムソルグスキーでは「いったい次の瞬間には何をやらかすのか?」といった意外性の連続。そうかこういう表現もあるんだなー、と大いに楽しみました。「古城」の大きな溜め息がとても印象的でした。
金管、さすがにイギリスの音だあ、上手い。サックス、テナーテューバ、ファゴット、いずれも良かったです。変幻自在の指揮にオケがよくついていったと思います。(少しだけ、えっ…と思うところもありましたが、ご愛嬌)
そして何と言っても諏訪内晶子!冒頭からシルクのような、手触り感のある美音。音量もたっぷり、流れるような表現、濃密な時間。女豹的な研ぎ澄まされた鋭さよりは、もっと大きくグラマラスな音楽なのかな。正直に言うと、シベリウスのこの曲に今まであまり魅力を感じたことがなく、苦手としていたのですが、今回初めていいなと思いました。
ルックスもいいですね!美人で長身で、スタイル抜群、堂々としたステージマナー。オケも指揮者もすべてを手の内に入れながら、もう楽々と弾いているように見えます。この方は「アイドル」なのかと何となく思っていましたが、申し訳なかった、すごい「音楽家」だわ。
残念ながら客席には多くの空席がありました。どうしてでしょう?松本の人は、サイトウキネンには熱狂するのに、他の素晴しいコンサートには関心がないのですかね、なんて言いたくなりました。
いやあ堪能しました。
運命かく扉を叩く音楽ばなし
20101108
出だし(だけ)は誰でも知ってる「ダダダダーーン」。
ベートーヴェン:交響曲第5番ハ短調、通称「運命」。
今度の日曜日、伊那フィルハーモニー定期演奏会の曲目のひとつです。
本番一週間前ということで、伊那市民会館を借りて集中練習が行われました。
ベートーヴェンの9つの交響曲はいずれも名作中の名作で、特に奇数番号の曲はアマチュアオーケストラの基本レパートリーとなっています。私もこれまで1、3、4(これをやった人は少ないでしょう)、7、9番のティンパニ演奏経験がありますが、実は運命は第1楽章しかやったことがなく初めて全曲を叩きます。(指揮したことはありますが)
超有名曲ですが、伊那フィルにとってはなかなかの難曲でして。楽器間の連携プレイがうまくいかず、リズムがストレートに運びません。お互いを聴き、反射神経を磨いて臨むという簡単そうなことが、難しいんだな。
冒頭の「ダダダダーーン」のリズムの意味を、弟子がベートーヴェンに聞くと、「運命が扉を叩く音だ」と答えたそうです。ちょっと運命のノックにしては、気ぜわしいような感じもしますね。あくまで愛称であり、ベートーヴェン自身が曲を運命と名づけたわけではありません。
一気呵成の直球勝負のような曲をベートーヴェンは書きました。剛速球をしっかり受け止められるだけの力と必死さが必要です。日曜の本番では、お客様にどんな演奏をお届けできるでしょうか。
本番は11月14日(日)午後2時~ 県伊那文化会館です。運命のほかに、チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 を演奏します。(こちらがメイン曲です)
関連リンク: 伊那フィルハーモニー交響楽団
アフリカの太鼓音楽ばなし
20101025
駒ヶ根にはJICAの青年海外協力隊訓練所があり、国際協力のまちとして様々なボランティア活動や国際交流活動が行われています。
その中でも最も大きなイベントである「こまがね国際広場・みなこいワールドフェスタ」が、24日行われました。
近所にはあまりない特色あるお祭りです。世界各国~とりわけアジア、アフリカ、中南米などの発展途上国~の民族食や民芸品の販売、国際協力のボランティアにかかわるいろいろな展示、そして民族音楽やダンスパフォーマンス。そのステージで、地元の小学生たちと一緒にアフリカの太鼓を演奏してきました。
私とアフリカの太鼓は、もう15年間にわたるつながりです。本気で書けば、軽くこのブログ三週間分位のボリュームになりそうな歴史がありますよ。ひとつだけいいますと、私のアフリカンドラムは、セネガルの生んだ世界的巨匠、ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ師とその一族の直伝なのです。
ドゥドゥはセネガルでは国民的英雄だそうです。何十人もの息子たちと共に(セネガルは一夫多妻制)アフリカンドラムの大合奏団を作り、みずから多くの曲を作曲し、80歳近い高齢をものともせずに世界をまたにかけて活動しています。
1996年8月、彼ら一行17人は駒ヶ根青年会議所(JC)の招きで駒ヶ根を一週間にわたって訪れ、地元の小中学生に太鼓の手ほどきをし、駒ヶ根高原スキー場の特設ステージで野外コンサートを行い、その中で特訓を積んだ子供たちとの共演を行ないました。この企画を発案したのが私です。
それはそれはお金もかかったし、莫大なエネルギーを要しました。本当に多くの人の理解と協力をいただいて実現した事業でした。参加した子供たちは、ドゥドゥたちの物凄いパワーを目の当たりにし、自分もその中に参加して曲を作り上げていくことで、忘れられない感動を持ったと信じます。
ドゥドゥや彼の息子の太鼓奏者たちはその後何度も駒ヶ根を訪れ、多くの人に太鼓の魅力を伝えてきました。今では子供たちがいつでも演奏できるよう、本物のセネガルの太鼓サバールを数十台用意し、私や仲間たちがいろいろな機会に子供たちと太鼓のワークショップを行なっています。
今年は地元の小学校5年生のクラスが、総合学習でアフリカンドラムに取り組んでいます。この国際広場で、彼らは公の場で二度目のお披露目演奏をしたのです。私たち講師3人に、地域の愛好家3人の友情出演もあわせて、おそらく子供たちには全く想像できなかったような盛り上がった演奏になりました。
実は、伊勢喜の社内にもアフリカンドラムのチームがあります。創業百周年の祝賀会のときに結成され、つたないステージを披露しました。それ以来何年かに一回演奏するだけですが、社員の結婚式の時にお祝いの太鼓パフォーマンスをプレゼントしています。
佐野成宏リサイタル音楽ばなし
20100917
昨日は駒ヶ根が生んだ世界のテナー、里帰り公演でした。。
佐野成宏テノール・リサイタル
ラッファエレ・コルテージ(ピアノ)
駒ヶ根市文化会館
会場はほとんど満員。いつもながら、年配の方が多いです。
前半に武満徹の歌曲を8曲。後半にはトスティの4曲など、イタリア歌曲とアリア合計7曲を歌いました。
相変わらずの輝かしい声、安定した歌いぶり。武満の歌は私も何曲かは知っていましたが、こうしてまとめて聴いてみると、憧れに満ちたもの、コミカルなもの、深い悲しみと憤り、バラエティ豊富ですね!表情豊かに歌い分けていたと思います。名曲「死んだ男の残したものは」では、ぞくっとするような凄みに、会場も引き込まれていました。
日本人のオペラ歌手が日本語の歌をうたっているのに、歌詞がまるでわからない、ってことが時たまあります。本来ありえないことですよね…
佐野さんはもちろんそんなことはなく、言葉が丁寧に扱われているのがよくわかります。
イタリア歌曲は、もう十八番ですから、言うことはありませんね。堪能しました。
初めて聴いたとき(十年以上前)の驚くような声量は、この夜はありませんでした。表現上そこまでは必要なかったということなのか、どうなのかな。
残念だったのは、客席です。終始ざわざわ、ガサゴソ、ギシギシ。美しい沈黙あってこその生演奏なんだがなあ。さらに驚いたのは、後半、会場でコオロギ?!が鳴きだしたことです。これには、まいりました。
武満の8曲に、1曲1曲拍手をするのは、やはりどうかと思います。演奏者は思いを込めて8曲を並べているはずで、そこには緩急、流れ、コントラスト、というものがあります。1曲1曲に拍手があっては、その組み立てが台無し、とまでは申しませんが、かなり興をそがれてしまいました。トスティの4曲でもそうでした。
演奏者を見ていれば、拍手をしないでほしい場所では、拍手があってもそれに応えていないのですから、客席もわかってほしいなあ…せっかく地元から生まれたスターです。彼の素晴しさを、さらに良い雰囲気で聴き、感じ取りたいと思います。
主催された後援会の皆様、お疲れさまでした。
歌手と減量音楽ばなし
20100826
サロメ役を演じたデボラ・ヴォイト、体格堂々と書きましたが、実は彼女、以前はもっともっと堂々としており、大変な減量をして今の姿になったことで有名です。。
2004年、彼女はロンドンの国立オペラで「あまりにも太りすぎて、指定の衣装が着られない」という理由で、既に決まっていた主役(ナクソス島のアリアドネ)を降ろされているのです。
デボラはさぞかし憤慨したでしょうが、思い切って胃のバイパス手術を受け、4年間で百ポンド(約45㎏)以上の減量に成功しました。その後、英国立オペラにも同じ役で見事に復帰。写真は、減量前と減量後のデボラです。それまで何キロあったんだろう?
ご承知のようにオペラ歌手は身体そのものが楽器ですから、豊かな声のためならばと、豊満な体型を気にしない女性も多いです。森公美子さんなんて、そんな感じですよね。(もちろん、スマートな歌手もたくさんいますが)
しかし役柄とあまりにかけ離れた体型は、昔ならいざ知らず今では、さすがに感興をそがれると感じる聴衆も多いのです。結核で弱って今にも死にそうな病人が、ベッドがきしむような体重の持ち主では、幾らなんでも不自然ということですね。今回のサロメも、以前のデボラが演じていたらと想像すると、やはり舞台の印象がだいぶ違ってきただろうと思わざるをえません。
そもそもサロメは、①強靭な声と②可憐なルックスが求められ、おまけに③踊りも見せ④しまいには全裸に!という極めて難しい役です。この条件をすべて満たすソプラノは、世界中でもほとんどいないでしょう。
④が一番難しいように思いますが…マリア・ユーイングという有名な歌手は本当に全裸になっています。十数年前にNHKでも放送されました。他にも勇気ある歌手は何人かいるようです。今回デボラは、一瞬脱いでいるかのように見せてはいますが、脱いでいません。
おっと、裸の話ではなく減量の話でした。もともと声量豊かな、ドラマチックな役を得意としていたデボラでしたが、減量したことでの声への影響はなかったようで、何よりでしたね。演技の幅も当然大きく広がったことでしょう。
関連リンク: デボラのインタビュー(英語です)
サイトウキネン/サロメ (続き)音楽ばなし
20100825
公演を観ての感想。。
舞台はシンプルながら立体的で、ゴージャス感はないものの、よく考えられていました。シカゴでのプロダクションを持ち込んだものです。古井戸は蚊帳のように透けて見える四角いテントで囲まれ、その中から鉄格子の檻がせり上がってくる仕掛けです。また高いところに回廊が設けられて、歌手は2階と1階を行き来しながら歌います。
照明がとても良くできていて、美しく(時に、おどろおどろしく)効果的に見せました。
主演のデボラ・ヴォイト。とても良かった!オペラ歌手の常で、体格堂々たる女傑が10代の少女を演じる違和感はどうしてもあるわけですが、あまりそれを感じさせない演技で、ちょっと驚きました。可愛さ、さえ感じる部分もありました。歌は勿論素晴しかった。終始安定した美声で、声量も充分でした。
お楽しみ、七つのヴェールの踊りは…自分で踊ったのは立派でしたが(この部分だけダンサーが代わって踊ることもよくあるのです)妖艶というより、所によっては何だか巨牛がロープを引っ張りながら暴れているようにも(失礼!)。踊りの後も息が乱れることなく長大なモノローグを歌いきりました。お見事。
ヨハナーンのアラン・ヘルドも良かったですね。預言者というよりは、サムソンみたいなマッチョな感じでしたが。ナラボートのショーン・パニカーも、急遽代役ということでしたが、いい歌と演技でした。
ヨハナーンを檻につないでいた太いロープにこだわった演出で、サロメはヨハナーンが井戸に帰ってからもときどきロープを抱きしめ匂いをかぐし(あんたは、のだめか!)幕切れ、通常なら兵士の盾に押し殺されるサロメが、ここではこのロープで首を絞められて絶命します。あえてそうするほどの効果があったかどうかは、疑問かな。
サロメがヨハナーンの首を抱えて歌うところ、いかにも「張りぼて」みたいに軽々とちっちゃな首を持ち上げていたのは、ご愛嬌。首といえば、エレベーターですっすとお盆に載った首が上ってきたのは、ちょっとあっさりしすぎでは?
オーケストラは、雄弁でした。キラ星のようにスーパースターが揃い、管楽器のソロの音色だけで陶酔感を味わえたサイトウキネン初期の頃の響きは今は聴かれません。そういう意味では普通のオーケストラになってきたのかもしれませんが、目指す音楽に進む一体感みたいなものは、凄いと思います。
オケピットのスペースの都合か費用の問題か、編成はいくらか縮小されていたようです。日本に何本もない希少楽器「ヘッケルフォン」がこの曲では使われるはずですが、見当たらず。他にも管楽器に省略されたパートがあったように見受けましたが…そうであれば、残念。もし勘違いだったら、ごめんなさい。
そして、指揮者。弱冠28歳の大抜擢、日本デビュー!良く頑張った、と思います。破綻なくこなしていました。弱音のところ、緊張感のある「間」がもっと欲しいな、というところもありました。事前に読んだオケメンバーのツィッターに、リハーサルでのテンポの速さが指摘されていましたが、私は不自然なほどの速さとまでは感じませんでした。
悪口も書きましたが、全体を通して、とても満足しました。そもそも曲の大ファンなので、ナマで見て響きに浸れただけでもOKかな?田舎にいてこんな演目を、高水準のパフォーマンスで観られたことに感謝したいと思います。
サイトウキネン/サロメ音楽ばなし
20100824
信州の夏を盛り上げる音楽祭。その中の最大イベントである、オペラの上演に出かけてきました。
リヒャルト・シュトラウス作曲「サロメ」 松本市民芸術館
指揮:オメール・メイア・ヴェルバー
サロメ:デボラ・ヴォイト
ヘロディアス:ジェーン・ヘンシェル
ヘロデ:キム・ベグリー
ヨハナーン:アラン・ヘルド
ナラボート:ショーン・パニカー
「サロメ」、ずっと前からCDやビデオで親しんでおり、大好きな演目です。これまでナマで観る機会がなく、一度どうしても観てみたかったのです。例年と違って小澤征爾氏の指揮でなかったためでしょう、チケットは苦労せず手に入りました。
物語は、情念が渦巻き、生々しく、陰惨で、まあ…凄い話なのですよ。
---------------------
2000年ほど前、キリストの頃のエルサレム。ユダヤ王ヘロデは、兄を殺し、兄の妻だったヘロディアスを王妃に迎えています。サロメはヘロディアスの連れ娘で、まだ十代の少女。
ぞっとするような不思議な月が美しく輝く宴の席で、義父ヘロデに好色な目で見つめられていたサロメは、テラスに逃れてきました。すると、地下から不気味な声が聞こえます。ヘロデによって古井戸に閉じ込められていた預言者ヨハナーンが、不貞の王妃ヘロディアスをののしる声でした。
興味を持ったサロメは、預言者をひと目見たいと若い護衛隊長ナラボートに迫ります。王からは固く禁じられていましたが、ナラボートはかねてから恋心を抱いていたサロメの妖艶さに負け、ヨハナーンを外に出してしまいます。
サロメはひと目でヨハナーンに心を奪われますが、ヨハナーンはサロメの誘いには耳も貸さず目もくれず、サロメがくちづけを求めると、呪いの言葉を吐いて井戸の底へと戻っていきます。ナラボートは絶望のあまり自害します。
ヘロデが妻ヘロディアスを伴い登場します。サロメに踊りを所望するヘロデ。サロメは始め断っていましたが、踊りを見せれば褒美に何でも望みのものを与えるとヘロデが約束し、サロメは有名な「七つのヴェールの踊り」(7つのヴェールを次々と脱いでいき、しまいには全裸になる)を踊ります。
満足したヘロデが、サロメの望みを尋ねます。「ヨハナーンの首を」とサロメ。とんでもない望みに、内心ではヨハナーンを恐れていたヘロデは驚愕し、やめさせようと説得しますが、サロメはかたくなに首を求めます。ヘロデはついに屈服し、ヨハナーンの斬首を命じます。
銀の盆に載せられたヨハナーンの首を持ち上げ、歓喜に身を震わせ、くちづけをするサロメ。それを見て恐怖にかられたヘロデは、兵士たちに命じてサロメを殺してしまいます。
------------------------
音楽がまた物語に輪をかけて凄まじいのです。調性感は限界まで崩れ、大編成のオーケストラが複雑にからみあい、身の毛のよだつような響きを聞かせます。ワンフレーズごとに表情を変えながら、約1時間40分(オペラとしては短いですが)を一気に持っていく力技には感嘆します。
上演は、大いに聴き応え見ごたえがあり、大変満足しました。感想は、次の回で。
涼しげな曲音楽ばなし
20100806
まいります、猛暑もこう続くと…。
冷房とビール以外に少しでも暑さをしのげるアイテムは?
いろいろありますが、BGMというのは涼しげな環境にいくらか効果があるのではないかと思います。
ギラギラした太陽光線を吹き飛ばすようなエネルギッシュな曲もいいでしょう。しかしここではもっとストレートに、ひんやりした肌触りで心を静めてくれるような曲を挙げてみましょう。
ベタですがずばり、フランス近代のピアノ曲が最適!とりわけ、ラヴェルのものがいいと思います。「水の戯れ」「ソナチネ」「クープランの墓」どれも良いですね。
涼しい曲第一位の「水の戯れ」は、5分ほどの小曲です。題名からして涼しげですね!曲の冒頭から、硬質クリスタルのような響きが美しい。動きが激しくなっても、決して熱くならない音のきらめき。短い曲中、水は流れ、噴きあがり、ときによどんで様々な形態を見せてくれます。
中学生の頃この曲が好きで好きで、楽譜を取り寄せ弾いてみようと思いましたが、あまりにも難しく撃沈しました。
水を題材にした曲としては、ラヴェルが「水の戯れ」の着想を得たといわれるリストの「エステ荘の噴水」、同じラヴェルの「オンディーヌ」、そしてドビュッシーには名曲「水の反映」があります。いずれもそこそこの涼しげ度です。
ドビュッシーで水つながりだと「金色の魚」の方が涼しいでしょうか。「喜びの島」も、水つながりと言えないこともないですね。
最近聴くようになった曲で、フォーレのピアノ5重奏曲。運転中に聴くことが多いですが、結構涼しさ感があります。室内楽は基本的に食わず嫌いをしてきたジャンルで、今でも全く疎いのですが、少しずつ聴き始めています。
一方で「暑苦しい曲」というのもありますね。チャイコフスキーやベートーヴェンの交響曲なんて双璧だと思います。
猛暑の中で、よりによってこの両者を練習中のオーケストラが私の身近にあるのですが…うーん、早く涼しくなって!としか言いようがないです。
サロンコンサート音楽ばなし
20100708
「しんきん高遠会」の総会にお招きをいただき、アトラクションとして室内楽の演奏会をしてきました。。(高遠さくらホテルにて)
といっても、私は今回は演奏は無しで、ご案内役(司会者)。演奏は日頃一緒に活動している弦楽器の先生と仲間たちが担当しました。1時間のコンサートで、モーツアルトのディヴェルティメント(k136)とアイネ・クライネ・ナハトムジークを両端に置き、間に小品をいくつか。お客様は、どうでしょう40人近くいらっしゃったかな。当社のお得意様も何人かお見えでした。
普段からクラシックに馴染みの方ばかりでないコンサートのときは、構成には普段以上に気をつかいます。飽きられないように、与えられた時間をどういう流れにするのか、親しみやすさはもちろん、変化も大事です。
演奏を聴きながら司会席に座ってお客様の反応を見ていましたが、楽しんでいただいているように思いました。もちろん腕利き揃いによる演奏あってのことです。(演奏には何の心配もしていませんでした)
終わって懇親会の席、感想を伺ってみました。弦楽器とはいえ、想像以上の迫力(音量)に驚かれた方がいらっしゃった。これはCDではわからない、ナマの醍醐味というやつですな。同一空間にいて、空気が振えるのを肌で感じる楽しさを味わっていただいたことが、とても嬉しかった!
スターバト・マーテル音楽ばなし
20100608
時々音楽ネタも書きます。この週末、私の出演した演奏会です。
手づくりの「スターバト・マーテル」演奏会
6月6日 長野県伊那文化会館
ワーグナー:「タンホイザー」序曲
ドボルザーク:スターバト・マーテル
指揮 荒川昌美/春日俊也
独唱 地元ゆかりのプロのソリスト4人
合唱 特別編成の地元合唱団130人
オーケストラ 伊那フィルハーモニー交響楽団
ドボルザークの大規模な声楽曲の前に(前座で)ワーグナーの管弦楽曲を1曲。これが私の担当で、指揮をさせていただきました。
タンホイザーは15~6分の曲です。人気ドラマ「白い巨塔」で、唐沢寿明扮する財前五郎教授のお気に入りの曲とされ、彼が病院の屋上で空に向かって手術のイメージトレーニングをする際に使われました。実に印象的な場面で、今でも忘れられません。
素朴で美しい響きで始まり、中間部はとても派手で輝かしく、最後はゴージャスに豪快に終わる、山あり谷ありの曲、です。
昨年末から練習がスタートしましたが、私たちにはいささか難しく、曲が中々形にならずに苦労しました。直前まで心配だった幾つかの箇所が、本番ではいい方へ動いて、どうにか納得できる演奏になりました。聴いて下さった方は、どう感じられたでしょうか。
メインであるスターバト・マーテルは演奏時間1時間半の大曲で、全曲が演奏されるのは県下初だったとか。荒川さんは箕輪町ご出身、まだまだ珍しいプロの女性指揮者で、見ていてもとても張り切った様子で故郷でのデビューに臨み、喝采を浴びました。
正直言うとアマチュアオーケストラにとっては、声楽曲を練習していくのは、曲の全貌をイメージすることがなかなかできず、独特の難しさがあります。それにこの曲は本当に長い!交響曲2曲分の長さですから。
私はこの曲では副指揮(荒川さんの助手として、下準備や楽譜のチェック、荒川さん不在のときは代わって練習をつける)をしてきましたが、本番は出番がないので客席で聴きました。(ちょっと寂しいね)オケは危なかった所もありましたが、何とか乗り切りました。
独唱4人が粒が揃っていて、とても良かったと思います。
何年かに一度、伊那では声楽・オーケストラ合同でこうした大曲に挑んでいます。本当にいい機会だと思います。
ご来場いただいた方、ありがとうございました。
関連リンク: 手づくりの演奏会